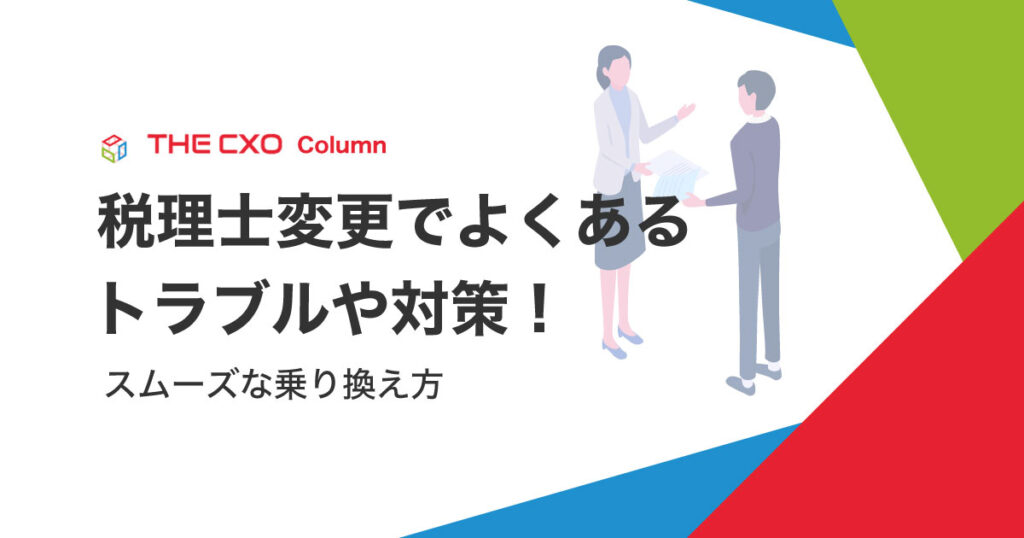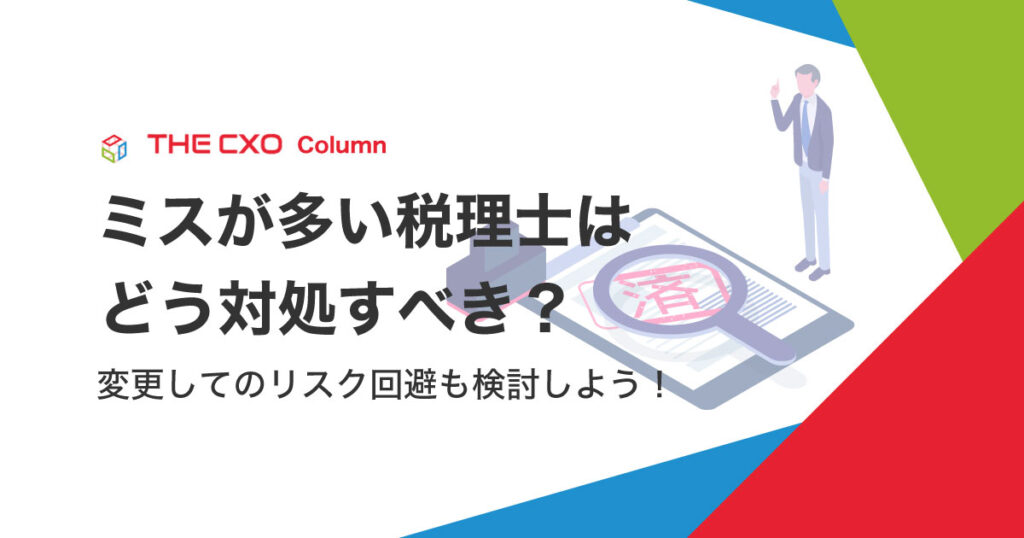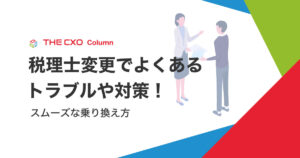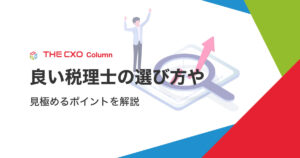税理士への不満がある!違和感を覚えたら取るべき行動とは?
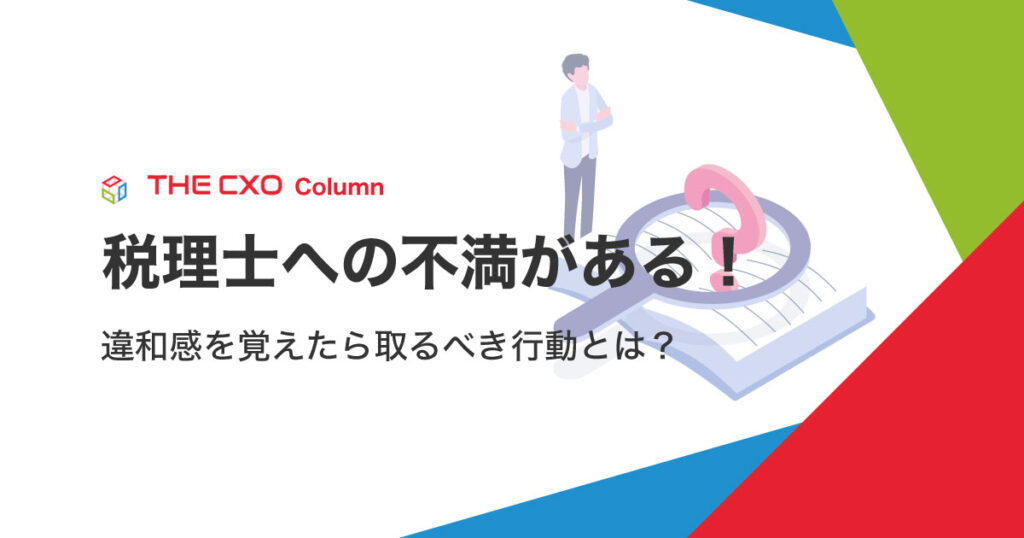
税理士との関係に、次のような不満を感じたことはありませんか?
- 「税理士に頼んでいるのに、経営の役に立っていない」
- 「相談しても返事が遅く、的確なアドバイスがもらえない」
- 「料金が高いのに、サービスの内容がよくわからない」
このように、税理士に対する違和感が積み重なり、不信感へとつながるケースは少なくありません。
しかし、税理士への不満をそのまま放置してしまうと、会社の成長に悪影響となる可能性があります。
税理士がきちんと経営をサポートしてくれないと、本来支払わなくてもよかった税金を余分に払ってしまったり、融資や補助金のチャンスを逃してしまったりすることもあるのです。
この記事では、税理士に不満を感じたときに取るべき具体的な行動を解説します。
株式会社カタリスタ 代表取締役
THE CXO 株式会社 代表取締役
飯島 彰仁(いいじま あきひと)
Iijima Akihito
経営計画コンサルタント、中小企業の社外CXO。大手会計事務所元代表取締役社長として、同社を年商22億円、従業員数447名の規模にまで成長させた実績を持つ。
これまで3,000社以上の中小企業に対し、財務やマーケティングを通じた経営向上に貢献。
その中で、中小企業の成長のためには、単なる税務処理を超え、経営に深く関与する税理士が必要不可欠であることを痛感。
その経験をもとに、税理士が真の価値を発揮する「社外CXOメソッド」を開発。累計300人以上の税理士に伝授し、「税務の枠を超え、中小企業のあらゆる相談に乗れるパートナー」を養成。
指導した税理士達からは、顧問先の売上向上、利益向上、V字回復や事業改善など成功報告が続々と寄せられている。

- 1. よくある税理士への不満
- 1.1. コミュニケーションがスムーズにとれない
- 1.2. 経営のアドバイスや提案がない
- 1.3. 何をしてくれているのかわからない
- 1.4. 税理士がITやデジタルに対応できない
- 1.5. 担当者が頻繁に変わる
- 1.6. ミスが多い
- 2. 税理士への不満は、企業と税理士のミスマッチによって起こる
- 2.1. 担当者(担当税理士)とのミスマッチ
- 2.2. 企業が期待することと税理士のスタンスのミスマッチ
- 2.3. 企業の成長フェーズによる税理士に求められる役割の変化
- 3. 「今の税理士で大丈夫?」不満を感じたらチェックすべき3つのポイント
- 3.1. 担当者のレスポンスの速さは適切か?
- 3.2. 顧問契約の内容と自社のニーズが合っているか?
- 3.2.1. 記帳や決算申告などの作業を代行してもらうだけで満足できるのか?
- 3.2.2. 資金繰りや節税提案をしてほしいのか?
- 3.2.3. 会社の将来を見据えた財務アドバイスを求めているのか?
- 3.3. 企業の成長フェーズに適した税理士か?
- 4. もう不満を抱きたくない!自社に合った税理士の選び方のコツ
- 4.1. 一般的な税理士の選び方では選ばない
- 4.1.1. 【ポイント1】知人の紹介は必ずしも良いとは限らない
- 4.1.2. 【ポイント2】税理士紹介サービスが必ずいいマッチングになるとは限らない
- 4.1.3. 【ポイント3】大手だから安心でいいサービスな訳ではない
- 4.2. 事務所名ではなく、実際の担当者に合って見極める
- 4.3. 税理士への不満から変更を検討する場合には必ずセカンドオピニオンを活用する
- 4.3.1. STEP1:今の税理士に具体的な改善要望を出す
- 4.3.2. STEP2:並行して複数の税理士に対応してもらう
- 4.3.3. STEP3:現状の担当税理士を変えるか、契約そのものを見直すか検討する
- 5. 税理士に不満を感じたら、まずはセカンドオピニオンがおすすめ!
よくある税理士への不満
税理士に対する不満は、さまざまな形で現れます。
業務の進め方や対応の仕方に不満を感じることもあれば、料金とサービスのバランスに納得がいかないこともあるでしょう。
税理士に対するよくある不満は次の通りです。
- コミュニケーションがスムーズにとれない
- 経営のアドバイスや提案がない
- 何をしてくれているのかわからない
- 税理士がITやデジタルに対応できない
- 担当者が頻繁に変わる
- ミスが多い
以下からは、こうした税理士への不満についてランク順に詳しく見ていきましょう。
コミュニケーションがスムーズにとれない
税理士に対する不満のなかで最も多いのが、「コミュニケーションが不足している」というものです。
税理士に相談しても返信が遅かったり、税務のことをわかりやすく説明してくれなかったりすると、経営者としては不安になります。
たとえば、「決算前に税金の金額を知りたかったのに、ギリギリまで連絡がなかった」「質問をしたのに、2週間経っても返事が来ない」といったケースがあります。
こうした状況が続くと、経営判断に支障が出るだけでなく、「この税理士で本当に大丈夫なのか?」という疑念が生まれてしまうものです。
税理士の返信が遅れることで、数百万単位の損失につながる可能性があります。
たとえば、新しい設備を導入するために即時償却(購入した年に一括で経費計上できる税制)を活用しようとしたものの、税理士からの返答が遅れたために決算日を過ぎてしまい、結果的に適用できなかった場合、本来受けられた節税効果がゼロになり、法人税の負担が大幅に増える可能性があります。
また、税務調査対策の相談をしていたものの、税理士の対応が遅れたことで税務署への説明が十分にできず、結果として追徴課税を求められるケースも考えられるのです。
一方で、レスポンスの早い税理士と契約していると、経営の意思決定をスムーズに進められる可能性があります。
たとえば、決算の1ヶ月前に「今年の税負担を抑えるにはどうするか?」というシミュレーションを行い、設備投資を前倒しすることで利益圧縮につなげ、法人税を削減できる場合があります。
さらに、補助金の申請についても迅速に相談できれば、キャッシュフローの改善が期待できるのではないでしょうか。
税理士への不満を感じた場合は、まず税理士に対して「もう少し頻繁に情報共有してほしい」「こちらからの質問に早く答えてほしい」といった具体的な改善要望を伝えてみることが大切です。
それでも改善が見られない場合は、解約も視野に入れ、他の税理士と比較することを検討しましょう。
税理士変更でよくあるトラブルや対策・安全な乗り換え方
税理士を変更したいと考えたとき、多くの方が「スムーズに進められるだろう」と思いがちですが、実際にはさまざまなトラブルが発生することがあります。 契約解除をめぐる問題や、必要な書類の返却が滞るケース、さらには新しい税理士と […]
経営のアドバイスや提案がない
税理士は単に決算や税金の計算をするだけでなく、経営者のパートナーとして、会社の成長をサポートしてくれる存在であるべきです。
しかし、現実には「決算書を作るだけで、経営のアドバイスは一切ない」「節税の提案をしてくれない」といった税理士への不満を抱える経営者が少なくありません。
税理士が経営のアドバイスをしないと、重大な機会損失につながる可能性があります。
パートナー型の税理士と、そうではない作業代行型税理士の違いをあらわすと、以下の表のようになります。
| 項目 |
パートナー型税理士 |
作業代行型税理士 |
|---|---|---|
| 経営アドバイス |
積極的・具体的 | ほぼ無い or 受け身 |
| 節税提案 |
利益シミュレーションまで踏み込む | 言われてからしか動かない |
| 金融機関との交渉・サポート |
決算書の見せ方までアドバイス | 「銀行に相談してみてください」 |
| 結果的なコスト意識 |
将来リスク含めて最適化 | 顧問料以上の効果が不透明 |
たとえば、売上が順調に伸びている会社があったとして、本来であれば「このままいくと税金の負担が増えるので、設備投資を考えたほうがいい」などの助言をすべき場面でも、何のアドバイスもないことがあります。
この結果、本来活用できたはずの設備投資による減価償却の調整を見落とし、法人税負担が過大になる可能性があるのです。
たとえば、決算前に「今年中に新しい機械を導入すれば、減価償却費を増やし税負担を抑えられる」というアドバイスがあれば、ベストなタイミングで投資ができたかもしれません。
しかし、税理士から何も情報がなかったために、機械の導入を翌期に先送りしてしまい、その結果、税負担が数百万円単位で増加することも考えられます。
また、役員報酬の最適化が行われなかったために、法人税が過大になるケースもあります。
本来、利益が大きく出た年には、役員報酬を増額することで法人税を抑え、個人所得税とのバランスをとることが可能です。
しかし、税理士が何の提案もせず、毎年同じ役員報酬のままにしてしまった場合、会社としては本来抑えられたはずの法人税を余計に支払うことになり、キャッシュフローが悪化する可能性があります。
一方で、経営に関与する税理士と契約していれば、会社の成長を加速させることができる可能性があります。
たとえば、事業拡大を考えている企業が「銀行融資を受けたい」と相談した場合、経験豊富な税理士であれば「直近の決算書をこう改善すれば、金融機関の評価が上がり、金利優遇が受けられる可能性がある」といった具体的なアドバイスができるかもしれません。
また、補助金や助成金の申請に関しても、税理士が積極的に情報提供をしていれば「この制度を活用すれば、新規採用にかかる人件費の一部が助成される可能性がある」など、経営者が知らなかった有利な制度を活用できる可能性が高くなります。
このような税理士と契約していれば、節税だけでなく、資金調達や利益の最大化にもつながるため、会社の成長スピードが大きく変わることが期待できます。
もし税理士に対して「経営のアドバイスが欲しい」と考えているのなら、契約内容を見直し、より積極的にサポートしてくれる税理士を探すことも選択肢の一つです。
何をしてくれているのかわからない
「毎月顧問料を払っているのに、何をしてくれているのかわからない」「請求書を見ても、どんな業務にいくらかかっているのか不明瞭」といった税理士への不満を抱えている方も多くいます。
税理士の業務内容がはっきりしていないまま放置すると、無駄なコストを支払い続ける可能性があります。
たとえば、毎月3万円の顧問料を支払っている会社が、「結局、記帳代行と決算申告しかしてもらっていない」と感じる場合、本当にその金額を支払う価値があるのか疑問を抱くのは当然です。
この状態を放置すると、知らず知らずのうちに年間で36万円、5年で180万円以上を不要な支出として失っている可能性があります。
そのお金で、社員の給料を上げたりインテリアを一新するなど、社内のQOLを向上させることもできたはずです。
しかも、その税理士が最低限の業務しかしていない場合、決算対策や資金繰りの改善など、本来受けられるはずのサポートを見逃すことにもつながってしまうでしょう。
たとえば、顧問契約の内容によっては、年末調整や税務調査対応が別料金となることがあります。
契約時に業務範囲をきちんと確認していなかったため、「顧問契約内だから大丈夫」と思い込んでしまうケースもあります。
年末調整が顧問契約に含まれていない場合、会社が自ら処理する必要があるのです。
しかし、それに気づかず税理士に任せたつもりでいると、年末調整がきちんと行われず、従業員の所得税が過剰に控除されたり、還付金が受け取れなかったりする可能性があります。
その結果、年が明けてから従業員から「還付されるはずの税金が戻ってこない」と不満を持たれたり、未処理のまま放置されることで税務署からの指摘を受ける可能性が生まれてしまうのです。
また、税務調査対応が顧問契約に含まれていない場合、調査時に税理士の立ち会いや書類作成を依頼すると、追加で数十万円の費用がかかることがあります。
さらに、税務調査の結果、経費の計上ミスや売上の申告漏れを指摘されると、追徴課税として100万円以上の支払いが発生する可能性もあります。
こうした費用は予算に計上されていないことが多く、急な支出が資金繰りを圧迫することにつながるかもしれません。
一方で、料金とサービス内容をはっきりさせておけば、無駄なコストを削減し、より効果的なサポートを受けられる可能性があります。
たとえば、「顧問料に含まれる業務」「追加料金が発生する業務」を事前に明らかにすることで、不要なサービスを削減し、必要な業務だけにコストをかけることが可能になります。
税理士と料金の見直しを行った結果、「本来不要だった業務が含まれていたことに気づき、毎月の顧問料を3万円から1.5万円に削減できた」というケースも考えられるでしょう。
年間で18万円の節約となり、その分を新規事業の資金や従業員の福利厚生に回せる可能性があります。
こうした場合、税理士に対して「具体的にどんな業務をしているのか」「顧問料の内訳を説明してほしい」と依頼することが重要です。
それでも納得のいく説明が得られなければ、ほかの税理士と比較してみることで、自社にとって適正な料金かどうかを判断することができます。
税理士がITやデジタルに対応できない
最近では、クラウド会計ソフトを活用する企業が増えていますが、税理士のなかには「昔ながらのアナログなやり方」にこだわり、最新のツールを使いこなせない方もいます。
税理士がITに対応できないと、業務の効率が大幅に低下し、無駄な手間やコストが発生する可能性があります。
たとえば、「請求書や領収書をPDFで送っても、紙で持ってこいと言われる」「クラウド会計ソフトの導入を相談したら、『そんなものは想定してない』と拒否された」といったケースが考えられるでしょう。
このような対応をされると、経理業務のデジタル化が進まず、書類の印刷・郵送・手入力などの手間が増えてしまいます。
たとえば、毎月50枚の領収書を印刷して郵送し、それを税理士が手作業で入力する場合、送付のための郵送料と印刷コストが年間で数万円かかるだけでなく、データ入力の遅れによって経営判断が後手に回ることも考えられます。
また、クラウド会計を導入すれば、リアルタイムで経営状況を把握しやすくなるものです。
しかし、クラウドアプリやオンラインツールなどの利用を拒否する税理士と契約していると、売上や経費の分析が遅れ、資金繰りの悪化を見逃す可能性があります。
たとえば、クラウド上ではほぼ自動化され、即時に確認できるはずの未収金情報を把握できないまま、資金繰りが厳しくなり、結果として支払いが遅延し、取引先の信用を失うリスクも考えられます。
一方で、ITに強い税理士と契約すれば、経理業務の効率化が進み、経営判断のスピードも向上しやすくなるでしょう。
たとえば、クラウド会計ソフトを導入することで、売上や利益のデータをリアルタイムで確認できるため、決算前に利益を見ながら節税対策を打つことが可能になります。
つまり、「決算ギリギリになって急いで対策を考え、結果的に十分な節税ができなかった」といった事態も防げるかもしれません。
また、電子帳簿保存法の改正により、今後はデジタルデータでの書類管理が求められる場面が増えるため、ITに対応できない税理士と契約を続けていると、法律の改正に適応できず、後々大きなトラブルにつながる可能性もあります。
もし税理士が時代に合った対応をしてくれない場合は、より柔軟に対応できる税理士への変更を考えてもよいでしょう。
担当者が頻繁に変わる
大手の税理士事務所では、担当者が定期的に変わることがよくあります。
しかし、担当者が頻繁に変わると、「せっかく業務の流れを理解してもらったのに、また一から説明しなければならない」という状況になり、経営者としてはストレスを感じることになります。
担当者の変更が頻繁に起こると、経理や税務の対応が遅れ、結果として経営に悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。
たとえば、「長年付き合ってきた税理士が異動になり、新しい担当者が全く会社のことを理解していない」といった状況になった場合、その都度こちらが引き継ぎをしてあげねばならず、業務の効率が落ちてしまうことになります。
さらに、前任者からの引き継ぎが不十分だった場合、過去の経理処理の意図や特有の会計処理が共有されておらず、税務申告のミスにつながる可能性もあります。
たとえば、前任者が特定の節税対策を講じていたにもかかわらず、新しい担当者がその方針を知らずに対応を変更した結果、本来適用できたはずの減税措置が使えなくなり、数十万円単位の税負担が増えることも考えられるのです。
また、融資の際には、金融機関が過去の財務状況を細かくチェックするため、税理士が会社の経営状況を正確に把握していることが重要です。
しかし、担当者が頻繁に変わると、過去の経営方針や資金繰りの状況を十分に理解していないまま対応せざるを得なくなり、結果として融資審査で不利になる可能性があります。
「前の税理士なら銀行の審査資料をすぐに準備できたのに、新しい担当者は何もわかっておらず、融資審査に遅れが出た」という状況になってしまっては、取り返しがつきません。
一方で、担当者が固定されている税理士事務所と契約すれば、こうした手間やリスクを最小限に抑えられる可能性があります。
たとえば、担当者が長く同じ会社を見ている場合、経営者の考え方や業務の流れを深く理解しているため、財務状況の変化に応じた最適な節税対策や資金調達の提案を迅速に行いやすくなります。
担当税理士が頻繁に変わるといった問題を防ぐためには、契約を結ぶ際に「担当者が変わる可能性があるのか」「その場合の引き継ぎはどのように行われるのか」といった点を確認しておくことが重要です。
それでも不安がある場合は、担当者が固定されている税理士事務所を探すのも一つの方法です。
ミスが多い
ミスが多いというのもよくある不満の1つです。
税理士のミスは経営判断などに大きく関わってくるので「ミスの多さ」は見過ごすことができません。
数字をベースに大きな経営判断を下す場合などにミスがあると、資金繰りの悪化などにつながってきてしまいます。
ミスがあまりに多い場合には、改善告知や変更など迅速な対処が必要です。
ミスが多い税理士はどう対処すべき?変更してのリスク回避も検討しよう!
「うちの税理士、よくミスをするけど、これって普通なのか?」と思ったことはありませんか? 経理や税務に関するミスは、企業経営に大きな影響を与える可能性があります。 決算書の誤り、税務申告の不備、税務調査時の指摘事項など、税 […]
税理士への不満は、企業と税理士のミスマッチによって起こる
税理士への不満は、単なる「相性の問題」ではなく、以下のように企業側の期待と税理士の業務スタンスが合っていないことが原因で発生します。
- 担当者(担当税理士)とのミスマッチ
- 企業が期待することと税理士のスタンスのミスマッチ
- 企業の成長フェーズによる税理士に求められる役割の変化
企業の成長フェーズによって求める税理士の役割も変わるため、現状の税理士が本当にベストなのかを定期的に見直すことが重要です。
以下からは、ミスマッチの種類それぞれについて詳しく見ていきましょう。
担当者(担当税理士)とのミスマッチ
税理士事務所を選ぶ際、多くの企業が「事務所の評判」や「知人の紹介」に頼ることが多いですが、実際に業務を担当するのは「担当税理士」です。
つまり、事務所全体の実力や、紹介してくれた方の人柄なんかよりも、実際に担当してくれる税理士の知識や対応力が重要になります。
事務所全体の評価が良くても、担当税理士自身の能力や相性が自社の業務に合わなければ、期待したサポートを受けられない可能性があるのです。
たとえば、大手の税理士法人に依頼した場合でも、担当税理士が新人で経験不足だと、経営に役立つアドバイスを受けられないことがあります。
企業の資金繰りに関する相談をしても、「とりあえず銀行に行って相談してみてください」としか言われず、具体的な資料作成や交渉のサポートを受けられない、ということも起こり得るでしょう。
これでは、税理士に頼るメリットがなく、むしろ顧問料を払うことすら疑問に感じてしまいます。
一方、小規模な税理士事務所でも、経験豊富な税理士が担当してくれれば、密なサポートが受けられることがあります。
たとえば、融資を受ける際に「銀行が重視する決算書の見せ方」をアドバイスしてもらえれば、審査がスムーズに進み、希望額の融資を受けられるかもしれません。
もし「担当者が合わない」と感じたら、そのまま放置せず、早めに対策を取ることが重要です。
担当者が自社の業界や経営課題を理解していないと、本来受けられたはずの節税対策や経営サポートの機会を逃す可能性があります。
たとえば、あなたと同じ業界に精通した税理士であれば、業界特有の経費計上の方法や、活用できる補助金・助成金について的確なアドバイスができるはずです。
しかし、担当者がその知識を持っていなければ、そうした情報が得られず、結果として他社と比べて不利な経営を強いられるかもしれません。
もし「担当者が合わない」と感じたら、事務所内で担当を変えてもらえないか相談するしかないでしょう。
それでも改善しない場合は、税理士事務所ごと見直すことを検討しましょう。
企業が期待することと税理士のスタンスのミスマッチ
企業側が「経営のアドバイスを求めている」のに対し、税理士が「記帳代行や決算処理だけを重視している」といったケースでは、明らかにズレがあるため、不満が出やすくなります。
このズレを放置すると、企業は本来得られたはずのアドバイスを受けられず、結果として経営判断を誤る可能性があります。
たとえば、会社が資金繰りの改善を目的に税理士に相談したのに、「それは銀行に聞いてください」と言われてしまう場合、企業としては「経営の相談に乗ってくれない」と感じるでしょう。
しかし、銀行に相談する場合、税理士の視点で事前にキャッシュフローを整理し、きちんと融資のシミュレーションをしておくことで、有利な条件で融資を受けられる可能性があります。
シミュレーションをしないまま銀行に行けば、融資審査の過程で不利な条件を提示され、結果として資金繰りがさらに悪化することも考えられます。
また、税理士のなかには「財務アドバイスは業務範囲外」と考えている方もいるため、そもそも企業の期待と税理士のスタンスが合っていないことが問題なのです。
このミスマッチを防ぐためには、契約前に「どこまで相談できるのか」「経営のアドバイスもしてもらえるのか」をはっきりと確かめておくことが大切です。
たとえば、「融資サポートもお願いできますか?」「資金繰りや節税の相談にはどこまで対応してくれますか?」といった具体的な質問をしておけば、税理士の対応範囲をはっきりさせられ、後々のズレを防ぐことができるでしょう。
企業の成長フェーズによる税理士に求められる役割の変化
企業の成長フェーズによって、求める税理士の役割は変わります。
創業期の企業は、補助金や融資のサポートが得意な税理士が役に立ちますが、成長フェーズに入ると、節税対策や財務コンサルティングが重要になります。
また、事業規模が拡大すると、税務調査やM&A(企業買収・合併)に強い税理士が必要になることもあるでしょう。
もし企業の成長に合わせて税理士を見直さないと、経営に深刻な影響が出る可能性があります。
たとえば、創業期向けの税理士をそのまま使い続けた場合、成長フェーズで必要な「利益圧縮のためのベストな節税対策」や「金融機関からの評価を高める決算書の作り方」を提案してもらえず、本来なら削減できたはずの税負担が増えることがあります。
結果として、利益が圧迫され、事業拡大に必要な資金が不足するかもしれません。
また、会社の規模が大きくなれば、税務調査が入る可能性も高まります。
しかし、創業期の記帳や申告だけを担当していた税理士では、税務調査対応の経験が乏しく、不要な追徴課税を招いたり、税務署との交渉を不利に進められたりする可能性があります。
たとえば、売上が急増した企業が過去の経理処理の不備を指摘され、数百万円の追徴課税を受けるケースも考えられるため、税務リスクへの対応は無視できません。
一方で、ちゃんとしたタイミングで税理士を見直すことができれば、企業の成長を後押しするような提案を受けられる可能性があります。
たとえば、成長フェーズの企業であれば、「研究開発費の税額控除」「事業承継税制の活用」「グループ法人化による税負担の最適化」など、より高度な税務戦略を提案してもらえるかもしれません。
創業時に税理士を選んだまま、そのまま10年近く契約を続けている場合、現在の経営課題に対応できない税理士と契約している状態である可能性があります。
経営環境の変化に応じて、定期的に税理士を見直すことが、利益を最大化し、経営リスクを減らすカギとなります。
「今の税理士で大丈夫?」不満を感じたらチェックすべき3つのポイント
税理士に不満を感じたら、すぐに変更を考えるのではなく、まずは現状を見直し、問題点を整理することが大切です。
特に、以下の3つのポイントをチェックすると、今の税理士が本当に自社に合っているのかが見えてきます。
- 担当者のレスポンスの速さは適切か?
- 顧問契約の内容と自社のニーズが合っているか?
- 企業の成長フェーズに適した税理士か?
以下からは、こうしたポイントをそれぞれ詳しく見ていきましょう。
担当者のレスポンスの速さは適切か?
税理士に質問をしたとき、どれくらいのスピードで回答が返ってくるかは重要なポイントです。
税理士の対応が遅いと、経営判断が遅れ、資金繰りや税務対応に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
たとえば、資金繰りに関する重要な相談をしたのに、「忙しいので後日回答します」と言われてしまい、結局1週間以上待たされたとします。
その間に銀行の融資申し込みの期限が迫り、必要な資料が揃わなかったら、審査が通らず、結果として運転資金が不足し、取引先への支払いが遅延する事態に陥ることもあるでしょう。
また、助成金や補助金の申請では、税理士の確認が必要なケースも多く、税理士のレスポンスが遅れたせいで申請期限を逃し、本来受け取れたはずの数百万円の補助金を失うことも考えられます。
こうした事態が続けば、資金繰りに影響が出るだけでなく、経営者自身の精神的な負担も増える可能性があります。
一方で、レスポンスの速い税理士と契約していれば、急な資金繰りの相談にもすぐ対応してもらえたり、税務処理の遅れによる余計な負担を避けられたりする可能性があります。
たとえば、決算直前に大きな利益が出そうなとき、すぐに対応してくれる税理士なら、「このままでは法人税が多くなるので、設備投資を検討するとよい」といった正しいアドバイスを受けられるかもしれません。
もし対応が遅い場合は、契約内容を見直すか、別の税理士との比較を検討しましょう。
顧問契約の内容と自社のニーズが合っているか?
顧問契約を結ぶ際に、「どこまで業務をお願いするか」をはっきりさせていないと、後々「思っていたサービスと違う」という不満が生じることがあります。
契約時の内容確認を怠ると、必要なサポートが受けられず、経営に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
たとえば、次のような「あなたが税理士に望むこと」について考えてみてください。
- 記帳や決算申告などの作業を代行してもらうだけで満足できるのか?
- 資金繰りや節税提案をしてほしいのか?
- 会社の将来を見据えた財務アドバイスを求めているのか?
それぞれ、詳しく見てみましょう。
記帳や決算申告などの作業を代行してもらうだけで満足できるのか?
記帳代行や決算書の作成などの業務を任せるだけなら、基本的な会計処理を行う税理士でも問題はありません。
しかし、こうした作業は比較的単純な業務のため、顧問料を支払う価値があるかどうかを見極める必要があります。
たとえば、会計ソフトを活用すれば自社で記帳ができるにもかかわらず、顧問料を支払い続けている場合、年間で数十万円のコストを無駄にしている可能性があります。
一方、会社の成長に伴い、税務処理が複雑化しているのに、単純な記帳代行しかしてくれない税理士では、本来受けられるはずの節税対策や補助金情報を逃していることもありえます。
資金繰りや節税提案をしてほしいのか?
経営上必要な資金繰りのアドバイスなどを求める場合、税理士の知識や経験が問われます。
単なる会計処理だけでなく、経営者の相談役として積極的に提案をしてくれる税理士を選ぶことが重要です。
もし「こちらから聞かないと何も提案してくれない」「節税のアドバイスがない」と感じる場合は、税理士を見直すタイミングかもしれません。
たとえば、売上が上がったにもかかわらず、その状況に応じた節税策を提案してもらえず、結果として数百万円といった法人税を支払ってしまうなども考えられます。
きちんとした税理士であれば、事前に設備投資や役員報酬の調整などの方法を提示し、納税額を最適化するサポートを受けられる可能性があります。
会社の将来を見据えた財務アドバイスを求めているのか?
会社の成長を支えるための長期的な財務戦略や事業計画のサポートを求める場合、税理士にも高い経営知識が必要になります。
きちんとした税理士と契約すれば、財務戦略がはっきりし、成長を加速できる可能性があります。
たとえば、「今後の売上拡大に向けた投資計画を一緒に考えてくれる」「資金調達やM&A(企業の合併・買収)にも詳しい」といった税理士なら、経営のパートナーとしての役割を果たしてくれるでしょう。
一方で、長期的な経営戦略を相談できない税理士と契約していると、事業拡大のチャンスを逃す可能性があります。
たとえば、資金調達の知識が乏しい税理士と契約していたことで、銀行融資の審査を通すための財務データをきちんと準備できず、融資を受けられないというケースが考えられます。
結果として、事業の拡大が半年以上遅れ、その間に競合他社が先に市場を押さえてしまい、成長機会を逃してもおかしくはありません。
また、「将来的に新規事業を立ち上げよう」と考えたとき、きちんとした税理士ならば、節税しながら設備投資を進める方法や、金融機関との交渉に有利な財務データの準備を提案してくれるはずです。
しかし、こうしたサポートを受けられない場合、資金繰りのミスで新規事業の立ち上げが遅れたり、運転資金が不足して事業拡大を断念せざるを得なくなることも考えられます。
きちんとした税理士を選ぶことで、資金調達の成功率を高め、利益を最大化しながら事業成長を加速させることが期待できます。
「税理士は決算書を作るだけ」と考えるのではなく、経営の未来を見据えた財務戦略を支援できる専門家として選んでみてはいかがでしょうか。
そうした方が、長期的な成功につながる可能性があります。
企業の成長フェーズに適した税理士か?
企業が成長していくにつれて、必要な税理士のスキルも変わっていきます。
創業期の税理士がそのまま成長フェーズの税理士として適しているとは限りません。
もし成長に合わない税理士と契約を続けると、企業の発展を妨げる可能性があります。
たとえば、売上が1億円を超えた企業が、創業時に契約した税理士とそのまま契約を続けている場合、事業のスケールに見合ったアドバイスを受けられていない可能性があります。
もし、創業時に資金調達のサポートをしてくれた税理士に、成長後の法人税対策や内部統制に関する知識が不足していたらどうなるでしょうか。
おそらく、きちんとした節税策が立てられず、結果的に本来払わなくてもよかった数百万円単位の税金を支払うことになるでしょう。
また、年商が上がると税務調査の対象になりやすくなりますが、成長期に必要なリスク対策をしてもらえず、税務調査で指摘を受け、多額の追徴課税が発生することも考えられます。
一方で、成長フェーズに適した税理士を選んだのであれば、経営の視点から見た節税策や財務戦略のサポートを受けることができ、結果として年間数百万円単位の利益を確保できる可能性があります。
このように、企業の規模やフェーズに合った税理士を選ぶことは、経営の安定と成長に直結する重要なポイントです。
もう不満を抱きたくない!自社に合った税理士の選び方のコツ
税理士に対する不満が生じる原因の多くは、そもそも「最初の選び方」が間違っていたことにあります。
自社にあった税理士の選び方は、以下の通りです。
- 一般的な税理士の選び方では選ばない
- 事務所名ではなく、実際の担当者に合って見極める
- 税理士への不満から変更を検討する場合には必ずセカンドオピニオンを活用する
以下からは、税理士選びの具体的なコツについて詳しく見ていきましょう。
一般的な税理士の選び方では選ばない
ネットなどでよく紹介されているような税理士の選び方を鵜呑みにしてしまうと失敗しやすいので注意しましょう。
特に次のような点はよく認識した上で一般的な税理士の選び方では選ばないことを意識する必要があります。
- 【ポイント1】知人の紹介は必ずしも良いとは限らない
- 【ポイント2】税理士紹介サービスが必ずいいマッチングになるとは限らない
- 【ポイント3】大手だから安心でいいサービスな訳ではない
それぞれ、詳しく解説します。
【ポイント1】知人の紹介は必ずしも良いとは限らない
「知人や銀行から紹介されたから安心」と思い込み、そのまま契約してしまうケースは多いですが、必ずしも正しい選び方ではありません。
知人の会社に合っている税理士が、自社にも合うとは限らないからです。
たとえば、知人が経営するのは小規模の飲食店で、自社は製造業だったとします。
業種によって求められる税理士の知識や経験は異なるため、「知人にとっては良い税理士」でも、「自社には適していない税理士」である可能性があります。
もし、製造業の会社が飲食店向けの税理士を紹介されて契約した結果、製造業特有の減価償却の扱いや設備投資に関する税制優遇の知識が不足しており、必要な申請ができずに何百万円もの税負担が増えてしまうといった事態になるかもしれません。
さらに、知人の紹介ということで契約を結んでしまうと、途中で変更しづらくなるというデメリットもあります。
「せっかく紹介してもらったのに失礼ではないか」「知人との関係が悪くなるのではないか」といった心理的な負担を感じ、契約を見直したいと思っても言い出せないことがあるのです。
結果として、本来ならより経営に役立つ税理士に変更すべき場面でも、ズルズルと契約を続けてしまい、事業の成長を妨げる要因になる可能性があります。
こうしたリスクを避けるためにも、税理士を選ぶ時は実際に会って話し、自社のニーズに合った税理士かどうかをしっかり判断することが重要です。
【ポイント2】税理士紹介サービスが必ずいいマッチングになるとは限らない
税理士紹介サービスを利用すれば、手間をかけずに税理士を見つけることができます。
しかし、こうしたサービスでは、紹介される税理士が「本当に自社に合っているかどうか」を事前に十分に確認することが難しいという問題があります。
紹介サービスは「顧問契約が成立した際の手数料」を収益源にしているため、企業に最適な税理士を紹介しているとは限らず、紹介手数料を払える税理士だけが登録されている可能性があるのです。
紹介サービス経由で税理士を選ぶと、後になって「業種特有の税務処理に詳しくない税理士だったため、誤った申告をしてしまい、税務調査で指摘を受けた」というケースが起こり得ます。
この結果、修正申告と追徴課税が発生し、予定外の支出が数十万円単位で増えることになっては、税理士を雇った意味がありません。
また、紹介された税理士が各種仲介サイトなどに支払った手数料を取り戻そうと、最初から「フルパッケージの契約」を勧めてきたたりして、不要な業務まで抱え込む形になり、顧問料が割高になるというケースも考えられます。
本来であれば、企業の成長フェーズに応じて必要な業務を見極めて契約するべきですが、紹介サービス経由だと「最初に提示されたプランをそのまま受け入れてしまう」というケースが少なくありません。
こうしたリスクを避けるためには、紹介された税理士をそのまま選ぶのではなく、必ず面談を行い、対応力や相性をチェックすることが必要です。
実際に面談をした結果、最初に紹介された税理士ではなく、別の税理士の方が自社に合っていたと判断し、契約を変更した企業もあります。
事前の確認を怠ると、後になって「こんなはずではなかった」と後悔する可能性があるため、慎重に判断しましょう。
【ポイント3】大手だから安心でいいサービスな訳ではない
大手の税理士法人に依頼すれば安心だと考える方も多いですが、必ずしもそうとは限りません。
大手事務所は担当者が頻繁に変わることが多く、「せっかく信頼関係を築いたのに、1年後には別の担当者に代わっていた」ということもあります。
もし、大手税理士事務所の担当者が2年連続で交代した結果、会社の経理処理に一貫性がなくなり、過去の仕訳ミスが放置され、税務調査で数百万円の修正申告を求められるというケースも考えられます。
また、大手事務所では「法人向けのサービスを重視している」ということが多く、小規模な会社の経営相談にはあまり親身になってくれないケースもあるため注意しましょう。
特に、資金繰りや補助金申請の相談をした際に、定型的な回答しか得られず、自社の状況に即した具体的な提案を受けられないことがあるかもしれません。
その結果、きちんとしたタイミングで資金調達ができず、事業の成長が停滞する可能性もあります。
こうしたリスクを避けるためには、「大手だから安心」という考えにとらわれず、窓口担当者や営業担当者ではなく、実際に担当する税理士の対応をチェックすることが大切です。
事前に面談を行い、担当者がどの程度自社の状況を理解してくれるのか、どんなサポートが期待できるのかを確認することで、後から「こんなはずではなかった」と後悔するリスクを減らせるでしょう。
事務所名ではなく、実際の担当者に合って見極める
税理士を選ぶ際は、「事務所の規模」や「知名度」ではなく、「実際に担当する税理士がどんな人物か」を重視することが重要です。
税理士事務所ごとにサービスの質が異なるわけではなく、結局のところ「誰が担当するか」がもっとも影響を与えるからです。
たとえば、大手の税理士法人に依頼して安心していたものの、実際に担当になったのは経験の浅い新人税理士で、税務調査時にきちんとした対応ができず、結果的に本来なら避けられたはずの追徴課税が発生するというケースも考えられます。
また、税理士の対応力次第では、会社の経営判断にも影響を及ぼす可能性があります。
たとえば、資金繰りに関する緊急の相談をした際に、担当税理士のレスポンスが遅く、金融機関との交渉が間に合わず、融資のタイミングを逃してしまっては目も当てられません。
こうした問題を避けるためには、実際に契約を結ぶ前に、担当者と直接話し、以下のような点を確認しましょう。
- レスポンスの速さ(質問した際の対応の早さ)
- 経営の相談にどこまで乗ってくれるか
- 節税対策の提案を積極的にしてくれるか
- 会社の成長を見据えたアドバイスができるか
きちんとした担当者を選ぶことで、事業の拡大時に積極的な節税提案や資金調達のサポートを受けられる可能性が高まり、経営の安定化につながりやすくあります。
こうしたポイントを見極めることで、税理士選びの失敗を防ぎやすくなるでしょう。
税理士への不満から変更を検討する場合には必ずセカンドオピニオンを活用する
税理士に不満を感じたとき、「すぐに変更しよう」と考えるのは早計かもしれません。
まずは、現在の税理士が本当に自社に合っていないのかを客観的に判断することが重要です。
そのために有効なのが「セカンドオピニオン」です。
セカンドオピニオンとは、現在の税理士とは別の税理士に意見を聞くことを指します。
以下のようなメリットがあります。
- 現在の税理士の対応が合っているかどうかを客観的に判断できる
- 他の税理士と比較することで、自社に合った税理士を見つけやすくなる
- すぐに税理士を変えた場合のリスクを減らし、慎重に判断できる
いきなり税理士を変更すると、業務の引き継ぎがうまくいかずに混乱が生じることがあります。
しかし、次の手順で、うまくセカンドオピニオンを活用すれば、スムーズに比較検討し、自社にとって最適な税理士を見極めることが可能になります。
- STEP1:今の税理士に具体的な改善要望を出す
- STEP2:並行して複数の税理士に対応してもらう
- STEP3:現状の担当税理士を変えるか、契約そのものを見直すか検討する
以下からは、セカンドオピニオンを活用するための各手順を詳しく見ていきましょう。
STEP1:今の税理士に具体的な改善要望を出す
税理士に不満を感じたら、まずは現在の担当者に改善を求めることが大切です。
不満があるからといって、すぐに契約を解除するのではなく、まずは「何が問題なのか」をはっきりさせ、改善できるかどうかを確認しましょう。
たとえば、次のような改善要望を出してみましょう。
- 返信のスピードを上げてもらうよう依頼する
- 節税や資金繰りのアドバイスをもっと積極的にしてもらうようお願いする
- 料金とサービスの内容を明らかにしてもらう
もし、こうした要望を伝えても改善が見られない場合、その税理士は自社に合っていない可能性が高いです。
その際、改善要望を伝えた記録を残しておけば、後々「そんな話は聞いていない」と言われたり、契約解除時に万が一裁判沙汰になったり、不当な請求を受けたりしたときに、不利になりにくくなります。
その場合に初めて、他の税理士を探すことを検討しましょう。
STEP2:並行して複数の税理士に対応してもらう
現在の税理士と比較するために、セカンドオピニオンとして別の税理士に相談してみることが重要です。
ただし、税理士の意見を比較する方法には次の表のように2パターンがあります。
| 比較方法 |
内容 |
メリット |
|---|---|---|
| ①完全に同じ業務をセカンドオピニオンと現税理士の両方に依頼(理想形) | 同じ決算書のチェックや税務相談を、現在の税理士とセカンドオピニオンの両方に依頼し、どちらがより的確なアドバイスをくれるかを比較する | 税理士ごとのスキルや対応力の違いがはっきりする、より適した税理士を判断しやすい |
| ②セカンドオピニオンに限定的な業務を依頼し、スポットで比較(現実的) | 「税務調査対策」「節税の相談」など、特定のテーマに絞ってセカンドオピニオンの意見を聞く |
低コストで他の税理士の意見を取り入れられ、必要な部分だけ比較できる |
どちらの方法を選ぶかは会社の状況によります。
いずれにしても一度は他の税理士の意見を聞いてみることで、現在の税理士との相性や、見えていなかった課題をよりはっきりさせることができます。
STEP3:現状の担当税理士を変えるか、契約そのものを見直すか検討する
セカンドオピニオンの結果、「やはり今の税理士では不十分だ」と感じた場合は、変更を検討するタイミングです。
ただし、必ずしも「すぐに税理士を変える」ことが最善とは限りません。
場合によっては、税理士の変更ではなく「契約内容の見直し」で解決することもあります。
たとえば、「今の税理士には決算業務だけを依頼し、経営アドバイスは別の税理士に依頼する」といった形で、役割を分けることも可能です。
こうした選択肢を検討したうえで、「やはり税理士を変更したほうがよい」と判断した場合は、次は解約や、新規契約のステップへと進みましょう。
税理士に不満を感じたら、まずはセカンドオピニオンがおすすめ!
今回は、税理士に対する不満の原因や、不満を解決するための具体的な方法について解説してきました。
不満を抱えたまま顧問税理士を放置すると、経営に悪影響を及ぼすことになりかねません。
しかし、いきなり税理士を変更するのではなく、まずは 「本当に税理士を変えるべきか?」 を冷静に判断することが大切です。
税理士に不満を感じたら、まずは「セカンドオピニオン」を試してみましょう。
別の税理士に意見を求めることで、現在の税理士の対応を客観的に判断でき、新しい視点を得られる可能性があります。
たとえば、資金繰りや節税対策について現税理士が「特に対策は不要」と言っても、他の税理士なら「今のうちに設備投資を検討すべき」と具体的なアドバイスをくれることがあります。
セカンドオピニオンの結果、税理士変更を決断した場合は、契約書の確認や引き継ぎを円滑に進める準備が必要です。
税理士は単なる税務処理の担当者ではなく「経営のパートナー」となるべき存在です。
慎重に選び、最適な税理士とともに安心して経営に集中できる環境を整えましょう。