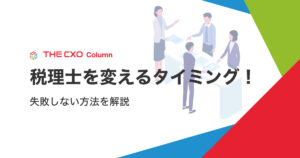自社に最適な「いい税理士」の探し方とは?手順や見極める基準を解説
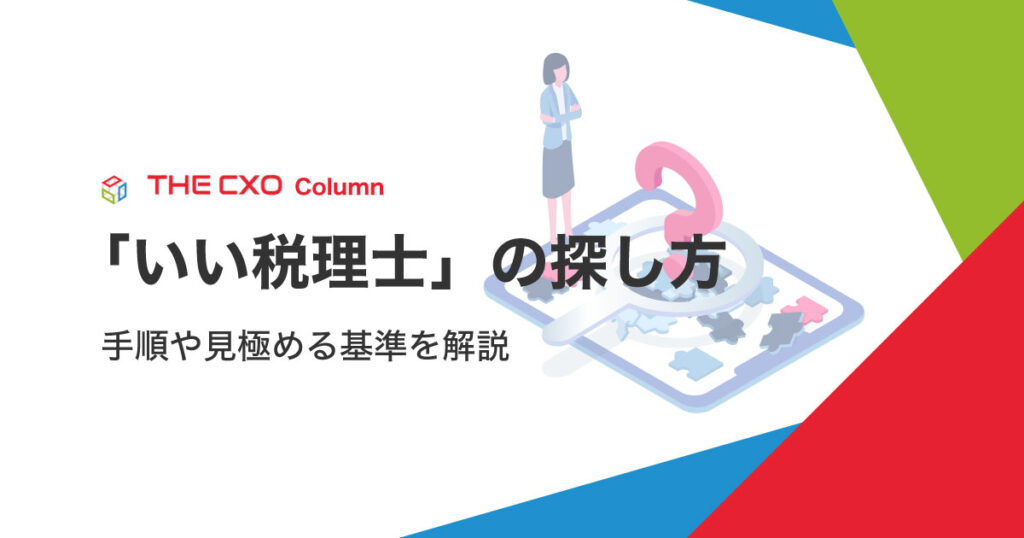
税理士を探すとき、多くの方が「ネット検索で上位に出てきた事務所に依頼する」「知人に紹介された税理士をそのまま契約する」といった方法を選ぶのではないでしょうか。
しかし、こうした探し方では本当に自社に合う、いい税理士とは出会えない可能性が高くなります。
なぜなら、税理士選びにおいて重要なのは、「事務所の知名度」ではなく「実際に担当する税理士のスキル・対応力」だからです。
大手事務所だからといって、必ずしもあなたの会社に最適なサポートができるわけではありません。
この記事では、一般的におすすめとされている税理士の探し方と、その落とし穴について詳しく解説し、本当に「いい税理士」を見つけるための方法を紹介します。
株式会社カタリスタ 代表取締役
THE CXO 株式会社 代表取締役
飯島 彰仁(いいじま あきひと)
Iijima Akihito
経営計画コンサルタント、中小企業の社外CXO。大手会計事務所元代表取締役社長として、同社を年商22億円、従業員数447名の規模にまで成長させた実績を持つ。
これまで3,000社以上の中小企業に対し、財務やマーケティングを通じた経営向上に貢献。
その中で、中小企業の成長のためには、単なる税務処理を超え、経営に深く関与する税理士が必要不可欠であることを痛感。
その経験をもとに、税理士が真の価値を発揮する「社外CXOメソッド」を開発。累計300人以上の税理士に伝授し、「税務の枠を超え、中小企業のあらゆる相談に乗れるパートナー」を養成。
指導した税理士達からは、顧問先の売上向上、利益向上、V字回復や事業改善など成功報告が続々と寄せられている。

- 1. 一般的にいい税理士の探し方とされる方法は7つ!
- 1.1. インターネット検索
- 1.2. 税理士紹介サービス
- 1.2.1. 手数料ビジネスである
- 1.2.2. 事務所単位での紹介が多く、担当税理士の質は分からない
- 1.2.3. 面談時に「経営の視点」を重視していない
- 1.3. 税理士検索サイト・マッチングサービス
- 1.4. 知人・同業者からの紹介
- 1.5. 税理士会や商工会議所での紹介
- 1.6. 金融機関経由の税理士紹介
- 1.7. セミナー参加で税理士と直接会う
- 2. 一般的にいいと言われる税理士の探し方には落とし穴がある
- 2.1. ネット検索・紹介サービスには根拠がない
- 2.2. 知人や同業者の紹介は「相性の保証」がない
- 2.3. 商工会・金融機関の紹介は「無難な選択」にすぎない
- 3. 自社にとって本当にいい税理士の探し方の手順
- 3.1. まずは「自社の課題」を整理する(事業フェーズ別・最適な税理士選び)
- 3.1.1. 創業期(0〜3年目)に適した税理士:記帳代行・節税対策に強い税理士
- 3.1.2. 成長期(3〜10年目)に適した税理士:資金繰り・融資・補助金サポートができる税理士
- 3.1.3. 成熟期(10年以上)に適した税理士:事業承継・税務戦略に強い税理士
- 3.2. ② 自社に合った税理士事務所を探す
- 3.2.1. 「低価格型税理士」は決められた業務のみを行う
- 3.2.2. 「業種特化型税理士」なら自社の課題を相談できる
- 3.2.3. 「付加価値型税理士」は経営全体のサポートをしてくれる
- 3.3. ③ 事務所の実績・ブランドではなく「担当者ベース」で選ぶ
- 3.4. ④ セカンドオピニオンを活用し、複数事務所を比較する
- 3.4.1. 税理士を比較する際に見るべきポイント
- 3.4.1.1. 比較することで見えてくる「税理士の質」
- 4. 自社に最適ないい税理士かどうかを見極める5つの基準
- 4.1. 営業担当者ではなく、実際の税務担当者と初回相談できるか?
- 4.2. レスポンスの速さ・経営アドバイスの有無はどうか?
- 4.3. 料金体系に透明性はあるか?(安さだけで選ばない)
- 4.4. 不要な投資・保険商品をすすめてこないか?
- 4.5. 長期的に経営をサポートできるか?
- 5. 自社に最適なパートナー税理士を見つけたいならTHE CXOにご相談ください!
- 5.1.1. 事務所単位ではなく、「実際の担当者ベース」で税理士を紹介
- 5.1.2. セカンドオピニオンの活用を推奨
- 5.1.3. 経営フェーズごとに最適な税理士をマッチング
- 6. 従来の方法では不十分!自社にとって最適ないい税理士を見つけよう!
一般的にいい税理士の探し方とされる方法は7つ!
税理士を探す方法として、以下の5つが一般的に知られています。
- インターネット検索
- 税理士紹介サービス
- 税理士検索サイト・マッチングサービス
- 知人・同業者からの紹介
- 税理士会や商工会議所での紹介
- 金融機関経由の税理士紹介
- セミナー参加で税理士と直接会う
それぞれの方法にはメリットやデメリットがあります。
以下から詳しく見ていきましょう。
インターネット検索
インターネットを使って税理士を探す方法は、手軽で情報量も多いため、多くの経営者が利用しています。
しかし、検索結果の上位に出てくる税理士事務所が必ずしも優れたサービスを提供しているとは限りません。
たとえば、SEO対策(検索エンジン最適化)を強化し、広告費をかけて上位表示されている事務所は少なくありません。
つまり、「検索結果の上位=良い税理士」というわけではなく、広告費を多く投入している事務所が目立ちやすいのが現状です。
また、ホームページの情報だけでは、実際にあなたを担当する税理士が誰で、どのような人物なのか、どのようなサービスをしてくれるのかが分かりにくいという問題もあります。
このため、単純に検索結果の上位から選ぶのではなく、慎重に情報を精査し、複数の候補を比較することが重要です。
税理士紹介サービス
税理士紹介サービスは、依頼者の希望に合わせて地域を越えた広い範囲で税理士を紹介してくれる便利なサービスです。
しかし、仕組みを理解せずに利用すると、かえってミスマッチが生じることがあります。
税理士紹介サービスの大半は、紹介手数料を受け取るビジネスモデルになっています。
そのため、必ずしも自社にとって最適な税理士を紹介してくれるとは限りません。
たとえば、「実績のある税理士を紹介してほしい」と依頼しても、実際には手数料契約のある事務所の中からランダムに選ばれることがあります。
また、ミスマッチが起きてもフォローがないこともあります。
そうした場合に、数年単位縛りの契約を結ばされてしまうと、泣き寝入りすることになってしまうかもしれません。
紹介サービスを利用する場合は、「なぜその税理士を選んだのか」をしっかり確認し、複数の候補と比較することが重要です。
次のような点をしっかりと踏まえた上で利用する必要があります。
手数料ビジネスである
紹介サービスの多くは、「税理士側から紹介料をもらうビジネスモデル」です。
そのため、必ずしも依頼主(経営者)に最適な税理士が紹介されるとは限らないのです。
たとえば、「顧問料の30%を紹介手数料として支払う契約」の税理士が優先的に紹介されるというように、仲介役の利益が優先されることもあり、本当に実力があるかどうかは二の次になるケースもあります。
事務所単位での紹介が多く、担当税理士の質は分からない
多くの紹介サービスは、「○○税理士事務所」という単位で税理士を紹介します。
しかし、実際に対応するのは事務所の代表税理士ではなく、別の担当者になることがほとんどです。
特に大手事務所では、「実際の担当者が誰になるのか契約するまで分からない」というケースがあり、契約後に「思っていた対応と違った」と後悔することもあります。
面談時に「経営の視点」を重視していない
一般的な紹介サービスでは、「業種」「地域」「予算」などの基本情報をもとに税理士を紹介するだけです。
紹介での判断基準に、「その税理士が経営の視点を持っているか?」というものは含まれていません。
そのため、紹介された税理士が「単なる記帳代行型」だったり、「レスポンスが遅い」タイプだったりすると、結果的に経営者にとってデメリットとなります。
税理士検索サイト・マッチングサービス
最近では、税理士を検索できるマッチングサイトも増えてきています。
こうしたサービスは、希望の条件を入力することで、全国にある複数の税理士事務所を簡単に比較できるというような便利さがあります。
しかし、注意すべき点として、「掲載されている税理士事務所が本当に信頼できるかどうか分からない」という問題があります。
特に、登録されている税理士の選定基準がサイトごとに異なる点に注意しなければなりません。
クラウド会計ソフトを販売する企業が運営している場所であれば、同ソフトを利用している税理士しか紹介されない場合や、価格の安さを重視するサイトでは、税務調査対応や対面サポートが不十分な税理士が多いケースもあります。
そのため、登録されている税理士が信頼できるかどうかは、プロフィールや口コミ情報だけでなく、実際に自分で話して対応の速さやサービス内容を確認し、慎重に見極める必要があります。
知人・同業者からの紹介
知人や同業者の紹介で税理士を決めるケースも多いですが、この方法にはリスクがあります。
たとえば、「同業者が長年付き合っている税理士だから安心」と思って契約しても、その税理士が自社の経営フェーズや業態にも適しているとは限りません。
また、紹介で契約した税理士は、途中で変更しにくくなるという問題もあります。
仮に税理士の対応に不満を感じても、紹介者との関係、今後の付き合いを考えると解約しづらくなり、結果として不満を抱えたまま契約を続けることになりかねません。
税理士会や商工会議所での紹介
税理士会や商工会議所では、無料で税理士を紹介してもらえることがあります。
公的機関が関わるため、開業して長い方が紹介されるなど、実績面においては確かに一定のメリットがあるかもしれません。
しかし、実績があなたの業界と関係なければ、あまり意味はありません。
また、こうした機関が紹介する税理士は、特定の分野に強いわけではなく、結局は各会との地域的な結びつきにより「無難な税理士」が選ばれることが多いです。
特に、「相性」などは測りようがありません。
また、紹介される税理士がその団体との関係性を重視していることもあり、「組織内のしがらみ」が優先され、企業側の本当のニーズに沿った提案をしてくれるかどうかもわかりません。
他にもたとえば、最新の税制やクラウド会計に精通していない税理士が紹介されることもあり、成長フェーズにある企業にとっては物足りないと感じるケースがあります。
金融機関経由の税理士紹介
銀行や信用金庫が税理士を紹介してくれることもあります。
紹介できる理由は、金融機関と税理士事務所が提携関係にあることが多いためです。
ただし、金融機関が紹介する税理士は、「銀行にとって安心できる税理士」である傾向があるため、必ずしも経営者にとって最適とは限りません。
たとえば、銀行が「融資の審査が通りやすい税理士」として紹介してくれたとしても、あくまで銀行にとって都合がいい税理士かもしれないのです。
そうした税理士は、企業の成長戦略に必要な税理士とは異なるかもしれません。
たとえば、銀行が紹介してくれた税理士なら安心だと思って契約したものの、税務相談はほとんどなく、融資関連の書類作成ばかりで、経営のアドバイスを一切してくれないということが起こるかもしれません。
銀行が安心できる税理士と、あなたの会社にとって本当に役立つ税理士は違う、ぐらいの気持ちで身構えておくべきでしょう。
セミナー参加で税理士と直接会う
税理士が登壇するセミナーに参加し、直接話を聞くことで、その方の考え方やスキルを確認する方法もあります。
実際に対話できるため、相性を確認しやすいのがメリットです。
ただし、セミナーで話がうまい税理士が必ずしも実務に強いとは限りません。
中には、税理士としての仕事より、セミナーの開催をビジネスにしている方もいます。
話を聞いたときは「この税理士なら安心できそう」と思ったものの、実際に依頼すると「記帳や決算の処理が遅い」「税金対策の提案がない」といったトラブルが起こることがあります。
ひどい時は、「セミナーの開催で忙しい」というような回答をされてしまうこともありえます。
たとえば、セミナーで「税務調査に強い」と話していた税理士に依頼したものの、実際には税務調査の対応経験が少なく、いざ税務署が来たときに何のアドバイスも受けられなかった、ということが起こるかもしれません。
また、別の例として、「補助金や融資の知識が豊富」とアピールしていた税理士にお願いしたところ、書類の不備が多く、申請が通らなかったという失敗も考えられます。
他にも、そもそもセミナーの主催・後援団体が、これまで見てきたような商工会議所、金融機関、自治体、業界団体、税理士会、会計ソフト会社などであることもあります。
こうした場合、結局はタイアップ契約などを結んだだけの税理士が紹介されることになってしまうのです。
セミナーで税理士の考え方を知ることは大切ですが、話のうまさだけで判断せず、「実際の仕事ぶり」を確認することが重要です。
依頼前には、過去の実績や他の顧問先の評判をチェックし、本当に頼れる税理士かどうかを見極めましょう。
一般的にいいと言われる税理士の探し方には落とし穴がある
ここまで、税理士を探す一般的な方法を紹介しました。
実際にはこうした方法をとりいれても「いい税理士」に出会えないケースが多いのが現実です。
理由は、税理士の探し方に関する根本的な誤解にあります。
多くの経営者は、税理士の質を判断する際に「事務所の規模」「紹介された安心感」「検索結果の上位表示」といった表面的な要素を重視しすぎています。
しかし、税理士の本質は「実際に担当する人物のスキルと対応力」にあるため、一般的な探し方では本質を測ることはできず、あなたにぴったりの税理士とは出会えません。
一般的に良いとされた方法でも、以下のような落とし穴があるのです。
- ネット検索・紹介サービスには根拠がない
- 知人や同業者の紹介は「相性の保証」がない
- 商工会・金融機関の紹介は「無難な選択」にすぎない
ここからは、従来の税理士探しの方法がなぜ失敗しやすいのか、なぜ落とし穴なのかの理由を具体的に解説していきます。
ネット検索・紹介サービスには根拠がない
インターネット検索や税理士紹介サービスを利用すると、簡単に「良さそうな税理士」を見つけることができます。
しかし、この方法には大きな問題があります。
それは、検索結果や紹介サービスの評価が、税理士の実力を示す根拠にはならないという点です。
たとえば、ネット検索で上位に表示される税理士事務所は、多くの場合、SEO対策(検索エンジン最適化)を強化したりと、広告費にかけられる資金が豊かであるだけです。
実際の業務の質とは関係がありません。
ホームページの印象がよかったから契約したら、実際に来た税理士はサイト上に名前も顔もない者だったり、全然経営アドバイスをくれない、ということが起こり得ます。
また、税理士紹介サービスは、基本的に「税理士から紹介手数料を得るビジネス」です。
そのため、顧客の課題を正確に分析し、最適な税理士を紹介しているとは限りません。
場合によっては、単に登録している税理士の中から、手数料の条件が良い事務所を紹介するだけのケースも考えられます。
こうした部分に気づかず紹介サービスを使うと、ただの金払いだけはいい帳簿付け専門の税理士が来て役に立たず、結局また別の税理士を探すことになる、ということが起こります。
「検索結果で上位に出たから良い税理士」ではないし、「紹介されたから安心」という保証もないという点を理解しておくことが重要です。
知人や同業者の紹介は「相性の保証」がない
税理士を知人や同業者から紹介してもらう方法は、一見すると安心感があるように思えます。
しかし、ここにも大きな落とし穴があります。
それは、「A社にとって良い税理士」が「B社にとっても良い税理士」とは限らないという点です。
たとえば、同業の先輩経営者が「うちはこの税理士にずっとお願いしているから、あなたもこの人に頼んだら?」と勧めてくれたとします。
しかし、その税理士は、「長年付き合っていること」が紹介者により評価されているだけで、実際の対応力やスキルがあなたに合っているとは限りません。
こうしたミスは、以下のような点を意識していないために起こります。
| 考慮すべきポイント |
説明 |
|---|---|
| 成長フェーズの違い | 会社の成長段階によって、必要な税理士のスキルは違う 創業期の企業には、融資や助成金に詳しい税理士 成熟した企業には、節税や事業承継に強い税理士 紹介された税理士が各フェーズのニーズに対応できるという保証はない |
| 業種の違い | 業界特有の会計処理や税務知識が必要な場合、業界に詳しくない税理士を選んでしまうと、ベストなアドバイスが受けられない たとえば、IT企業と飲食業では、キャッシュフローの管理や経費の処理方法がまったく異なる |
また、紹介で契約すると、「紹介してもらった手前、合わなくても簡単に解約できない」という心理的なプレッシャーが生じます。
税理士は、安くても月額数万円、年間なら数十~数百万円と、それなりの費用を支払って雇うものです。
そんなにお金のかかる相手を、自分の一存で変更できないなど本末転倒です。
このように、「知人の紹介だから安心」という考え方には大きなリスクが伴います。
税理士選びにおいて最も重要なのは、「実際に担当する税理士が、自社の課題を理解し、的確なサポートを提供できるかどうか」なのです。
商工会・金融機関の紹介は「無難な選択」にすぎない
商工会や金融機関が紹介する税理士も、一見すると信頼できるように思えます。
しかし、結局は紹介に過ぎないため「最適な税理士を選ぶ」という意味では、必ずしも良い方法とは言えません。
なぜなら、こうした機関が紹介する税理士は「(各機関と)取引があるから紹介されている」だけ。
実際に、あなたの企業の成長にとって最適な人材かどうかは考慮されていないことが多いからです。
たとえば、金融機関が紹介する税理士は、銀行にとって「融資の審査をスムーズに進められる税理士」である可能性が高いです。
しかし、企業にとって本当に必要なのは、資金繰りのアドバイスができる税理士かもしれません。
こうした機関が「この先生はベテランだから!」と紹介してきて、まんまと契約してしまったら、確かに長年の税理士としての経験があるものの、最新のクラウド会計を知らなかったり、電子申告で不備を起こしてしまうことが起こりかねません。
つまり、「公的機関の紹介=信頼できる税理士」という思い込みは危険であり、紹介された税理士が自社に適しているかどうかを慎重に見極める必要があるのです。
自社にとって本当にいい税理士の探し方の手順
ここまで、従来の税理士の探し方に潜む落とし穴について説明しました。
では、どうすれば自社にとって最適な税理士を見つけられるのでしょうか。
単に「評判が良いから」「紹介されたから」という理由で税理士を選ぶのではなく、「自社の課題を解決できる税理士を見極めること」が重要です。
そのために必要な手順は、次の4つです。
- まずは「自社の課題」を整理する(事業フェーズ別・最適な税理士選び)
- 自社に合った税理士事務所を探す
- 事務所の実績・ブランドではなく「担当者ベース」で選ぶ
- セカンドオピニオンを活用し、複数事務所を比較する
以下から、それぞれ詳しく見ていきましょう。
まずは「自社の課題」を整理する(事業フェーズ別・最適な税理士選び)
税理士を探す前に、まずやるべきなのは「自社が税理士に何を求めるのか」を整理することです。
多くの経営者は、「税理士なら誰でも同じ」と考えがちですが、それは大きな間違いです。
税理士にはそれぞれ得意分野があり、しかも「どんな税理士が自社に適しているのか」は、事業フェーズによって異なります。
たとえば、創業期の企業と、10年以上続く成熟企業では、必要な税理士のスキルがまったく違います。
創業期には「融資サポートや記帳代行に強い税理士」が必要かもしれませんが、成熟期には「節税対策や事業承継に詳しい税理士」が求められます。
もし、会社の成長フェーズに合わない税理士を選んでしまうと、次のような問題が発生します。
| 会社の成長フェーズ・選んだ税理士 |
合わない税理士を選んだ場合の問題点 |
|---|---|
| 創業期の企業が「節税が得意な税理士」に依頼すると… | そもそも利益が少なく、節税よりも「資金調達や経理の整備」が重要なのに、的外れなサポートを受けることになる |
| 成長期の企業が「記帳代行専門の税理士」に依頼すると… | 資金繰りや融資サポートが不足し、経営戦略のアドバイスが受けられない |
| 成熟期の企業が「一般的な税理士」に依頼すると… | 事業承継や相続の専門知識が不足し、将来的に税金負担が増えるリスクがある |
このように、会社の成長フェーズごとに最適な税理士の条件は異なります。
そこで、以下からは事業フェーズごとに最適な税理士の特徴を見ていきましょう。
創業期(0〜3年目)に適した税理士:記帳代行・節税対策に強い税理士
創業期の企業は、資金が限られており、まずは「基本の税務処理を正しく行うこと」が最優先となります。
創業期(0〜3年目)に適した税理士の特徴は、以下の通りです。
- 記帳代行や決算申告をスムーズに行える
- 創業融資・助成金に詳しい
- 顧問料が比較的リーズナブルで、コストパフォーマンスが高い
たとえば、創業期の企業が「高度なコンサルティングができる税理士」に依頼すると、余計なコストがかかるだけでなく、必要のないサービスを契約させられてしまうリスクがあります。
成長期(3〜10年目)に適した税理士:資金繰り・融資・補助金サポートができる税理士
事業が軌道に乗ると、売上が増え、それに伴い税金負担も増えていきます。
成長期のフェーズでは、単なる税務処理だけでなく、資金繰りや融資・補助金活用に詳しい税理士が必要になります。
成長期(3〜10年目)に適した税理士の特徴は、以下の通りです。
- 融資の相談や金融機関との交渉に強い
- 節税対策の提案ができる
- 補助金・助成金の申請サポートが可能
もし、創業期の延長で「記帳代行専門の税理士」に依頼し続けると、資金繰りのアドバイスが不足し、成長のスピードが鈍化する可能性があります。
成熟期(10年以上)に適した税理士:事業承継・税務戦略に強い税理士
企業が10年以上続くと、経営の安定化だけでなく、次世代への事業承継や税務戦略が重要な課題になります。
成熟期(10年以上)に適した税理士の特徴は、以下の通りです。
- 相続・事業承継に関する専門知識がある
- 長期的な税務戦略を提案できる
- 会社の財務状況を分析し、利益最大化のアドバイスができる
成熟期であるにもかかわらず、創業期向けの「安価な記帳代行型税理士」などに依頼していると、事業承継や相続対策が不十分になり、結果的に高額な税金負担が発生するリスクがあります。
② 自社に合った税理士事務所を探す
自社の課題が整理できたら、次に「どんな税理士事務所を選ぶべきか」を検討しましょう。
ここで気をつけるべきポイントは、税理士事務所の規模やブランドに惑わされず、実際に担当することになる税理士の能力、および当人から提供されるサービスを見極めることです。
たとえば、大手の税理士事務所に依頼すると「知名度が高いから安心」と思うかもしれません。
しかし、大手事務所も結局は「法人」であり、組織として活動しています。
つまり、税理士事務所である以前に、組織としての効率を重視し、自社の利益を最大化するためにシステマチックに業務を進めるのです。
その結果、実際に担当するのは単に暇な者だったり、経験の浅いスタッフだったりと、経営者が期待するレベルのサポートが受けられないこともあります。
また、「料金が安いから」という理由で選ぶと、記帳代行や決算申告のみに特化した税理士になり、経営戦略の相談ができないという問題が起こることもあります。
今まで見てきたように、税理士の「型」には以下3つがあります。
| 低価格型税理士 |
業種特化型税理士 |
付加価値型税理士 |
|
|---|---|---|---|
| 記帳・決算代行 |
◯ | ◯ | ◯ |
| 経営相談・節税対策 |
× | △(業種による) | ◯ |
| 事業戦略の提案 |
× | △(税務に関するアドバイスのみ) | ◯ |
そこで続いては、税理士事務所を選ぶ際に知っておきたい3つのタイプについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。
「低価格型税理士」は決められた業務のみを行う
「とにかくコストを抑えたい」と考える経営者であれば、月額1万円〜2万円程度で契約できる「低価格型税理士」に魅力を感じる方も多いでしょう。
しかし、低価格型の税理士は基本的に「申告業務のみ」に特化しているため、経営アドバイスや節税対策は期待できません。
たとえば、「決算書の作成と税務申告だけをしてもらえれば十分」と考えている場合は問題ありません。
しかし、もし「事業の成長に合わせて、税金対策や資金繰りの相談もしたい」と思うなら、こうした税理士を選ぶと後々思いもかけないオプション料金を請求されることになったり、「そこは対応外です」と突き放されてしまったりして、後悔することになります。
「業種特化型税理士」なら自社の課題を相談できる
最近では、「IT業界専門」「飲食業向け」「不動産オーナー向け」など、特定の業種に特化した税理士事務所が増えています。
業種特化型の税理士は、その業界特有の税務知識や経営課題に詳しいことが特徴です。
たとえば、飲食業向けの税理士なら「原価率の管理」や「インボイス制度の影響」について詳しく、IT企業向けの税理士なら「クラウド会計やストック型ビジネスの税務」に精通している可能性が高いです。
ただし、業種特化型の税理士にはデメリットもあります。
そのデメリットは、「業界特有の知識はあるが、税務全般のスキルが十分とは限らない」という点です。
たとえば、「飲食業の税務には詳しいが、補助金や融資の知識が不足している」といったケースもあります。
そのため、業界特化型の税理士を選ぶ場合でも、「税務の基礎対応がしっかりできるか」を確認することが重要です。
「付加価値型税理士」は経営全体のサポートをしてくれる
経営者が「税理士にもっと積極的に経営アドバイスをしてほしい」と考えるなら、「付加価値型税理士」が適しています。
付加価値型税理士とは、単なる記帳代行や税務申告だけでなく、経営戦略・財務管理・資金調達などのアドバイスを提供する税理士のことを指します。
こうした税理士は、通常の顧問料よりも高めに設定されていることが多いですが、その分、次のようなメリットがあります。
- 融資・資金繰りのアドバイスがある
- 補助金や助成金の最新情報を教えてくれる
- 事業承継やM&Aなどの長期的な戦略をサポートしてくれる
- より踏み込んだ節税対策の提案が受けられる
たとえば、「今後3年以内に事業を拡大したい」「将来的に後継者へ会社を引き継ぎたい」と考えている場合、単なる税務処理だけでなく、経営視点を持った税理士の存在が頼りになることでしょう。
③ 事務所の実績・ブランドではなく「担当者ベース」で選ぶ
税理士事務所を選ぶ際、大手だから安心とは限りません。
事務所のブランドより、「自社の担当となる税理士の実力と相性」が重要です。
大手事務所と、相性の合う税理士のどちらを選ぶべきなのか、それぞれの特徴を比較してみましょう。
| 項目 |
大手税理士法人を選ぶ |
実力があり、相性の合う税理士を選ぶ |
|---|---|---|
| 知名度 |
高い | 低いこともある |
| 担当者の経験 |
若手が担当することがある | 経験豊富な税理士を選べる |
| サポートの柔軟性 |
画一的な対応になりがち | 会社の事情に合わせた提案が可能 |
| 費用 |
割高な場合が多い | コストパフォーマンスがよいことも |
| 相談のしやすさ |
担当者が固定されず、変わることがある | 直接相談しやすく、長期的な関係を築ける |
大手事務所に依頼しても、担当が経験の浅い税理士なら、資金繰りの相談をしても適切な回答が得られず、成長の機会を失う可能性があります。
税理士を選ぶ際は、必ず「誰が担当するのか?」を確認しましょう。
広告で「経営アドバイスができる」と書かれていても、実際の担当者がその知識を持っているとは限りません。
たとえば、資金繰りを相談しても「銀行に聞いてください」と言われるだけなら、意味がありません。
契約前の面談では、税理士の「連絡の速さ」「経営の視点」「具体的なアドバイス力」を確認することが大切です。
税務署から突然の連絡があった際、レスポンスの遅い税理士では対応が遅れ、余計な負担がかかることもあります。
また、決算や申告だけでなく、節税や補助金の活用について具体的な提案をしてくれるかも重要な判断材料です。
さらに、契約時に対応したのがベテラン税理士でも、実際の担当が新人というケースもあるため注意が必要です。
必ず「担当税理士と直接話したい」と伝え、対応を渋る事務所は避けましょう。
税理士選びは会社の成長に直結します。
ブランドではなく、実際に担当する税理士の実力を見極めて決めましょう。
④ セカンドオピニオンを活用し、複数事務所を比較する
税理士を選ぶ際に最も避けるべきなのは、「最初に話した税理士と、そのまま契約を結んでしまうこと」です。
税理士業界には、「士業だから信用して当然」といった態度を取り、一度契約したら簡単には変えられないと威圧的に迫る事務所もあります。
専門知識を盾にして「あなたの業界を何十年も見てきた」「税務は素人には分からない」「契約したら最後まで任せるのが普通」と言い切り、有無を言わせず契約を結ばせようとするケースもあるため注意が必要です。
すると経営者も「せっかく紹介されたから」「時間をかけたくないから」といった理由で、十分に比較せずに契約してしまいます。
こうした思い込みは、「現状維持バイアス」や「確証バイアス」によるもので、一種の思考停止による経費の無駄遣いといえます。
こうしたケースは少なくありません。
1社目で即決してしまうと、あとから「もっと良い税理士がいたかもしれない」と後悔するケースが多いのです。
たとえば、次のような失敗例が挙げられます。
- 紹介された税理士とすぐ契約したが、2年後に税務調査が入り、申告ミスが発覚。もっと慎重に選べばよかったと後悔
- 最初に相談した税理士は安価だったが、節税アドバイスがなく、後になって余計な税金を払っていたことに気づいた
- 知人に紹介された税理士と契約したが、対応が遅く、資金繰りの相談に乗ってくれず、結果として経営判断が遅れた
こうした事態を防ぐために、医者選びのように「セカンドオピニオン」として、税理士を決める前に必ず2〜3名と面談し、比較検討することが重要です。
初回相談だけなら、1時間程度無料で相談できる税理士事務所も多く存在します。
ぜひ初回相談を活用して、セカンドオピニオンの事務所を探してみてください。
税理士を比較する際に見るべきポイント
複数の税理士と面談するとき、何を基準に比較すればよいのでしょうか。
特に重要なのは、「この税理士は本当に経営に寄り添ってくれるか?」という視点です。
税理士に依頼する際、「どの税理士でも経営アドバイスをしてくれる」と思い込んでいる経営者は少なくありません。
しかし、実際には「記帳・申告をこなすだけの税理士」もいます。
そのような単純作業だけの税理士と「経営の視点を持ち、積極的にアドバイスをしてくれる税理士」では、得られる情報・価値が大きく異なります。
「税理士に相談すれば、資金繰りの助言や節税対策の提案をしてもらえるはずだ」と考えていたのに、実際には「うちは記帳と決算申告だけを担当します」と言われてしまい、「求めていたサポートを全く受けられなかった」というケースも多くあります。
どこまでの業務を依頼できるのかを事前に把握しておかないと、「経営の相談をしたいのに、ひたすら帳簿作成しかしてもらえない」という状況に陥り、後から後悔することになります。
この違いを理解した上で、自社に必要なサポートを受けられる税理士を選ぶことが重要です。
記帳型、経営サポート型を比較すると、以下の表のような違いがあります。
| 項目 |
記帳代行型税理士 |
経営サポート型税理士 |
|---|---|---|
| 主な業務 | 記帳・決算申告のみ | 節税・融資支援・経営相談まで対応 |
| 経営の視点 | なし(税務処理が中心) | あり(財務・経営のアドバイス) |
| 節税提案 | ほぼなし | 個別に最適な節税策を提案 |
| 料金 | 安価(月額1〜3万円) | 高め(月額5万円以上) |
| 企業の成長への貢献度 | 低い | 高い |
「税理士は記帳・申告をしてくれればいい」と考えているなら記帳代行型でも構いません。
しかし、もし「経営の視点を持ったアドバイスが欲しい」「将来的な税務戦略を相談したい」と考えているなら、経営サポート型の税理士を選ぶべきです。
この違いを見極めるために、面談では次のような3つの質問を投げかけることを意識してみてください。
| 質問 |
チェックポイント |
|---|---|
| 「うちの会社の業界で、よくある税務上のリスクは何か?」 | 具体的な事例を挙げて説明できる税理士は、実務経験が豊富な可能性が高い |
| 「決算対策で、今すぐできる節税策は何か?」 | その場で即答できない場合、税務戦略に強くない可能性がある |
| 「売上が2倍になった場合、どんな税務・財務対策が必要か?」 | 成長フェーズに合わせたアドバイスができるかどうかを見極める |
こうした質問に対し、曖昧な答えしか返ってこない場合、その税理士は「単なる記帳代行型」である可能性が高いです。
比較することで見えてくる「税理士の質」
複数の税理士と面談をすると、税理士ごとの対応の違いがはっきりします。
たとえば、同じ質問をしたときに次のような違いがあるかもしれません。
- 税理士A:「今期の利益が出ているので、来期に経費を先送りするのも一案ですね」(節税策の提案がある)
- 税理士B:「決算書を作るだけなので、特に何も考えなくて大丈夫ですよ」(アドバイスなし)
- 税理士C:「経営計画を作成して、最適な資金調達方法も検討しましょう」(経営の視点を持っている)
このように、実際に話してみると、税理士によって視点が大きく異なることがわかります。
比較をしないまま契約してしまうと、後になって「もっと親身になってくれる税理士がいたかもしれない」と後悔することになりかねません。
自社に最適ないい税理士かどうかを見極める5つの基準
ここまで、税理士の探し方や比較の重要性について説明しました。
しかし、実際に複数の税理士と話してみても、「この人が本当にいい税理士なのか?」と判断に迷うことは少なくありません。
いい税理士かどうかを見分ける基準として、以下5つがあります。
- 営業担当者ではなく、実際の税務担当者と初回相談できるか?
- レスポンスの速さ・経営アドバイスの有無はどうか?
- 料金体系に透明性はあるか?(安さだけで選ばない)
- 不要な投資・保険商品をすすめてこないか?
- 長期的に経営をサポートできるか?
こうしたポイントを押さえておけば、適当な税理士を選んでしまうリスクを大幅に下げることができます。
以下から、それぞれ詳しく見ていきましょう。
営業担当者ではなく、実際の税務担当者と初回相談できるか?
税理士事務所によっては、「営業担当者」が最初の相談を受けるケースがあります。
しかし、営業担当者とどれだけ話しても、実際にあなたの税務を担当する税理士のスキルや相性は分かりません。
たとえば、初めての事務所訪問で次のような会話があったとしたら、どうでしょうか。
- 営業担当者:「当事務所は500社以上のクライアントがいます。実績も豊富です」
- 経営者(あなた):「それはすごいですね!具体的にはどんなサポートが受けられるのですか?」
- 営業担当者:「詳しいことは、実際に担当する税理士にお任せいただく形になります」
このように、営業担当者が対応すると、実際にサポートを受ける税理士の人柄や能力が分からないまま契約することになります。
こうした状態を避けたいのであれば、契約前に「実際に担当する税理士と話したい」と伝え、面談を設定することが重要です。
もしこの要望を拒否された場合、その事務所は避けたほうが無難です。
レスポンスの速さ・経営アドバイスの有無はどうか?
税理士に求めるべきものは、単なる「記帳・申告代行」だけではありません。
経営の相談に乗ってくれるかどうか、そしてレスポンスが速いかどうかも重要です。
たとえば、税務や資金繰りの相談をした際に、次のような対応の違いがあります。
- 税理士A:「すぐに確認しますね!」→ 当日中に回答がくる
- 税理士B:「確認しておきます」→ 3日経っても返信がない
- 税理士C:「それは経営の問題なので、私の仕事ではないですね」→ 相談をはぐらかされる
当初の契約において、記帳代行のみを依頼する内容だったのであれば、Cのケースもやむを得ないかもしれません。
しかし、A以外のケースのように税理士の対応が遅いと、経営の判断が遅れ、資金繰りや税務対策のチャンスを逃す可能性があります。
また、経営の相談に対して積極的にアドバイスできる税理士かどうかも、長期的な成長ができるかどうかに関係します。
この基準をチェックするのであれば、「質問したとき、最低どのくらいの速さで答えてくれるか?(メール、メッセージアプリなど意思疎通媒体も確認)」と「経営アドバイスがあるか」を面談で聞いてみるとよいでしょう。
料金体系に透明性はあるか?(安さだけで選ばない)
税理士の料金は、事務所によって異なります。
たとえば、税理士のタイプ別に次の表のような料金設定が考えられます。
| 種類 |
月額料金 |
特徴 |
|---|---|---|
| 低価格型(記帳代行中心) | 1万円〜3万円 | 記帳・決算申告のみ、経営アドバイスなし |
| 標準型(一般的な税理士) | 3万円〜8万円 | 基本的な節税提案あり、補助金情報なども提供 |
| 経営サポート型 | 8万円以上 | 経営コンサルティング、資金調達支援も対応 |
ここで注意すべき点は、「安いからお得」と考えてはいけないということです。
税理士の仕事は、単なる「費用」ではなく「投資」と考えるべきです。
たとえば、月額5万円の税理士が、適切な節税対策を提案して年間100万円の税負担を軽減してくれるなら、むしろコストパフォーマンスが良いということになります。
料金体系およびその料金である理由を事前に明らかにするためには、「安さ」ではなく「何をしてくれるのか」を確認し、料金とサービス内容のバランスを見極めるようにしましょう。
不要な投資・保険商品をすすめてこないか?
税理士の中には、税務相談のついでに「投資商品」や「生命保険」をすすめてくる方がいます。
もちろん、税理士が金融知識を持っていること自体は悪いことではありません。
しかし、本来の税務サポートとは関係のない商品を勧められる場合、手数料目的の営業である可能性が高いので注意が必要です。
たとえば、次のようなケースは要注意です。
- 「節税のために、この保険に加入しませんか?」(高額な生命保険)
- 「法人向けの投資信託で税金を減らせますよ」(手数料が高い金融商品)
本当に経営者のことを考える税理士であれば、「自分に手数料の入る商品」ではなく、「会社の利益を最大化する方法」を提案するはずです。
このような話が出たら、その税理士の解約を考えるのもありです。
真意を確かめたければ、急に投資や保険の話が出たときに「この商品を私が契約することで、あなたに手数料は入りますか?」と率直に聞いてみるべきでしょう。
逆に、それぐらい腹を割って話せる相手でなければ、経営の根幹に関わるような望ましいパートナーにはなれないはずです。
長期的に経営をサポートできるか?
税理士を選ぶ際は「今だけではなく、長期的に付き合えるか」を考えることが大切です。
会社の成長フェーズによって、求める税理士の役割は以下のように変わっていくことはこれまでも触れてきました。
- 創業期(0〜3年):記帳・決算・融資支援
- 成長期(3〜10年):節税対策・資金繰り・補助金支援
- 成熟期(10年以上):事業承継・税務戦略のサポート
このように、事業フェーズごとに最適な税理士の条件が変わるため、「長く付き合える税理士か?」を考えて選ぶことが大事です。
長期的な経営サポートができるかどうかの基準を知りたければ、契約前に「会社の成長に合わせてどんなサポートをしてくれるか?」を具体的に確認してみましょう。
自社に最適なパートナー税理士を見つけたいならTHE CXOにご相談ください!
ここまで、一般的な税理士の探し方や、いい税理士を見極めるための基準について詳しく解説しました。
しかし、「自分でいい税理士を探し、比較し、見極めるのは難しい」と感じる経営者も多いはずです。
そこで、私たちTHE CXOは、単なる税理士紹介ではなく、「経営に本当に役立つ税理士」とのマッチングを提供するサービスを行っています。
| 一般的な税理士紹介 |
THE CXO |
|
|---|---|---|
| 紹介基準 |
業種・地域・予算のみ | 経営課題にフィットするか |
| 紹介対象 |
事務所単位で紹介 | 実際の担当税理士を紹介 |
| 手数料の仕組み |
紹介手数料ビジネス | 手数料なし(経営者目線) |
| 経営サポート |
ほぼなし(別途費用) | 節税・資金繰り・成長戦略 |
THE CXOは、一般的な税理士紹介サービスとは異なり、「単なるマッチングではなく、経営の成長をサポートできる税理士の紹介」にこだわっています。
そのため、次の3つのような特徴を持っています。
事務所単位ではなく、「実際の担当者ベース」で税理士を紹介
THE CXOでは、単に「○○税理士事務所」と紹介するのではなく、実際に担当する税理士のスキル・人柄・対応力を重視してマッチングを行います。
たとえば、「IT業界に詳しく、クラウド会計の導入支援ができる税理士」「節税対策だけでなく、融資支援にも強い税理士」といった形で、経営者のニーズにジャストフィットする税理士を選定します。
セカンドオピニオンの活用を推奨
契約前に、「現在の税理士と比較して、本当に最適な税理士なのか?」を判断するため、セカンドオピニオンの活用を推奨しています。
たとえば、「今の税理士が悪いとは思わないけど、他の意見も聞いてみたい」という場合、別の税理士にも相談できる機会を提供し、比較検討する機会を持っていただきます。
経営フェーズごとに最適な税理士をマッチング
税理士は「会社の成長フェーズ」によって求められるスキルが異なります。
- 創業期(0〜3年):記帳・決算・融資サポートが得意な税理士
- 成長期(3〜10年):節税・資金繰り・補助金支援が得意な税理士
- 成熟期(10年以上):事業承継・M&A・財務戦略が得意な税理士
THE CXOでは、こうしたフェーズごとの課題を踏まえ、単なる「税務処理担当」ではなく、「経営の未来を支える税理士」を厳選してご紹介します。
従来の方法では不十分!自社にとって最適ないい税理士を見つけよう!
今回は、「いい税理士」を見つけるための正しい方法について詳しく解説しました。
多くの経営者は、「間違った探し方」や、「比較せずに即決してしまうリスク」、そして「本当に経営の役に立つ税理士を選ぶための基準」を知らず、税理士の探し方を間違えてしまいがちです。
税理士は、単なる「税務処理の代行者」ではなく、会社の未来を左右する重要なパートナーです。
しかし、一般的な探し方では、本当に経営に役立つ税理士を見つけるのが難しいのが現実です。
事務所のブランドや料金の安さではなく、「実際に担当する税理士のスキルと相性」を重視することが、失敗しない税理士選びの鍵となります。
また、セカンドオピニオンを活用し、複数の税理士と比較検討することも重要です。
THE CXOでは、手数料目的の単なる紹介ではなく、経営の成長を本気でサポートできる税理士とのマッチングを提供しています。
「税理士選びで後悔したくない」「経営のパートナーとして頼れる税理士を見つけたい」と考えているなら、従来の選び方を見直し、会社の未来を見据えた最適な税理士と出会えるよう、私たちにご相談ください。