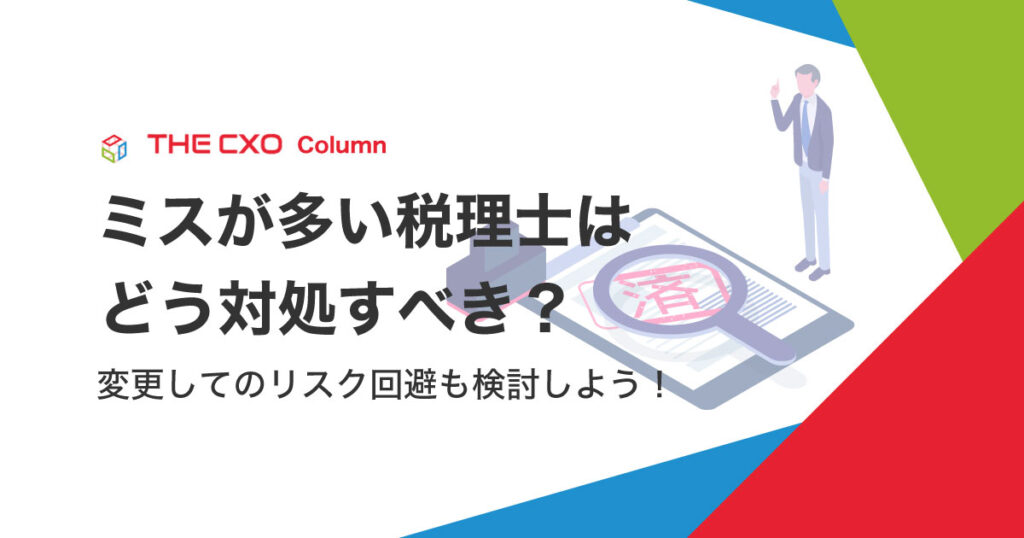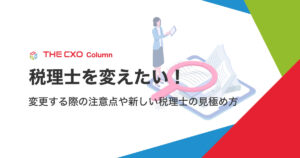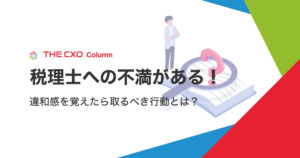税理士変更でよくあるトラブルや対策・安全な乗り換え方
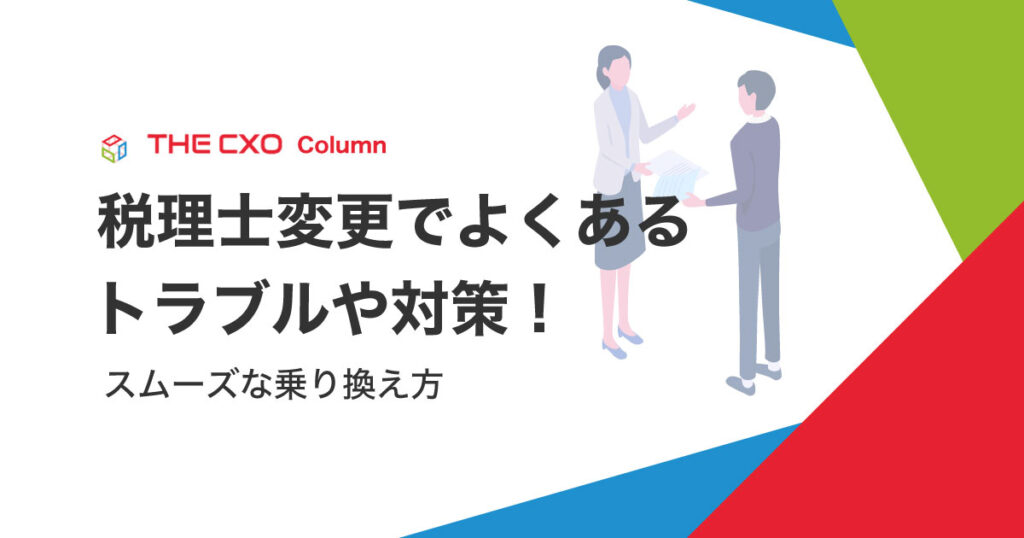
税理士を変更したいと考えたとき、多くの方が「スムーズに進められるだろう」と思いがちですが、実際にはさまざまなトラブルが発生することがあります。
契約解除をめぐる問題や、必要な書類の返却が滞るケース、さらには新しい税理士とのミスマッチなど、税理士変更には課題がつきものです。
さらに、税理士の選び方を誤ると、変更後も満足のいくサービスを受けられず、結果的に「変更しなければよかった」と後悔することにもなりかねません。
そこで、この記事では、税理士変更に関するトラブルの具体例や対策について詳しく解説します。
株式会社カタリスタ 代表取締役
THE CXO 株式会社 代表取締役
飯島 彰仁(いいじま あきひと)
Iijima Akihito
経営計画コンサルタント、中小企業の社外CXO。大手会計事務所元代表取締役社長として、同社を年商22億円、従業員数447名の規模にまで成長させた実績を持つ。
これまで3,000社以上の中小企業に対し、財務やマーケティングを通じた経営向上に貢献。
その中で、中小企業の成長のためには、単なる税務処理を超え、経営に深く関与する税理士が必要不可欠であることを痛感。
その経験をもとに、税理士が真の価値を発揮する「社外CXOメソッド」を開発。累計300人以上の税理士に伝授し、「税務の枠を超え、中小企業のあらゆる相談に乗れるパートナー」を養成。
指導した税理士達からは、顧問先の売上向上、利益向上、V字回復や事業改善など成功報告が続々と寄せられている。

- 1. 税理士変更に伴うよくあるトラブル一覧と対策・予防策
- 1.1. 必要書類が返却されない
- 1.2. 新しい税理士に情報が引き継がれない
- 1.3. 顧問契約解除時に法外な料金を請求される
- 1.3.1. 適正な契約解除料金とは?
- 1.3.2. 違法な請求に対する対処法
- 1.4. 税理士に契約解除を拒否される
- 1.4.1. 税理士との契約解除をスムーズに進める方法
- 1.5. 後任の税理士と上手くいかない
- 1.5.1. 「安いから」という理由だけで選んでしまった
- 1.5.2. 業種に詳しくない税理士を選んでしまった
- 1.5.3. 税務調査への対応など、税務処理に不安がある税理士を選んでしまった
- 1.5.4. 後任の税理士を見極める3つのポイント
- 1.6. 企業の内部情報を勝手に暴露される
- 1.6.1. 情報漏洩の具体例
- 1.6.2. 情報漏洩を防ぐためにできること
- 2. 税理士変更のトラブルでよくある誤解
- 2.1. 税理士変更のタイミングで税務調査が入る理由
- 2.1.1. なぜ税理士変更と税務調査が結びつけられるのか?
- 2.1.2. 税務調査が入りやすい状況とは?
- 2.1.3. 税務調査の不安を軽減するためにできること
- 3. すでに起きてしまった税理士変更トラブルの対処法3つ
- 3.1. 【対処法1】トラブルの証拠を整理しておく!
- 3.1.1. 証拠として確保すべきもの
- 3.2. 【対処法2】税理士会へ問い合わせて正しく対処をする!
- 3.2.1. 税理士会への相談方法・手順
- 3.3. 【対処法3】必要に応じて弁護士に相談する!
- 3.3.1. 弁護士に相談する前に準備すべきこと
- 4. 税理士変更をトラブルなく穏便に進めるための断り方とは?
- 4.1. 税理士側の明らかな非が原因の場合の伝え方
- 4.2. 今後を見据えた税理士変更の場合の伝え方
- 4.3. 長年契約している税理士に対する配慮ある断り方
- 4.4. 親戚・知人の税理士との契約解消の方法
- 5. そもそも選び方が悪いから税理士変更のトラブルが起こる
- 5.1. 「お腹が痛いなら眼科には行かない」=自社の課題に合わない税理士を選ぶと失敗する
- 6. トラブルを起こさず後悔しない、本当の税理士の選び方
- 7. THE CXOでより良い税理士を見つけ、トラブルなく変更を進めよう!
税理士変更に伴うよくあるトラブル一覧と対策・予防策
税理士を変更すると、典型的なトラブルとして、以下が起こる可能性があります。
- 必要書類が返却されない
- 新しい税理士に情報が引き継がれない
- 顧問契約解除時に法外な料金を請求される
- 税理士に契約解除を拒否される
- 後任の税理士と上手くいかない
- 企業の内部情報を勝手に暴露される
以下からは、こうしたトラブルについて詳しく見ていきましょう。
必要書類が返却されない
税理士を変更する際、顧問税理士に預けていた書類が返却されないケースがあります。
たとえば、帳簿、決算書、確定申告書、契約書類など、本来であれば企業側が管理すべき重要な書類が返ってこないと、新しい税理士にスムーズに引き継ぐことができず、会計処理が止まってしまう原因になります。
こうしたトラブルを防ぐためには、事前に「どの書類を預けているのか」を整理し、リストアップしておくことが重要です。
また、前の税理士に契約解除を申し出る際には、書類を返却してほしいことをはっきり伝え、スムーズに引き渡させるようにしましょう。
もし書類の返却を拒まれる場合は、「税理士法」に基づいてきちんと対処することが必要です。
税理士法第38条、第54条にある通り、税理士は守秘義務があるため、依頼者の書類を返さないことは大きな問題となります。
(秘密を守る義務)
引用元:税理士法 第38条| e-Gov 法令検索
第三十八条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
引用元:税理士法 第54条 | e-Gov 法令検索
第五十四条 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。
そのため、書類を返してもらえない場合は、税理士会へ相談することで、解決できることがあります。
新しい税理士に情報が引き継がれない
税理士を変更すると、過去の会計データや申告情報がスムーズに引き継がれないことがあります。
特に、会計ソフトのデータがきちんと移されなかったり、前の税理士が引き継ぎに非協力的だったりすると、新しい税理士が業務を開始するまでに時間がかかってしまいます。
たとえば、前の税理士が使っていた会計ソフトが、新しい税理士のシステムと互換性がない場合、データ移行に手間がかかり、最悪の場合、過去の取引を一つ一つ手入力しなければならないケースもあります。
このような事態を避けるためにも、税理士変更を考える段階で、新しい税理士と相談し、必要なデータのフォーマットや移行方法を確認しておくとよいでしょう。
また、税理士変更をする前に、過去の申告書類や帳簿のデータをすべて手元に確保し、新しい税理士へきちんと引き渡す準備を整えておくことが大切です。
顧問契約解除時に法外な料金を請求される
税理士との契約を解除しようとした際、違約金や高額な請求を求められることがあります。
本来、顧問契約は双方の合意のもとで解除できるものですが、一部の税理士事務所では、依頼者側が法律の素人であることをいいことに、不当な請求をしてくるケースが見受けられます。
たとえば、「契約期間の途中解約だから、残りの契約期間分の報酬を全額払ってもらう必要がある」と主張されたり、「過去の決算処理の手間賃」として高額な精算金を請求されたりすることがあります。
特に地方では、「客を奪われた」と逆恨みし、法外な請求をしてくる事務所もまだ存在するようです。
適正な契約解除料金とは?
税理士の報酬は、契約内容によって異なります。
しかし、契約解除に伴う費用が発生する場合でも、一般的には次の表の範囲に収まるべきです。
| 費用の種類 |
内容 |
|---|---|
| 月額顧問料の精算 | すでに発生した月額顧問料の未払い分については、支払う必要がある。 |
| 決算業務の完了報酬 | 進行中の決算業務や申告作業がある場合、その分の報酬が請求される可能性がある。ただし、契約時の報酬規定に明記されていない場合、支払い義務はない。 |
| 違約金の適用範囲 | 契約書に違約金の取り決めがある場合、契約に基づいて支払い義務が発生することがある。しかし、過度に高い違約金は無効と判断されることが多いため、納得できない場合は税理士会や弁護士に相談するのが望ましい。 |
違法な請求に対する対処法
もし、不当な料金を請求された場合は、契約書の内容をよく確認し、請求の正当性を確かめることが大切です。
税理士側が口頭で請求を主張してきた場合でも、契約書に記載がなければ支払う必要はありません。
また、「顧問契約解除の際には、過去の書類やデータを返却しない」といった対応を取る税理士もいますが、これは税理士法に違反する可能性があります。
こうした場合には、税理士会へ相談すると、正しく対応してもらえることがあります。
税理士に契約解除を拒否される
顧問税理士を変更しようとした際、「今の契約期間が終わるまで解約はできない」「あと少しで決算だから最後までやらせてほしい」などと言われ、解約を引き延ばされるケースがあります。
特に、長年付き合いのある税理士ほど、「せっかくこれまでサポートしてきたのに、突然契約解除は困る」と感情的になりやすく、スムーズに解約できないことがあります。
しかし、顧問契約は事前の通告があれば、基本的に一方的に解除が可能です。
税理士との契約解除をスムーズに進める方法
今の税理士と契約解除したい場合は、以下の手順で進めてみてください。
| 契約書の解除条件を確認する:顧問契約を締結する際、多くの契約書には「解除の際は◯ヶ月前に通知すること」などの条項が記載されています。契約内容を確認し、正規の手順で解約を申し出ることが大切です。 書面で通知する:口頭で契約解除を伝えても、「聞いていない」「そんな話はしていない」と言われる可能性があります。内容証明郵便やメールで、書面として通知を残しておくことが重要です。 穏便な言い回しを工夫する:税理士との関係を悪化させず、スムーズに解約を進めるためには、「業務内容を見直した結果、別の視点を持つ税理士の意見も聞きたくなった」など、角の立たない理由を伝えるのも一つの方法です。 |
後任の税理士と上手くいかない
税理士を変更したにもかかわらず、「思っていたサービスと違う」「前よりも対応が悪くなった」といった不満を感じるケースがあります。
新しい税理士とのミスマッチが起こる原因は、大きく分けて以下の3つです。
- 「安いから」という理由だけで選んでしまった
- 業種に詳しくない税理士を選んでしまった
- 税務調査への対応など、税務処理に不安がある税理士を選んでしまった
また、後任にふさわしい税理士を見極めるためのコツも存在します。
以下からは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
「安いから」という理由だけで選んでしまった
税理士を探す際、「できるだけ顧問料を安く抑えたい」と考えるのは当然です。
しかし、単に安いだけの税理士を選んでしまうと、以下の表のような問題が発生する可能性があります。
| 問題点 |
内容 |
|---|---|
| 税理士が十分な時間を割いてくれない | 格安の顧問契約では、一人の税理士が多くの企業を担当するため、「質問してもすぐに返信が来ない」「訪問してもらえない」といった不満が生じやすい。 |
| 記帳代行だけで終わり、アドバイスがもらえない | 本来、顧問税理士には「経営の相談相手」としての役割が求められるが、料金が極端に安い場合、税務申告の最低限の作業のみしか対応してもらえず、経営アドバイスや節税の提案が期待できない。 |
| 結果的にコストが増える | 税理士の正しいアドバイスがないことで誤った税務処理が行われ、本来払わなくてよい税金を余分に支払うことになり、結果的に損をする可能性がある。 |
業種に詳しくない税理士を選んでしまった
税理士にも得意分野があります。
業種によって適用される税制や助成金の制度が異なるため、業界知識のある税理士でなければ正しいアドバイスができません。
たとえば、飲食業の税務は「仕入れ管理」や「現金取引の多さ」が重要なポイントですが、製造業では「設備投資や減価償却の扱い」が大きな課題になります。
このような違いを理解していない税理士に依頼してしまうと、次のように経営のサポートどころか、必要な税務処理すらきちんと行われないことがあります。
税務調査への対応など、税務処理に不安がある税理士を選んでしまった
税務調査は、企業にとって大きなリスクとなる可能性があります。
その際、税理士がどれだけきちんと対応できるかが重要です。
しかし、税務調査の経験が少ない税理士や、交渉力のない税理士を選んでしまうと、以下のような問題が発生します。
| 問題点 |
内容 |
|---|---|
| 税務署からの指摘に対してきちんと反論できない | 経験の少ない税理士は、税務調査で指摘を受けた際に、正しく説明や交渉ができず、本来不要な修正申告や追徴課税が発生する可能性がある。 |
| 必要以上に税金を支払うことになる | 税務調査では「どこまで主張できるか」が重要。経験豊富な税理士であれば交渉により不要な税金を抑えられるが、経験が浅い税理士では「税務署の言いなり」になり、多く支払ってしまうケースがある。 |
しかしながら、税務調査はよほどのことがなければ起こりません。
常に税務調査を不安視しなければならない状態なのであれば、まずはその経営体質を根本から変えられる、経営サポート型の税理士とご相談されることがおすすめです。
後任の税理士を見極める3つのポイント
税理士を変えたのに「思っていたのと違った…」と後悔しないために、新しい税理士を選ぶ際には慎重な見極めが必要です。
特に、業務範囲や得意分野を事前に確認しておかないと、後になって「こんなはずじゃなかった」と感じることになりかねません。
以下の表で3つのポイントを押さえて、失敗のない税理士選びを進めましょう。
| ポイント |
内容 |
|---|---|
| 税理士に求める業務内容をはっきりさせておく | 自社が記帳代行だけでなく、経営アドバイスを求めるのかを事前に整理する。「節税提案」「融資サポート」など、自社のニーズに合った業務をしてくれるかを確認する。 |
| 業種に詳しい税理士を探す | 自社と同業の顧問経験がある税理士かを確認する。「この業界の税制はよくわからない」と話すような税理士には依頼しない。 |
| 税務調査や補助金申請に対応できるかを確認する | 過去に税務調査の対応経験があるかを聞く。補助金申請や経営改善の支援ができる税理士かどうかもチェックする。 |
企業の内部情報を勝手に暴露される
税理士には守秘義務があります。
税理士法第38条や第54条に基づき、業務上知り得た顧客の情報を外部に漏らすことは禁じられています。
しかし、悪意のある税理士や、不注意な税理士による情報漏洩が発生するケースもあるため注意が必要です。
情報漏洩の具体例
税理士による情報漏洩として、以下の2点が挙げられます。
| 漏洩のパターン |
具体例 |
|---|---|
| 競合企業に経営状況を話されてしまった | 税理士を変更した後、ライバル会社に自社の財務状況が漏れていることが発覚。調査の結果、以前の税理士が、競合企業のクライアントとの雑談の中で話してしまっていたことが原因だった。 |
| 銀行に不必要な情報を伝えられた | 企業が融資を申請した際、税理士が銀行に「この会社の経営は厳しい」と余計な発言をしてしまい、結果的に融資審査が通らなかった。 |
情報漏洩を防ぐためにできること
プロ意識が低い税理士によって、自社の財務状況や経営情報が外部に漏らされてしまうことも考えられます。
こうした情報漏洩を防ぐために、以下のポイントを押さえ、自衛意識を持っておきましょう。
| 対策 |
内容 |
|---|---|
| 契約時に守秘義務の確認をする | 「税理士には守秘義務があることは理解していますよね?」とあえて確認することで、意識させる |
| 情報漏洩が疑われる場合は税理士会に相談する | 税理士法第38条違反として処分対象になるため、問題があれば税理士会へ報告する |
しかし、契約してしばらく経ってから「この税理士、大丈夫かな?」と不安になることもあるかもしれません。
最初は良さそうに見えても、後から「まさかこんなことをするなんて…」というケースもあります。
あなたに悪気がなくても、信用した相手が勝手に情報を漏らしてしまうこともあるのです。
THE CXOの税理士紹介サービスならそんな心配はいりません。
信頼できる税理士だけを厳選して紹介しているので、「ちゃんと仕事をしてくれるか?」「情報を勝手に漏らさないか?」といった不安を抱えずに、安心して任せることができます。
税理士変更のトラブルでよくある誤解
税理士を変更する際に、「トラブルになる」と思われがちなものの、実は単なる誤解であるケースも少なくありません。
特に、「税理士を変えると税務調査が入る」といった話は、多くの経営者が気にするポイントですが、これは事実ではありません。
税理士を変更すること自体が税務調査における直接的なトラブルの原因になるわけではないため、正しい情報を知っておくことが大切です。
以下からは、税務調査の誤解について詳しく説明していきます。
税理士変更のタイミングで税務調査が入る理由
「税理士を変更すると税務署に目をつけられて、税務調査が入る」という話を耳にしたことがある方も多いでしょう。
しかし、実際には税理士変更と税務調査の実施には直接的な関係はありません。
以下から詳しく説明します。
なぜ税理士変更と税務調査が結びつけられるのか?
税理士を変えるだけで税務署が動くことはありませんが、税理士変更と税務調査のタイミングが重なることはあります。
以下の表で詳しく見ていきましょう。
| 理由 |
内容 |
|---|---|
| 新しい税理士が問題点を指摘するから | 税理士を変更すると、新しい税理士が過去の帳簿や申告内容をチェックする。このとき、前の税理士のミスや経理処理の曖昧さが見つかると、修正申告を勧められることがある。修正申告をすると税務署が過去の申告内容に注目し、結果的に税務調査につながる可能性がある。 |
| 過去の申告が不適切だった場合、タイミング的に重なることがある | 税務調査は通常3年から5年ごとに行われるため、たまたま税理士を変更した時期と税務署の調査対象期間が重なり、「税理士を変えたから税務調査が入った」と勘違いされることがある。 |
| 「税理士を変える=不正を疑われる」と考えてしまう | 一部の経営者は「税理士を変えると、不正を隠そうとしていると思われるのでは?」と不安を感じることがある。しかし、税務署は税理士変更自体を問題視しないことが多く、むしろ「しっかりと税務を行うようになった」と判断されることが多い |
このように、税務調査が入る理由ははっきりしており、税理士を変えたタイミングで調査されたとしても、たまたまです。
税務調査が入りやすい状況とは?
実際に税務調査が入りやすいのは、次のようなケースです。
- 売上や利益が急激に変動した(前年より大幅な増減があった)
- 消費税の還付を頻繁に受けている
- 役員報酬が異常に高い、または変動が大きい
- 交際費や経費が極端に多い
- 現金取引が多い業種(飲食業、小売業、夜職など)
つまり、税理士変更自体が税務調査の要因ではなく、事業の状況や申告内容が不自然であれば、調査の対象になりやすいということです。
税務調査の不安を軽減するためにできること
「税務調査が入るかもしれない」と不安に感じる場合は、事前に準備をしておくことで、慌てずに対応できます。
以下のポイントを押さえて、税務調査への対策を万全に整えましょう。
| 対策 |
内容 |
|---|---|
| 新しい税理士に過去の申告内容をチェックしてもらう | 税理士変更後は、できるだけ早めに過去の申告書類を確認してもらい、問題点がないかをチェックする。 |
| 帳簿や証憑(しょうひょう:請求書や領収書などの証拠書類)を整理しておく | もし税務調査が入った場合でも、正しく書類が揃っていれば問題なく対応できる。 |
| 正しく節税対策を行う | 税理士と相談し、過去の処理方法に問題がなかったかを確認し、正しく節税ができているかを見直す。 |
すでに起きてしまった税理士変更トラブルの対処法3つ
税理士変更に伴うトラブルは、事前に防ぐのが理想的ですが、すでに発生してしまった場合は、きちんと対応することが重要です。
実際にトラブルが起こった際の対処法は、以下の3つです。
- 【対処法1】トラブルの証拠を整理しておく!
- 【対処法2】税理士会へ問い合わせて正しく対処をする!
- 【対処法3】必要に応じて弁護士に相談する!
以下から、詳しく見ていきましょう。
【対処法1】トラブルの証拠を整理しておく!
契約書の内容や過去のやり取りを確認し、どのような問題が発生しているのかをはっきりさせましょう。
証拠として確保すべきもの
税理士との間でトラブルが発生した場合、まずすべきことは、証拠を整理し、状況をわかりやすくしておくことです。
| 証拠として確保すべきもの |
内容 |
|---|---|
| 契約書や顧問契約の内容 | 「契約解除の条件」「違約金の有無」「報酬の詳細」などを確認する。 |
| メールやLINE、書面でのやり取り | 「書類の返却を依頼したのに、対応してくれない」「高額な請求をされた」などの証拠をスクリーンショット撮影などで残す。 |
| 請求書や振込履歴 | 不当な請求をされた場合、過去の支払い履歴と照らし合わせて、不審な点を整理する。 |
証拠が整理できたら、次にどう動くべきかを考えます。
【対処法2】税理士会へ問い合わせて正しく対処をする!
税理士には、税理士法という法律のもとで業務を行う義務があります。
もし、税理士の対応に問題がある場合、税理士会へ問い合わせることで、正しく対処を求めることができます。
特に、以下のようなケースでは、税理士会へ報告することを検討しましょう。
| 相談すべきケース |
内容 |
|---|---|
| 税理士が書類を返してくれない | 税理士は、依頼者の書類を預かっている場合、きちんと返却する義務がある。返却を拒否するのは、税理士法違反の可能性があるため、税理士会に相談できる。 |
| 不当な違約金や高額な請求をされた | 契約内容を超えた不当な請求が行われた場合、税理士会が仲介してくれることがある。 |
| 守秘義務違反が疑われる | 企業の内部情報が外部に漏洩した場合、税理士の守秘義務違反に該当し、懲戒処分の対象になる可能性がある。 |
税理士会への相談方法・手順
税理士とのトラブルを税理士会に相談する際は、事前に準備をしておくことで、スムーズに対応してもらえます。
以下の方法と手順を参考にしてみてください。
| 相談の手順 |
内容 |
|---|---|
| 所属する税理士会を調べる | 税理士は全国各地の税理士会に所属しているため、税理士が所属する税理士会を調べ、連絡を取る。 |
| 証拠を整理して相談する | 口頭だけでなく、契約書・メール・請求書などの証拠を揃えて相談すると、スムーズに対応してもらえる。 |
| 解決策を確認する | 税理士会が調査を行い、問題がある場合は正しく指導や処分を行うことがある。 |
たとえば、相手の税理士が東京税理士会に所属している場合は、東京税理士会の紛議調停制度を利用して相談が可能です。
ただし、相手の税理士が別の地域の税理士会(関東信越税理士会、大阪税理士会など)に所属している場合は、該当する税理士会の窓口を確認し、正しく機関へ問い合わせる必要があります。
【対処法3】必要に応じて弁護士に相談する!
税理士とのトラブルが深刻で、話し合いで解決しない場合、弁護士に相談することも検討しましょう。
以下のように、深刻な税理士とのトラブルでは、弁護士による法的手段を検討する必要があります。
| 相談すべきケース |
内容 |
|---|---|
| 税理士が書類を返却しないことで、業務に支障が出ている | 重要な書類が返却されず、決算処理や申告業務に支障が出ている場合、法的手段での対応を検討する。 |
| 高額な違約金を請求され、支払いを求められている | 法外な請求に対し、支払い義務があるのかを確認する必要がある。 |
| 税理士が経営情報を勝手に第三者に漏らした | 競合他社に情報が漏れた場合、損害賠償請求を視野に入れることもある。 |
弁護士に相談する前に準備すべきこと
税理士トラブルは専門性が高いため、税務に強い弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士への相談をする前には、以下の準備をしておきましょう。
| 準備すべきこと |
内容 |
|---|---|
| 証拠を整理する(契約書・メール・請求書など) | 具体的な証拠を揃え、税理士の問題行為をはっきり示せるようにする。 |
| これまでの経緯を時系列でまとめる | いつ、どのような問題が発生したのかを整理し、スムーズに説明できるようにする。 |
| 解決したいポイントをはっきりさせておく | 「書類を返してほしい」「不当な請求を取り下げてほしい」など、自分が求める解決策をしっかり決めておく。 |
適切な準備をしたうえで弁護士に相談すれば、無駄な時間や費用を抑えて問題を解決しやすくなります。
税理士変更をトラブルなく穏便に進めるための断り方とは?
税理士を変更する際、多くの経営者が悩むのが「どうやって今の税理士に伝えればよいのか?」という点です。
特に、長年付き合いのある税理士や、知人・親戚の税理士の場合、関係を悪化させずに契約を終了するのは難しいと感じるかもしれません。
しかし、次のように状況別に考えることで、トラブルを避けてみてください。
- 税理士側の明らかな非が原因の場合の伝え方
- 今後を見据えた税理士変更の場合の伝え方
- 長年契約している税理士に対する配慮ある断り方
- 親戚・知人の税理士との契約解消の方法
以下からは、それぞれの「上手な断り方」について、詳しく見ていきましょう。
税理士側の明らかな非が原因の場合の伝え方
税理士を変更する理由の中には、「明らかに税理士側のミスや対応の悪さが原因である」というケースもあります。
たとえば、以下のようなケースです。
- 申告ミスが発生し、税務署から指摘を受けた
- レスポンスが遅く、必要な時に相談できない
- 節税や補助金の提案がまったくない
- 決算直前になって急に連絡が来るが、普段のフォローは一切ない
こうした場合、経営者としては不満を感じて当然ですが、感情的にならず、次のように冷静かつはっきりと理由を伝えることが大切です。
| 解約の伝え方 |
「これまで、お世話になりました。ただ、現在の経営状況を考えると、より積極的に節税や資金繰りのアドバイスをいただける税理士と契約することが必要だと判断いたしました。そのため、今期をもって顧問契約を終了させていただきます。」 |
|---|
税理士に非がある場合での解約の伝え方のポイントは、以下の通りです。
- 相手を非難する言い方は避け、あくまで「会社の方針として変更を決定した」という形にする。
- 感情的にならず、事実を簡潔に伝える。
- 「今後の成長を考えて変更する」という前向きな理由を伝えると、角が立ちにくくなる。
ミスが多い税理士はどう対処すべき?変更してのリスク回避も検討しよう!
「うちの税理士、よくミスをするけど、これって普通なのか?」と思ったことはありませんか? 経理や税務に関するミスは、企業経営に大きな影響を与える可能性があります。 決算書の誤り、税務申告の不備、税務調査時の指摘事項など、税 […]
今後を見据えた税理士変更の場合の伝え方
「特に不満があるわけではないが、事業の成長に合わせて、より適した税理士を探したい」ということもありませんか。
たとえば、以下のようなケースです。
- 会社の規模が大きくなり、より高度な税務アドバイスが必要になった
- 海外取引が増え、国際税務に強い税理士に変更したい
- IPO(株式上場)を視野に入れているため、上場準備に詳しい税理士と契約したい
このような場合、次の言い方のように、相手のプライドを傷つけず、円満に契約を終了することが重要です。
| 解約の伝え方 |
「長年お世話になり、心より感謝しております。このたび、事業の拡大に伴い、より専門的な税務サポートを受ける必要が出てまいりました。そのため、次の決算をもって、新しい税理士にお願いすることを決定いたしました。」 |
|---|
自社の今後の成長を見据えた上での税理士解約の伝え方のポイントは、以下の通りです。
- 「事業の成長に伴う変更」という前向きな理由を伝える。
- 「お世話になったことへの感謝」を忘れずに伝える。
- できるだけ早めに伝え、引き継ぎがスムーズにできるように配慮する。
長年契約している税理士に対する配慮ある断り方
以下のケースのように、長い間、税理士とのつきあいがある経営者の方もいるのではないでしょうか。
- 先代の社長からの付き合いがあり、長年顧問契約をしている
- 地域の商工会や税理士会などで何度も顔を合わせる関係にある
- 担当税理士が高齢になり、業務に支障が出始めている
長年付き合いのある税理士に対して、「もう契約しません」と突然伝えるのは、やはり気まずいものです。
特に、地元の小規模な会計事務所などでは、税理士との関係が長く続いていることもあり、慎重な言い方をしたいところです。
このような場合、いきなり契約解除を伝えるのではなく、次のように段階的に伝えることが理想です。
| 解約の伝え方 |
「これまで長年にわたりご指導いただき、心から感謝しております。事業の方向性が変わる中で、今後の経営について新しい視点を取り入れたいと考え、一度セカンドオピニオンを受けてみることにしました。まだ正式な決定ではありませんが、今後の方針を検討する中で、ご相談させていただくこともあるかと思います。」 |
|---|
長年、契約していた税理士に解約を伝える時の考え方のポイントは、以下の通りです。
- いきなり解約を伝えるのではなく、「セカンドオピニオンを受ける」とワンクッション置く。
- 長年の関係性への感謝をしっかり伝える。
- 「今後も相談させていただく可能性がある」と伝え、関係を完全に断ち切らない雰囲気を匂わせてフェードアウトする。
親戚・知人の税理士との契約解消の方法
以下のように、親戚や知人の税理士と契約しているケースもあるのではないでしょうか。
- 親戚の税理士に頼んでいるが、対応が悪い
- 知人の紹介で契約したが、思ったようなサービスを受けられない
- 「身内だから」と甘えられ、業務が雑になっている
身内の税理士を解約する場合、単なるビジネスの関係以上に、人間関係のトラブルを避けることが重要になります。
このようなケースでは、以下のように「身内だからこそ、きちんとした関係を築きたい」と伝えることがポイントです。
| 解約の伝え方 |
「これまでお世話になり、本当に感謝しています。ただ、会社の成長を考えたとき、より客観的なアドバイスを受けられる税理士にお願いしたいと思うようになりました。決して不満があるわけではなく、ビジネス上の判断としてご理解いただけると幸いです。」 |
|---|
親戚や知人である税理士を解約する時のポイントは、以下の通りです。
- 「不満がある」とは言わず、あくまで「ビジネス上の判断」として伝える。
- 感謝の言葉を忘れずに伝える。
- もし関係を完全に断ち切りたくない場合は、「何かあったらまた相談させてください」と伝えておく。
そもそも選び方が悪いから税理士変更のトラブルが起こる
税理士変更時のトラブルの多くは、「悪い税理士に当たったから」と考えがちですが、実は最初の税理士選びの段階でミスをしていたことが原因で発生するケースがほとんどです。
多くの経営者は、税理士を選ぶ際に次のような安易な基準で決めてしまいます。
- 「知人の紹介だから信頼できると思った」
- 「ネット検索で上位にあったから良い事務所だと思った」
- 「税理士紹介サービスに任せたら、すぐ見つかって安心した」
しかし、こうした方法では「自社に合った税理士」と出会える可能性は極めて低く、結果として後々トラブルが発生しやすくなります。
皆さんは、お腹が痛いのに眼科を予約するなんてことがあるでしょうか?
つまり、自社が抱える問題を解決するのにふさわしくない税理士を選ぶと、失敗してしまうのです。
以下からは、税理士選びでの問題について詳しく見ていきましょう。
「お腹が痛いなら眼科には行かない」=自社の課題に合わない税理士を選ぶと失敗する
税理士は「どこでも同じ」ではありません。
事業のフェーズや経営課題によって、適した専門家が異なるため、間違った選び方をすると後で後悔することになります。
たとえば、医者にかかるときのことを考えてみましょう。
| お腹が痛いのに、眼科に行っても治療は受けられない 逆に、目の病気なのに内科に行っても、正しい診断は受けられない |
同じように、自社の課題に合わない税理士を選んでしまうと、必要なサポートを受けられず、結果的に税理士変更を検討することになるのです。
自社の課題と向き合わずに、適当に税理士を選んでしまうと、以下のようなトラブルが起きてしまいます。
- 資金が限られている創業期の企業が、大手税理士事務所に依頼した結果、基本料金が高い割にグロースのためのアドバイスなども大して受けられず、費用ばかりかかってしまった
- 製造業の企業が、飲食業に特化した税理士を選び、減価償却などにきちんとした対応をしてもらえず、余計な税金を払ってしまった
- 海外取引が増えてきたのに、国際税務に対応できない税理士を選び、輸出入に関する税務や外国税額控除の処理ができず、余計な税負担が起きてしまった
このように、税理士には得意分野があるため、自社の事業やフェーズに合った税理士を選ぶことが何よりも重要なのです。
トラブルを起こさず後悔しない、本当の税理士の選び方
税理士変更時のトラブルの多くは、最初の税理士選びを間違えたことが原因です。
つまり、最初から正しく税理士を選べば、トラブルを防ぐことができ、税理士を何度も変える必要もなくなります。
トラブルを起こさず後悔しない税理士を選ぶ際には次の点を意識しましょう。
- 価格だけで選ぶと「安かろう悪かろう」になるからやめる
- 業種特化・経営アドバイスができる税理士を選ぶ
- 税理士変更時に「セカンドオピニオン」を活用する
次の記事で自社に合った税理士の選び方や見極め基準について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
※「自社と相性の良い税理士の選び方や見極めるポイントを解説」の内部リンク
THE CXOでより良い税理士を見つけ、トラブルなく変更を進めよう!
今回は、税理士変更にまつわるトラブルや、トラブル自体の回避方法について詳しく解説しました。
書類が返却されない、契約解除時に不当な請求をされる、新しい税理士との相性が合わない、といった問題は、多くの場合、最初の税理士選びを誤ったことが原因です。
「安いから」「紹介されたから」といった安易な理由で税理士を選ぶのではなく、事業のフェーズや課題に合った税理士を見つけることが、税理士変更でトラブルに巻き込まれず、後悔しない最大のポイントになります。
THE CXOでは、単なる税理士紹介はせず、企業の成長を支える経営パートナーとしての税理士とマッチングできます。
スムーズな変更のサポートも受けられるため、トラブルを避けて、安心して税理士を切り替えたい方に最適です。
「税理士を変えたいけど、どう進めればいいのかわからない…」
「経営を本気で支えてくれる税理士と出会いたい!」
そうお考えの方は、ぜひTHE CXOを活用して、自社にぴったりの税理士を見つけてください!