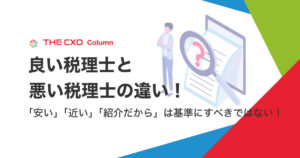ミスが多い税理士はどう対処すべき?変更してのリスク回避も検討しよう!
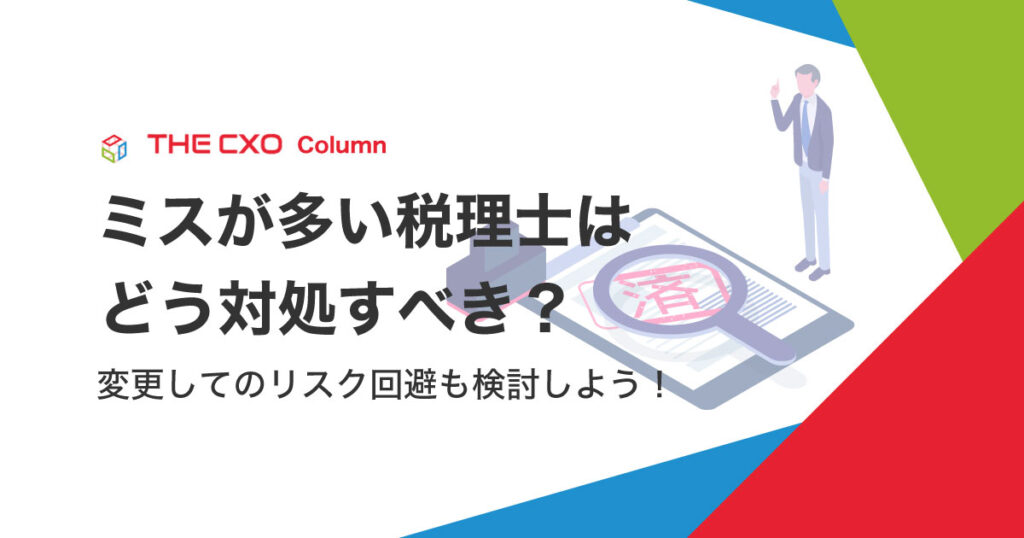
「うちの税理士、よくミスをするけど、これって普通なのか?」と思ったことはありませんか?
経理や税務に関するミスは、企業経営に大きな影響を与える可能性があります。
決算書の誤り、税務申告の不備、税務調査時の指摘事項など、税理士のミスが原因で起こる問題は少なくありません。
そもそも、税務に関する業務は「資格がなくても自分でやることは許されている」一方で、他人の税務を有償で代行・指導することは税理士法で禁止されています。
「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」と規定し、税理士又は税理士法人でない者が、原則として「税理士業務」を行うことを禁止しています。
引用元:国税庁「6税理士法違反行為」
それほど税務の専門性は重要視されており、ミスが許されない仕事だといえるでしょう。
もし、頻繁にミスをする税理士を雇っているのであれば、プロ意識が欠けている可能性があるため、早めに見直すべきです。
この記事では、ミスが多い税理士を放置するとどのような問題が起こるのか、そして、税理士を変更することでどのようなリスクを回避できるのかを詳しく解説します。
株式会社カタリスタ 代表取締役
THE CXO 株式会社 代表取締役
飯島 彰仁(いいじま あきひと)
Iijima Akihito
経営計画コンサルタント、中小企業の社外CXO。大手会計事務所元代表取締役社長として、同社を年商22億円、従業員数447名の規模にまで成長させた実績を持つ。
これまで3,000社以上の中小企業に対し、財務やマーケティングを通じた経営向上に貢献。
その中で、中小企業の成長のためには、単なる税務処理を超え、経営に深く関与する税理士が必要不可欠であることを痛感。
その経験をもとに、税理士が真の価値を発揮する「社外CXOメソッド」を開発。累計300人以上の税理士に伝授し、「税務の枠を超え、中小企業のあらゆる相談に乗れるパートナー」を養成。
指導した税理士達からは、顧問先の売上向上、利益向上、V字回復や事業改善など成功報告が続々と寄せられている。

- 1. 結論:ミスが多い税理士は早めに変更を検討しましょう
- 2. ミスが多い税理士を放置することによる5つの悪影響
- 2.1. 追徴課税などの税務トラブル
- 2.2. データの誤りによる経営判断ミス
- 2.3. 金融機関の信用低下による融資条件の悪化
- 2.4. 税務調査が長引くなど、時間と労力のロスの増大
- 2.5. 経営者のストレスとモチベーションダウン
- 3. 「ミスが多い税理士でも仕方ない」では済まされない!
- 3.1. 税理士には「注意義務」や「説明義務」などの法律上の責任がある
- 3.1.1. 税理士が果たすべき重要な10の注意義務
- 4. ミスを連発する税理士への対応はどうすべき?
- 4.1. ミスの改善要求
- 4.2. ミスの損害賠償請求
- 4.3. 税理士の切り替え
- 5. ミスが多い税理士なら「変更する」など前向きな行動をとろう!
- 6. 税理士のミスはなぜ起こる?
- 6.1. 税理士にも得意分野と苦手分野があるから
- 6.2. 企業の成長ステージや業態ごとに合う税理士が違うから
- 6.3. 低価格やブランド名で選んでしまいやすいから
- 7. ミスの多い税理士を切り替える手順はこんなに簡単
- 7.1. 【手順1】自社の課題を洗い出し、現税理士に不満を伝える
- 7.2. 【手順2】セカンドオピニオンやお試し契約で新しい税理士を選定する
- 7.2.1. 新しい税理士と面談する時のチェックポイント5選!
- 7.3. 【手順3】ミスを防ぐため、引き継ぎの主導権を握り、自社と新しい税理士で管理する
- 7.4. 【手順4】必要なデータをすべて回収したうえで、現在のミスが多い税理士と契約解消する
- 8. ミスが多い税理士は遠慮なく乗り換えるべき!
結論:ミスが多い税理士は早めに変更を検討しましょう
税理士の仕事は、単なる計算作業ではなく、企業の経営を支えるものです。
しかし、税理士のミスが原因で、以下のような問題が起こることがあります。
- 税務申告の誤りによるペナルティ(追徴課税や延滞税)
- 決算書のミスで融資審査に落ちる
- 税務調査での指摘が増える
- 財務管理のズレによる経営判断ミス
- 経営者のストレスが増える
こうした問題が続くと、会社の信用が低下し、経営そのものに悪影響を及ぼします。
さらに、税理士には「注意義務」や「説明義務」といった責任が法律上定められています。
したがって、頻繁にミスをする税理士は、そもそも職務を果たせていない可能性があるのです。
もし、現在の税理士に不満を感じている場合、すぐに変更を検討しましょう。
税理士の切り替えは決して難しいものではなく、きちんと準備をすればスムーズに移行できます。
ミスが多い税理士を放置することによる5つの悪影響
税理士のミスを「仕方ない」と放置すると、以下のような、会社にとって深刻な5つのリスクが起こります。
- 追徴課税などの税務トラブル
- 経営データの誤りによる経営判断ミス
- 金融機関の信用低下による融資条件の悪化
- 税務調査が長引くなど、時間と労力のロスが増大
- 経営者のストレスとモチベーションダウン
税務や会計のミスは、見過ごせば見過ごすほど大きな問題へと発展し、最悪の場合、経営そのものが危うくなることもあるのです。
ここからは、ミスが多い税理士をそのままにしておくことで生じる5つの悪影響をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
追徴課税などの税務トラブル
税理士のミスによって最も直接的な影響を受けるのが、税務申告の誤りによる追加税負担です。
たとえば、以下のような間違いがあると、後から税務署の指摘を受け、追徴課税(追加で納める税金)を支払わなければなりません。
- 売上や経費の計上ミス
- 消費税の計算ミス
他にも、適用できる税制優遇を知らなかったことによる納税額の増加があった場合も、会社の資産にとってダメージとなるでしょう。
特に税務調査でミスが発覚した場合、延滞税や重加算税などのペナルティが発生し、納税負担が大幅に増加するリスクがあります。
もし、会社の資金繰りが厳しい状況で税務署から多額の追徴課税を求められると、最悪の場合、資金ショートにつながる可能性もあります。
データの誤りによる経営判断ミス
税務や会計の数字は、経営判断の基礎となるものです。
もし、税務や会計の数字が間違っていたら、以下のように間違った経営判断をしてしまう可能性が高くなります。
- 利益が出ていると思っていたのに、実は赤字だった
- キャッシュフローが健全だと思っていたのに、資金繰りが悪化していた
- 事業拡大のタイミングを誤り、大きな損失を出してしまった
税理士のミスによって、正しい財務状況を把握できないと、経営戦略そのものが狂ってしまうのです。
金融機関の信用低下による融資条件の悪化
銀行や金融機関は、融資の審査の際に「会社の決算書」をもとに審査を行います。
しかし、税理士のミスによって決算書の数字が不正確だった場合、融資の審査で以下のような悪影響を及ぼすことがあります。
- 銀行から「この決算書の数字が信用できない」と言われる
- 利益がきちんと計上されていないため、本来受けられるはずの融資額が減る
- 税務申告のミスが過去に何度もあると、金融機関からの信用が落ちる
税理士が多くミスしたことによって、事業拡大のための資金調達が難しくなるだけでなく、経営が厳しくなったときに資金の支援を受けられなくなるリスクも高まってしまうのです。
税務調査が長引くなど、時間と労力のロスの増大
税理士のミスが続くと、税務調査が入ったときに問題が起こります。
税務調査では、会社の申告内容に問題がないかどうかを税務署がチェックしますが、ミスが多い税理士に任せていると、申告内容に不備が多くなり、調査が長引く原因になります。
税務調査が長引くと、以下のようなデメリットがあります。
- 税務署への対応に多くの時間を取られる
- 追加の資料提出や説明が求められ、経営者や経理担当者の負担が増える
- 最悪の場合、罰則や追徴課税が起こる
そもそも税務調査を起こさないために税理士がいるのに、こうした問題に対処しなければならないのであれば、税理士を雇った意味などなくなってしまい、経営者は本業に集中できなくなってしまいます。
経営者のストレスとモチベーションダウン
ミスが多い税理士を使い続けることで、経営者のストレスが増加し、モチベーションが低下するという問題もあります。
税理士に対する不満が積もると、以下のようなことでストレスが溜まりがちです。
- 「この税理士、本当に大丈夫なのか?」と不安になり、常に気を使うことになる
- 「もっと良い税理士にしておけば…」と後悔する
- そもそも「税理士に任せておけば安心」という状態にならず、余計な手間や負担が増える
経営者としては、本業に集中し、会社の成長を目指すことが最も重要です。
そのために決して安くはない費用をかけて、外部からわざわざ税理士を雇っているはず。
税理士のミスによって経営者の時間とエネルギーが奪われるのは、大きな損失といえます。
「ミスが多い税理士でも仕方ない」では済まされない!
税理士がミスをすることは、単なる「うっかり」では済まされません。
税務や財務の管理は、企業経営に直結する重要な業務だからです。
特に、税理士には「注意義務」や「説明義務」などの法律上の責任があります。
義務を果たさない場合、会社に損害を与えることになり、税理士自身が業務停止や懲戒処分を受ける可能性があります。
すると「税理士がミスをしても仕方がない」と考えるのがいかに危険かが分かるでしょう。
税理士には「注意義務」や「説明義務」などの法律上の責任がある
税理士のミスによって企業が損害を受けた場合、法的に責任を問うことが可能です。
主に、以下の2つの法的責任が適用されます。
| 責任の種類 |
内容 |
|---|---|
| 債務不履行責任(契約違反) | 税理士と企業の顧問契約に基づき、税理士が適切な業務を行う義務を果たさなかった場合に発生する責任 |
| 不法行為責任(法律違反) | 税理士が明らかに間違った税務処理を行い、企業に損害を与えた場合に発生する責任 |
税理士が果たすべき重要な10の注意義務
税理士は、単に計算をするだけでなく、正しい税務処理を行うため、以下のようにさまざまな注意義務を負っています。
| 義務の種類 |
内容 |
|---|---|
| 説明助言義務 | 企業に対して税務や会計処理の方法を分かりやすく説明し、有益不利益問わず適切なアドバイスをする義務 |
| 有利選択義務 | 税務申告の際、企業にとって最も有利な方法を選択し、提案する義務 |
| 不適正処理是正義務 | 税務処理のミスを発見した場合、速やかに修正し、企業に適切な対応を求める義務 |
| 前提事実の確認義務 | 税務申告を行う前に、企業の財務状況や会計処理が正確であるかをチェックする義務 |
| 税法以外の法令調査義務 | 税務だけでなく、会社法や労働法など関連法規についても調査し、企業に適切な助言を行う義務 |
| 積極調査義務 | 企業から提供された資料だけに頼るのではなく、不明点があれば積極的に調査し、正確な税務処理を行う義務 |
| 租税立法遵守義務 | 最新の税法や条例を把握し、反することなくそれに基づいた正確な申告を行う義務 |
| 正しく事実認定をする義務 | 企業の会計処理において、税法を理解し、事実を正確に把握し、税法に従い誤った認識や解釈で申告を行わないようにする義務 |
| 不正発見義務 | 企業の税務処理において、役員や従業員などによる不正や脱税の可能性がある場合、それを見逃さず適切に指摘する義務 |
| 第三者に対する義務 | 企業の取引先や金融機関など、税務に関わる第三者にも正しい情報を提供する義務 |
このように、税理士には多くの責任があり、ミスをすること自体が「職務を果たしていない」ことに直結するのです。
ミスを連発する税理士への対応はどうすべき?
税理士が繰り返しミスをする場合、それは笑って済ませるような「うっかりミス」とはいえず、職務を放棄している状態といえます。
本来、税理士は経営者の重要なパートナーであり、正確な税務処理としっかりしたアドバイスを提供する責任があります。
しかし、その責任を果たせていない税理士と契約を続けることは、会社にとって大きなリスクでしかありません。
「では、ミスを頻発する税理士をどうするべきか?」と考えたときに取れる行動は、以下の通りです。
- ミスの改善要求
- ミスの損害賠償請求
- 税理士の切り替え
ここからは、税理士変更を視野に入れた、ミスが多い税理士に出会ってしまった時の考え方について説明します。
ミスの改善要求
税理士がミスをした場合、すぐに契約を切るのではなく、まずは改善を求めることも選択肢の一つです。
たとえば、以下の3点を確認してみて、対応次第で継続の判断をしましょう。
| 対応ポイント |
内容 |
確認すべき点 |
|---|---|---|
| ミスの原因を詳しく説明してもらう | なぜミスが発生したのか、今後どう防ぐのかを具体的に説明してもらう。 | 言い訳ではなく、再発防止の具体策を提示できるか? |
| チェック体制の見直しを依頼する | 計算ミスや提出遅れなどのミスを防ぐ仕組みを強化してもらう。 | 同じミスが起こらないよう、仕組みを改善する意思があるか? |
| 対応スピードやコミュニケーションを改善してもらう | 連絡の遅れや報告の不備を解消し、スムーズに対応できるようにする。 | 返信が遅すぎる、説明が雑すぎるといった問題点を改善できるか? |
このように、税理士が誠実に対応し、改善の意思を示せば継続を検討できます。
しかし、改善を頼んでも適当な言い訳ばかりだったり、改善の姿勢が見られない場合は、速やかに次の選択肢(損害賠償請求・税理士変更)を検討すべきです。
ミスの損害賠償請求
税理士が重大なミスをした場合、損害賠償を請求できる可能性があります。
しかし、法的手続きを取るには多くの労力と時間が必要になります。
たとえば、税理士のミスによって企業が損害を受けた場合、裁判や示談交渉を行うことができますが、以下のような問題点が起こります。
- 証拠を揃えるのが大変(税理士のミスによる損害を立証するためには、契約書・過去の申告書・会計データなどの証拠を揃える必要がある)
- 裁判に時間がかかる(法的手続きには最低でも数ヶ月~1年以上かかることが多い)
- 勝訴しても実際に賠償金を回収できるとは限らない(税理士が支払い能力を持っているとは限らない)
このように、損害賠償を請求すること自体は可能ながら、現実的に解決までのハードルが高いのが実情です。
税理士の切り替え
税理士のミスを指摘し、法的責任を追及するよりも、もっと重要なのは、経営を安定させるために迅速にベストな税理士へ切り替えることです。
たとえば、税務申告のミスが発覚した際に「過去の税理士が悪かった」と責めても、すでに発生した問題は解決しません。
それよりも、「今後、同じミスをしないようにするにはどうするか?」を考え、信頼できる税理士を見つけることが最優先です。
また、腹が立って、問題のある税理士を矯正、改善したいと感じ、既に支払ってしまった顧問料などの回収に固執してしまうことがあるかもしれません。
しかし、衝動的に行動してしまうと以下のような悪影響が出ることも考えられます。
- 申告ミスが続き、税務調査で追徴課税を受けるリスクが高まる
- 金融機関の信用を失い、融資条件が悪化する可能性がある
- 軸のあるアドバイスを受けられず、利益を圧迫する無駄な税負担が起こる
経営において大事なのは、「過去のミスをどう責めるか」ではなく、「未来のトラブルをどう防ぐか」です。
そのためには、ミスを繰り返す税理士にこだわるよりも、速やかに新しい税理士へ切り替えるのが最善策といえます。
ミスが多い税理士なら「変更する」など前向きな行動をとろう!
「税理士を変えるのは手間がかかるし、面倒だ…」と思うかもしれません。
しかし、ここまででミスを頻発する税理士に任せ続ける方が、長期的にはもっと面倒なことになるということがわかりました。
ミスが多い税理士に不満を持ったら、すぐに税理士を変更することで、会社の未来を大きく変えられる可能性があるのです。
税理士のミスはなぜ起こる?
税理士のミスが起こる理由は、単なる「不注意」ではなく、構造的な問題や、税理士ごとの適性の違いが原因となっていることが多いです。
税理士がミスをするのは、以下のような理由だと考えられます。
- 税理士にも得意分野と苦手分野があるから
- 企業の業態や成長ステージごとに合う税理士が違うから
- 低価格やブランド名で選んでしまいやすいから
「税理士なんだから、誰でも同じように仕事ができる」と考えるのは大きな間違いです。
なぜ税理士のミスが起こるのか、その理由を以下から詳しく解説していきます。
税理士にも得意分野と苦手分野があるから
税理士と一言でいっても、全員が同じスキルを持っているわけではありません。
税理士にはタイプがあり、それぞれに得意な分野と苦手な分野が存在します。
たとえば以下のように、税理士によって得意な業務は異なります。
| 税理士のタイプ |
得意な業務 |
苦手な業務 |
|---|---|---|
| 記帳代行型 | 経理作業、仕訳入力 | 経営アドバイス、税務調査対応 |
| 節税対策型 | 節税対策、法人税・所得税の最適化 | 日常の細かい会計業務 |
| 資金調達・融資型 | 銀行融資、補助金申請のサポート | 実務の細かい記帳作業 |
| 税務調査対応型 | 税務調査時の交渉、税務署対応 | 通常の経理・会計業務 |
このように、税理士には専門分野があるため、自社が属すフェーズや業界における税務に精通した税理士でなければ、ミスが起こりやすくなるのです。
たとえば、日々の経理処理をきちんとやってほしいのに、「税務調査専門」の税理士に依頼してしまうと、日常業務のサポートが手薄になり、経理ミスが増える可能性があります。
また、記帳代行をメインとする税理士に節税対策を相談しても、効果的な提案が得られないことがあります。
そのため、税理士を選ぶ際には、「この人は何が得意なのか?」を見極めることが大切です。
企業の成長ステージや業態ごとに合う税理士が違うから
企業の規模や成長段階によっても、適した税理士のタイプが異なります。
たとえば、創業直後の企業と、上場を目指している企業では、求める税理士のスキルが以下のように全く違います。
| 企業の成長ステージ |
適した税理士のタイプ |
|---|---|
| 創業期(設立~3年) | 記帳代行、融資支援が得意な税理士 |
| 成長期(3年~10年) | 節税・財務戦略に強い税理士 |
| 安定期(10年以上) | M&A・事業承継・資産管理に詳しい税理士 |
| 上場準備企業 | IPO(上場準備)に強い税理士 |
たとえば、創業期の企業は、資金繰りや融資のサポートが得意な税理士を選ぶべきですが、すでに事業が安定している企業が「融資専門の税理士」を雇っても、あまり役に立たない可能性があります。
また、以下のように業種によっても適した税理士が異なります。
| 業種 |
適した税理士の特徴 |
|---|---|
| IT・スタートアップ | クラウド会計に強い、資金調達の経験が豊富 |
| 飲食業 | 原価管理や補助金に詳しい |
| 製造業 | 固定資産管理や設備投資に強い |
| 医療・介護 | 医療法人・社会福祉法人に精通している |
適した税理士を選ばないと、業界特有のルールや助成金制度を把握していないため、ミスが増える可能性があります。
低価格やブランド名で選んでしまいやすいから
税理士を選ぶ際に「料金が安いから」「有名な事務所だから」といった理由で決めると、実務の質が低くなることがあります。
たとえば、料金が安すぎる税理士事務所には、以下のようなリスクがあります。
- 1人の税理士が大量の顧問先を抱えており、細かいチェックができない
- 税務相談に時間をかけられず、最低限の業務しか対応してくれない
- ミスをしても責任を取らないどころか、その質問自体がずっと放置される可能性がある
また、「ブランド名が有名だから安心」と思って大手の税理士事務所を選んでも、担当者が新人だったり、十分なサポートを受けられなかったりするケースもあります。
そのため、税理士を選ぶ際には、価格や知名度だけで判断せず、「実際に対応する人がどんな税理士なのか」を見極めることが重要です。
ミスの多い税理士を切り替える手順はこんなに簡単
「税理士を変えたいけど、手続きが面倒くさそう」と思っている方は多いでしょう。
しかし実際には、以下のように税理士の切り替え作業は、すべきことを整理して進めれば意外とシンプルです。
- 【手順1】自社の課題を洗い出し、現税理士に不満を伝える
- 【手順2】セカンドオピニオンやお試し契約で新しい税理士を選定する
- 【手順3】ミスを防ぐため、引き継ぎの主導権を握り、自社で管理する
- 【手順4】必要なデータをすべて回収したうえで、現在のミスが多い税理士と契約解消する
しっかりと下準備をすれば、スムーズに新しい税理士へ移行できます。
以下からは、各手順を詳しく見ていきましょう。
【手順1】自社の課題を洗い出し、現税理士に不満を伝える
効率を重視する場合、【手順2】にある、新しい税理士を探す作業などと同時進行で、今の税理士に「改善してほしい点」を具体的に伝えましょう。
顧問契約を解消する前に、一度フィードバックを行うことで、状況が改善するかもしれないからです。
自分の不満などを明らかにした上で、たとえば以下のようなことを伝えてみてはいかがでしょうか。
- 「税務申告のミスが多いので、チェック体制を強化してほしい」
- 「節税対策の提案がないので、具体的なアドバイスをお願いしたい」
- 「連絡が遅いので、レスポンスを早めてもらえないか?」
もし、こうした要望に対して改善が見られない場合は、切り替えを決断すべきです。
【手順2】セカンドオピニオンやお試し契約で新しい税理士を選定する
いきなり税理士を変更するのではなく、まずはセカンドオピニオン(他の税理士の意見を聞くこと)を活用するのがポイントです。
たとえば、現在の税理士に以下のような不満がある場合、別の税理士に相談してみると、改善の余地があるかどうかを確認できます。
- 税務申告のミスが頻発する
- 経営上の提案が少ない
- 対応が遅く、相談しても後回しにされる
セカンドオピニオンを利用することで、今の税理士と比較し、本当に変更が必要かどうかを見極められるのです。
また、新しい税理士を選ぶ際には、お試し契約を活用するのもおすすめです。
「いきなり本契約」ではなく、「スポット相談」や「短期契約」を利用して相性を確認しましょう。
新しい税理士と面談する時のチェックポイント5選!
税理士を変更する前に、現状の不満を明らかにしておくことも重要です。
すると、新しい税理士と面談したときに、何を聞けばいいのかがはっきりします。
たとえば、初回面談では次のような点を確認すると、相手との相性もわかりやすくなり、税理士選びに失敗しにくくなるでしょう。
| チェック項目 |
確認すべきポイント |
理由 |
|---|---|---|
| レスポンスは早く、対応は丁寧か? | メールや電話の返信速度、対応の丁寧さをチェック | 返信が遅い税理士は、契約後も対応が遅れ、重要な税務対応が遅延するリスクがあるから |
| 経営改善につながる具体的な提案があるか? | 記帳代行だけでなく、節税・資金調達・経営戦略のサポートが可能か確認 | 企業の成長を支援する税理士であれば、単なる申告業務以上の価値を提供できるから |
| ミスを未然に防ぐ意識と仕組みを持っているか? | 過去のミス事例やその対応策について質問 | ミスを繰り返さない仕組みがあるかを確認することで、安心して業務を任せられるか判断できるから |
| デジタル対応(クラウド会計など)は進んでいるか? | クラウド会計やITツールの活用状況をチェック | ITを活用できる税理士なら、経理業務の効率化が進み、手間を削減できるから |
| 顧問料とサービス内容のバランスは納得いくか? | 料金と提供サービスの内容を比較し、適正かどうか判断 | 安さだけで選ぶと、質の低いサービスになりがちだから。ちゃんとサポートを受けられるか確認すべき |
このように、自分が税理士に求めることを具体的にリスト化してから、本人に質問を直接ぶつけることで、新しい税理士を選ぶ上での失敗を防げます。
【手順3】ミスを防ぐため、引き継ぎの主導権を握り、自社と新しい税理士で管理する
税理士を変更するときは、いきなり契約を切るのではなく、準備を整えてから進めることが大切です。
特に、ミスの多い税理士に引き継ぎを任せるのは危険なので、こちらが主導して必要なデータを管理し、新しい税理士がスムーズに対応できるようにしておきましょう。
以下の3つのポイントを押さえておけば、問題を最小限に抑えられます。
| ポイント |
内容 |
理由 |
|---|---|---|
| 決算直前に税理士を変えない | 決算が終わり、落ち着いたタイミングで変更する | 決算直前は業務が立て込むため。決算前に税理士を変更すると作業が混乱し、ミスが発生しやすい |
| 会計データを自社で管理する | クラウド会計ソフトを導入し、自社でもデータを管理できるようにする | 旧税理士に依存しない体制を整えることで、データ引き継ぎのトラブルを防げるから |
| 必要書類を事前に受け取る | 過去(直近3年分)の申告書・決算書・会計データなどを確保しておく | 契約解除後に書類を請求すると、後回しにされたり、受け取れなくなる可能性があるため |
このように、税理士に頼らず自社でデータを管理し、必要な書類を確実に確保しておくことで、スムーズな引き継ぎが可能になります。
【手順4】必要なデータをすべて回収したうえで、現在のミスが多い税理士と契約解消する
最後に、今の税理士との契約を正式に解除します。
ただし、契約を切る前には、【手順3】にもあったように必要なデータをすべて回収しておくことが大前提です。
ミスの多い税理士に「あとで送ります」と言われても、確実に受け取れる保証がないためです。
契約解除の際は、次の4つのポイントを押さえておきましょう。
| ポイント |
内容 |
理由 |
|---|---|---|
| 書面で通知し、トラブルを防ぐ | 口頭だけでなく、書面で契約解除を伝える。 | 口約束だと「聞いていない」と言われる可能性があるため、証拠を残す。 |
| 回収書類に抜け漏れがないか最終チェックし、確実に受け取る | 決算書・申告書・会計データなどをすべて最終確認し、事前に回収する。 | 契約を解除した後では、後回しにされることがある。解約前に確実に受け取っておくことが重要。 |
| 引き継ぎを終えてから契約解除を実行する | 新しい税理士がしっかりと業務を引き継げる状態にしてから解約する。 | 途中で税理士がいなくなると、業務に支障が出るため。 |
| 未払いの顧問料がないか確認する | 未払い分がある場合は、解約前に清算する。 | 未払いがあると、税理士側が書類を渡さないケースがある。 |
税理士の契約は、基本的に「1ヶ月前までに通知すれば解約できる」ケースが多いですが、事前に契約内容を確認しておきましょう。
ミスが多い税理士は遠慮なく乗り換えるべき!
今回は、ミスが多い税理士を放置すると、どれほどの悪影響があるのか?について詳しく解説してきました。
税理士が繰り返しミスをする場合、それは単なる「うっかり」ではなく、職務放棄やスキル不足が原因である可能性が高いです。
ミスの多い税理士とそのまま契約を続けることで、会社の経営に深刻な損害を与えるリスクが高まります。
たとえば、税務申告のミスによる追徴課税、節税対策不足による余計な税金支払い、融資審査への悪影響などが考えられます。
「税理士を変えるのは面倒」と思うかもしれませんが、放置する方が長期的にリスクが高く、経営に悪影響です。
一方で、優秀な税理士に切り替えれば、節税や資金調達のアドバイスを受けられ、経営の安定につながります。
税理士を変更する際は、セカンドオピニオンを活用し、複数の税理士を比較することが大切です。
もし「今の税理士で本当にいいのか?」と疑問を感じたら、早めに行動し、経営の未来を守りましょう。