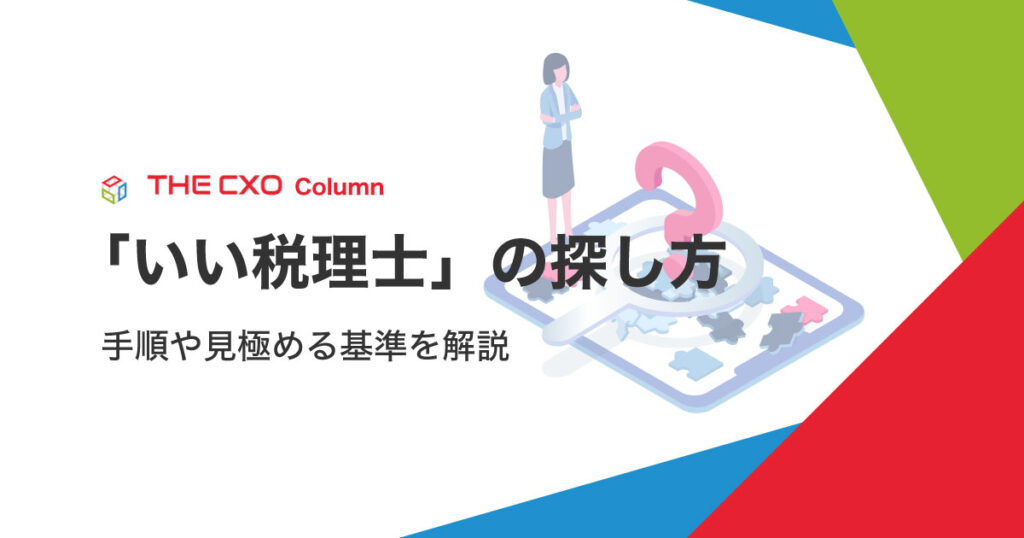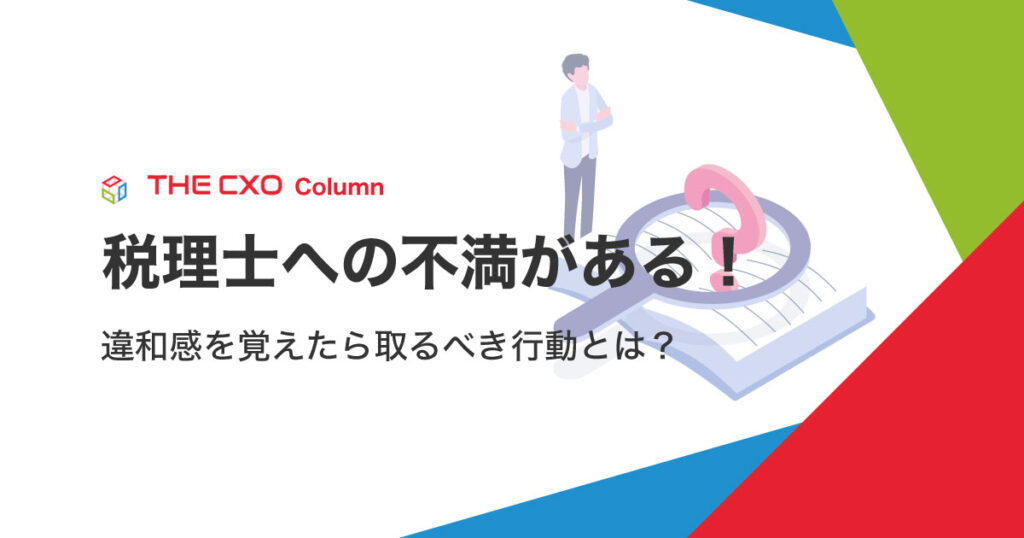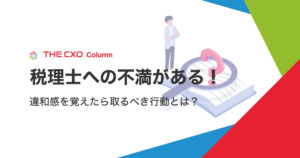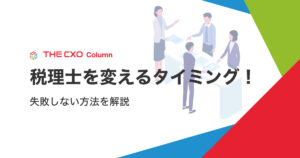自社と相性の良い税理士の選び方や見極めるポイントを解説
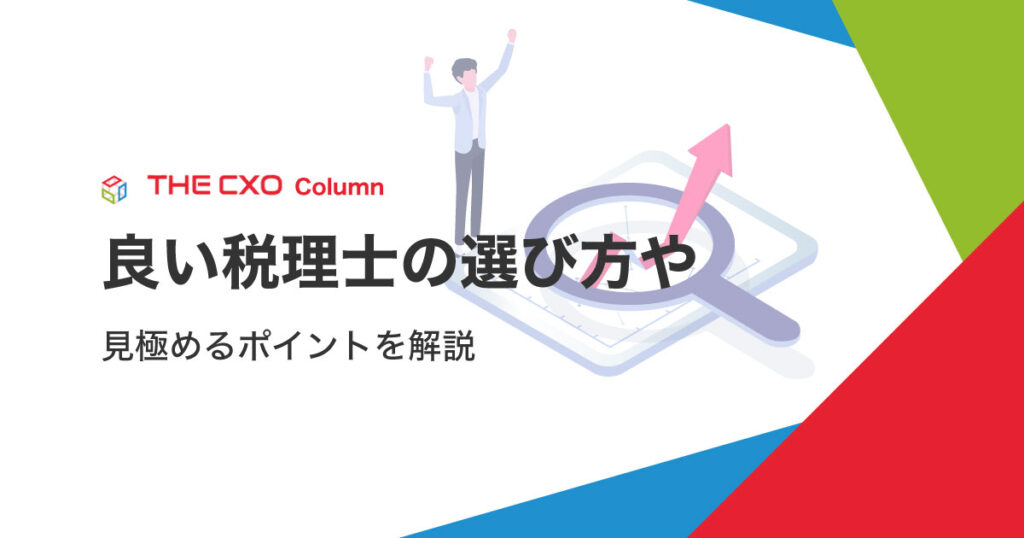
事業を続ける上で、税理士の存在は欠かせません。
しかし、記帳や決算の申告を機械的にこなすだけの税理士に不満を感じている経営者は少なくないでしょう。
税理士の顧問料は、毎月支払っているはずです。
つまり、顧問税理士を抱える限り、会社の資産は毎月、顧問契約料分確実に目減りします。
それなのに、「訪問してくれない」「連絡が遅い」「決算のときしか連絡が来ない」という不満を持たれるような税理士を抱えたままでは、経営の成長を妨げる要因になりかねません。
もし「今の税理士を変えたい」と思っているなら、どのように選び直せばいいのでしょうか?
本記事では、一般的な税理士の選び方がなぜ間違っているのかをはっきりさせ、本当に良い税理士の選び方を解説します。
株式会社カタリスタ 代表取締役
THE CXO 株式会社 代表取締役
飯島 彰仁(いいじま あきひと)
Iijima Akihito
経営計画コンサルタント、中小企業の社外CXO。大手会計事務所元代表取締役社長として、同社を年商22億円、従業員数447名の規模にまで成長させた実績を持つ。
これまで3,000社以上の中小企業に対し、財務やマーケティングを通じた経営向上に貢献。
その中で、中小企業の成長のためには、単なる税務処理を超え、経営に深く関与する税理士が必要不可欠であることを痛感。
その経験をもとに、税理士が真の価値を発揮する「社外CXOメソッド」を開発。累計300人以上の税理士に伝授し、「税務の枠を超え、中小企業のあらゆる相談に乗れるパートナー」を養成。
指導した税理士達からは、顧問先の売上向上、利益向上、V字回復や事業改善など成功報告が続々と寄せられている。

- 1. 一般的に言われている税理士の選び方や基準は間違っている!
- 2. 一般的によく知られている税理士の選び方
- 2.1. 税理士紹介サービスやマッチングサイトで条件に合う税理士を選ぶ
- 2.2. ネット検索で上位に来た税理士事務所を選ぶ
- 2.3. 税理士事務所のブランドや知名度の高さで選ぶ
- 2.4. 知人・友人からの紹介で選ぶ
- 2.5. 銀行や保険会社の紹介で選ぶ
- 2.6. 税理士会からの紹介
- 3. 税理士の選び方は悩みのタイプによって変えよう!悩みタイプ別の最適な選び方
- 3.1. 【今の税理士に不満がある】すぐに税理士を変えてOK!
- 3.1.1. 記帳や決算申告しかやってくれない
- 3.1.2. 経営アドバイスをしてくれない
- 3.1.3. 対応が遅い
- 3.2. 【税理士費用を抑えたい】コスパ重視なら最低限の業務をしてくれるかを見よう
- 3.2.1. 安さで税理士を選ぶと結局損をする
- 3.2.1.1. 月3万の税理士は単なる作業代行、月10万の税理士は利益増の提案
- 3.2.1.2. 税理士費用は「コスト」ではなく「投資」
- 3.3. 【もっと企業成長したい】攻めの経営を支える税理士を選ぼう
- 3.3.1. 売上・利益・キャッシュフローを良い方向に導けるか?
- 3.3.2. 「決算対応」だけでなく、「未来の利益」を生み出せるか?
- 3.3.3. 企業成長のための「財務戦略」を持っているか?
- 3.4. 【初めて税理士を探す】良い税理士を選ぶなら、事務所より「担当税理士」を見よう!
- 3.4.1. 事務所のブランドに惑わされるな!税理士選びは担当税理士が全て!
- 3.4.2. スキル・経験・レスポンスの速さを確認し、相性の合う担当税理士を選ぶべし!
- 3.4.3. 試算表の使い方を聞き、税理士の理解度を見極めよう!
- 3.5. 【税務調査に対応してほしい】税務調査に強い税理士を選ぼう!
- 3.5.1. 税務調査が不安なら、その場しのぎの対応ではなく「経営の見直し」を!
- 4. 税理士の選び方で失敗しないために見極めるべきポイント
- 4.1. ポイント1:実際に担当してくれる税理士と直接話す!
- 4.2. ポイント2:料金ではなく、「提供価値」で選ぶ!
- 4.3. ポイント3:短期間の試用契約を活用し、本契約する価値があるか確かめる!
- 5. 税理士の選び方を間違えると、会社の成長が止まる!今すぐ見直そう
- 6. 税理士を変更したい!次の税理士の選び方に迷ったら?
一般的に言われている税理士の選び方や基準は間違っている!
新しくパートナーの税理士を探す際は、次のような方法で探す方が多いと思います。
- インターネット検索
- 税理士紹介サービス
- 税理士検索サイト・マッチングサービス
- 知人・同業者からの紹介
- 税理士会や商工会議所での紹介
- 金融機関経由の税理士紹介
- セミナー参加で税理士と直接会う
自社に最適な「いい税理士」の探し方とは?手順や見極める基準を解説
税理士を探すとき、多くの方が「ネット検索で上位に出てきた事務所に依頼する」「知人に紹介された税理士をそのまま契約する」といった方法を選ぶのではないでしょうか。 しかし、こうした探し方では本当に自社に合う、いい税理士とは出 […]
こうした方法は一見すると便利で、スタンダードであるように見えますが、実は「自社にとって最適な税理士を選ぶ」という観点から言えば、大きな落とし穴があります。
なぜなら、このような方法では「担当税理士の質」まで見極めることができないからです。
実際に担当する税理士がどんな人なのかわからないままでは、「自社に合わない税理士を選んでしまう」リスクが高まってしまう可能性が高くなります。
最初は良いと思っていても、徐々に税理士への不満が溜まっていき、経営などにも大きな影響を及ぼしてしまいます。
そうならないためにも、「一般的な税理士の選び方には落とし穴があるのだ」という認識はまず持っておきましょう。
一般的によく知られている税理士の選び方
多くの方がやっている一般的な税理士の選び方は、以下の通りです。
- 税理士紹介サービスやマッチングサイトで条件に合う税理士を選ぶ
- ネット検索で上位に出てきた税理士を選ぶ
- 事務所のブランドや知名度の高さで選ぶ
- 知人や友人の紹介で選ぶ
- 銀行や保険会社の紹介で選ぶ
- 税理士会からの紹介で選ぶ
ここからは、税理士選びの方法それぞれと、各方法の落とし穴について解説します。
税理士紹介サービスやマッチングサイトで条件に合う税理士を選ぶ
税理士紹介サービスやマッチングサイトなどは、一見自社にとって最適な税理士を選べる便利な仕組みに思えます。
しかし、ここにはいくつかの問題があるのです。
紹介サービスの多くは、税理士側が紹介手数料を支払う仕組みになっています。
そのため、紹介される税理士が「本当に優秀な税理士かどうか」は保証されません。
むしろ、積極的に紹介料を払える税理士が優先される可能性が高いのです。
つまり、紹介サービスに登録している税理士は、単に売上を伸ばそうと営業に来ているだけです。
「この紹介サービスなら、良い税理士を見つけられるだろう」と思って依頼したら、実際には全く期待外れの税理士が紹介された、というケースは珍しくありません。
たとえば、決算書の作成はするものの、経営のアドバイスを一切行わないため、資金繰りの相談をしても具体的な対策を提案してもらえない税理士を引いてしまう可能性があります。
すると、銀行融資を受ける予定だったにもかかわらず、決算期の直前になってもきちんとした財務分析が行われず、結果的に融資審査に必要な書類の準備が間に合わないといったことが起こってしまうでしょう。
資金調達が遅れれば、新規設備投資の計画がずれ込み、事業拡大のチャンスを逃してしまうかもしれません。
結果として、また税理士を変えることになり、手間もコストも二重にかかってしまうのです。
ネット検索で上位に来た税理士事務所を選ぶ
「税理士 地域名」などで検索し、上位に表示された事務所をそのまま選んでしまうことは、特に避けるべきです。
なぜなら、検索上位に来る税理士事務所の多くは、SEO対策(検索結果の上位表示対策)や広告にお金をかけているからです。
検索で目立つからといって、その事務所の実力が高いとは限りません。
たとえば、広告を出している事務所は、広告費を回収するためにできるだけ多くの顧問契約を取ろうとします。
その結果、一人の税理士に何十社も抱えさせるようノルマを課していることもあり、結局、エンドユーザーである顧客は、手厚いサポートを受けられないこともあるのです。
検索上位の事務所に依頼してしまうと、以下のような問題が起こるかもしれません。
- 契約後、担当税理士と全く連絡が取れない
- 確定申告の時期に対応が遅れる
- 各種申告書などが、税務署への提出期限ギリギリになってしまい、余裕を持った節税対策ができない
さらに、決算期に入っても税理士と細かい打ち合わせができず、税務調査への備えが不十分なまま申告をすることになり、後々、税務署からの指摘を受けて修正申告をさせられる可能性もあります。
すると、本来不要だった追徴課税や延滞税を支払うことになり、結果的にコストが膨らんでしまいます。
逆に、実力のある税理士を慎重に選べば、決算前から利益の見通しを立て、余裕をもって節税対策を進められるはずです。
さらに、銀行融資を見据えた財務管理の提案が受けられれば、資金繰りの改善にもつながるでしょう。
税理士は単なる申告代行ではなく、経営のパートナーとして選ぶべき存在です。
検索結果の順位だけで安易に決めるのではなく、実際に税理士と面談し、ちゃんとしたサポートを受けられるかを見極めることが重要です。
税理士事務所のブランドや知名度の高さで選ぶ
「大手の税理士事務所なら安心だろう」と考えるのも危険です。
大手事務所は、確かに組織としての信頼性はあります。
しかしながら「組織としての価値」は税理士を利用する側には関係のないことです。
税理士を選ぶ側にとって重要なことは、「実際に担当する税理士が誰なのか」です。
事務所のネームバリューだけで選ぶと、以下のような問題が起こることがあります。
- 経験の浅い若手税理士が担当になる
- 一人の税理士が大量のクライアントを抱えているため、対応が遅い
たとえば、決算直前になってようやく試算表を受け取ったものの、担当税理士が数字の意味を深く理解していないというケースです。
経営者側が質問しても「確認します」と繰り返され、結局、重要な税務判断を自分でしなければならない、という状況が起こる可能性があります。
また、税務調査の際に税理士の経験不足が原因で税務署との交渉がうまく進まず、本来不要だった指摘を受けてしまい、結果として余計な税金を支払うことになるかもしれません。
特に、大手税理士事務所では「担当者がコロコロ変わる」というケースがよくあります。
ある年はベテランの税理士だったのに、その方は新規顧客向けのフロント税理士で、翌年は新人に変わり、会社のことを一から説明し直さなければならない、という事態になることも珍しくありません。
もし引き継ぎが不十分だった場合、前年に税理士と話し合って決めた節税対策が、新しい担当者に伝わっておらず適用されなかったというケースも考えられます。
節税対策ができなければ、会社の利益が守れず、予測よりも高額な税負担が発生する可能性があります。
逆に、しっかりと実力のある税理士を確保できれば、経営状況を深く理解し、「この時期に設備投資をすると税務上のメリットがあります」「今期の利益を考慮すると、◯◯の経費を来期に回した方が有利です」 といった具体的なアドバイスが得られるでしょう。
税理士の知識と戦略が、経営の意思決定を大きく左右するのです。
税理士選びでは、事務所の規模やブランドではなく、実際に担当する税理士のスキルや経験をしっかり確認することが不可欠です。
知人・友人からの紹介で選ぶ
「知り合いの紹介だから安心」と思うかもしれませんが、紹介にも落とし穴があります。
知人の会社と自分の会社は業種も規模も違います。
知人にとっては良い税理士でも、自社には合わない可能性があるのです。
たとえば、製造業の友人が「この税理士はいいよ」と紹介してくれたとしても、自社がIT系なら、必要とする知識やサポート内容が全く違うため、期待外れになってしまうことがあります。
具体的には、業界特有の税制を理解していない税理士を選んでしまうと、本来受けられるはずの税制優遇措置を活用できず、余計な税負担が生まれてしまう可能性があります。
たとえば、IT系企業であれば、研究開発費の税額控除やソフトウェア資産の減価償却に関する特例が適用できることがあるでしょう。
しかし、製造業の税務に詳しい税理士が担当した場合、こうした制度について詳しくないため、適用漏れが発生し、本来なら抑えられたはずの税額をそのまま支払うことになってしまうことも考えられます。
また、補助金や助成金の活用に関しても、業界ごとに適用される制度が異なるため、知識がない税理士ではきちんとしたアドバイスを受けられない可能性があります。
たとえば、IT系企業であれば「ものづくり補助金」よりも「IT導入補助金」の方が適している場合が多いですが、製造業向けの税理士ではそのような情報を知らず、不要な制度の利用を勧められてしまうかもしれません。
後から間違った補助金を受け取ってしまったと気づいても、受領してしまった後では基本的に取り消しができません。
さらに、同一事業について別の補助金を申請することはできず、場合によっては補助金の返還を求められることもあります。
結果として、本来受けられたはずの支援を逃し、資金繰りが悪化するリスクが生じる可能性があります。
逆に、業界に精通した税理士を選ぶことができれば、きちんとした節税対策や補助金の活用によって、経費を最適化しながら事業拡大のチャンスを最大限に狙えるでしょう。
税務処理の正確性が向上するだけでなく、資金繰りの安定や投資計画の最適化にもつながるため、長期的に見て大きな経営メリットが得られるのです。
そもそも「まともな税理士」「本当に良い税理士」であれば、自分が不得意な業種や専門外の領域だと感じた場合には、安易に紹介を受けたりはしません。
むしろ、「わたくしの専門領域では貴社の問題を解決するのは難しいため、こういう分野に精通した税理士を別途お探しください」と、きちんと正直に伝えてくれるでしょう。
逆に、どんな業種でも安易に引き受けるような税理士は、結果的に対応が浅く、節税や補助金獲得に失敗するリスクがあります。
良い税理士ほど、自分の専門領域や得意分野を理解しており、明確にできること・できないことを伝えます。
そういう税理士を選ぶことこそが、真に自社にメリットをもたらすのです。
税理士選びでは、「知人が使っているから」という理由だけで決めるのではなく、自社の業種や経営状況に合った税理士を慎重に選ぶことが重要です。
銀行や保険会社の紹介で選ぶ
銀行や保険会社が税理士を紹介してくれるケースもありますが、「金融機関の紹介だから安心」とはならず、注意が必要です。
なぜなら、銀行や保険会社は「自分たちの利益を優先する」からです。
銀行が紹介する税理士は、銀行側の意向をくんで、融資に対して厳しめのアドバイスをすることが多く、結果的に資金繰りの自由度が低くなることもあります。
たとえば、成長資金として融資を受けたいと考えている経営者が、銀行が紹介した税理士の指導を受ける場合を考えてみます。
相談した税理士が「銀行寄り」の税理士だった場合、「借りすぎは危険です」と過度に慎重な方針を取らされ、本来なら投資すべき設備導入を先送りにしてしまうのではないでしょうか。
その結果、事業拡大の機会を逃し、ライバル企業が先に市場を押さえてしまい、売上の伸び悩みにつながってもおかしくはありません。
さらに、実際には融資を受けても問題のない財務状況であったにもかかわらず、銀行の意向を優先した税理士の指導に従った場合はどうなるでしょうか。
おそらく、キャッシュフローの改善策を見逃し、あとあと資金繰りに苦しむことになってしまうはずです。
また、保険会社が紹介する税理士は、保険商品を売ることが目的になっていることもあります。
本来の税務や経営の本質的なアドバイスを期待していたにもかかわらず、定期的なミーティングのたびに「この生命保険に入れば節税になります」といった提案ばかりされ、最終的に不必要な保険契約を結ばされることも考えられるのです。
こうした場合、本業の資金繰りを圧迫し、本来必要だった事業投資のための資金が不足してしまうような事態になってしまう可能性があります。
逆に、銀行や保険会社の意向に左右されない独立系の税理士を選べば、資金調達の選択肢を広げながら、会社の成長にとって本当に必要な投資を見極められます。
たとえば、事業拡大のために融資を受けるべきかどうかを財務状況に基づいて冷静に判断し、きちんとした資金計画が立てられれば、成長のタイミングを逃さず、利益を最大化できるはず。
税理士を選ぶ際には、単に「銀行や保険会社が紹介したから」という理由ではなく、自社の成長戦略に合ったサポートが受けられるかどうかをしっかり見極めることが重要です。
税理士会からの紹介
税理士会に問い合わせると、税理士を紹介してもらうことができます。
しかし、税理士会で紹介されるのは「近くにいる税理士」であって、「自社に合う税理士」とは限りません。
税理士会の紹介制度は、公平性を保つために「順番制」を取っていることが多いのです。
つまり、「たまたま順番が回ってきた税理士」が紹介されるだけであり、その税理士の得意分野や実績までは考慮されません。
たとえば、飲食業の会社が税理士を探していたとします。
紹介された税理士が製造業に特化していた場合、飲食業界特有の「原価率の管理」「軽減税率制度」「インボイス制度」などの重要なポイントを正しく理解しておらず、的外れなアドバイスをされる可能性があります。
実際、飲食店では食品ロスの計算や、仕入れの値段が変わることをどう扱うかが、経営にとって大事です。
しかし、それまで製造業の会社ばかりを担当してきた税理士だと、飲食業の特別なルールをよく知らないこともあり、きちんとしたアドバイスが受けられないことがあります。
また、経営の相談に乗れない税理士が担当になった場合、「税金の計算はしてくれるが、資金繰りの改善や融資のアドバイスは一切してくれない」という事態になることもあります。
たとえば、銀行融資を受ける際に「どのタイミングで借りるべきか」「どのような資料を提出すれば審査に通りやすいか」といった戦略的なサポートがないまま進めた結果、本来通るはずの融資審査に落ちてしまい、資金ショートを起こすリスクも考えられるでしょう。
逆に、きちんとした税理士を選ぶことができれば、業界特有の税制や補助金制度を活用し、本来支払うべき税金を最適化することで、余剰資金を事業拡大に回せる可能性があります。
たとえば、IT業界に強い税理士であれば、「このシステム開発費用は資産計上ではなく、研究開発費として処理することで税額控除が受けられます」といった具体的なアドバイスを受けることができ、利益を最大化できるかもしれません。
税理士会からの紹介を受ける場合は、単に紹介されたからといってすぐに契約するのではなく、実際に面談をして「自社の業界に詳しいか」「経営の相談に乗ってくれるか」を必ず確認することが重要です。
税理士の選び方は悩みのタイプによって変えよう!悩みタイプ別の最適な選び方
税理士を選び直すべきかどうかは、今あなたが抱えている悩みによって変わります。
次のように、税理士に関する悩みは5つのタイプに分類でき、それぞれの悩みに対応した最適な選び方があります。
- 【今の税理士に不満がある】すぐに税理士を変えてOK!
- 【税理士費用を抑えたい】コスパ重視なら最低限の業務をしてくれるかを見よう
- 【もっと企業成長したい】攻めの経営を支える税理士を選ぼう!
- 【初めて税理士を探す】良い税理士を選ぶなら、事務所より「担当税理士」を見よう!
- 【税務調査に対応してほしい】税務調査に強い税理士を選ぼう!
以下からは、それぞれの悩みに応じた税理士の選び方を詳しく見ていきましょう。
【今の税理士に不満がある】すぐに税理士を変えてOK!
現在の税理士に不満があるなら、すぐにでも変更を検討すべきです。
なぜなら、税理士が原因で経営に悪影響が出る可能性があるからです。
以下からは、不満が起こりがちな税理士のパターンを3つ、見ていきましょう。
税理士への不満がある!違和感を覚えたら取るべき行動とは?
税理士との関係に、次のような不満を感じたことはありませんか? このように、税理士に対する違和感が積み重なり、不信感へとつながるケースは少なくありません。 しかし、税理士への不満をそのまま放置してしまうと、会社の成長に悪影 […]
記帳や決算申告しかやってくれない
「とりあえず帳簿をつけて、決算申告をしてくれるだけ」
こうした税理士に任せていると、経営の成長を阻害する原因になります。
本来、税理士は「経営のパートナー」として、節税や資金繰り、利益改善などのアドバイスをすべき存在です。
しかし、単なる作業として記帳や決算処理をしているだけなら、会社にとって何のプラスにもなりません。
たとえば、あなたの会社の利益が伸び悩んでいるとします。
その原因が「経費の使い方に問題がある」のか、「売上の伸ばし方がわからない」のかを分析し、改善策を提案してくれる税理士なら、会社の成長に貢献してくれるでしょう。
逆に、何もアドバイスせずに「はい、決算できました」と言うだけの税理士では、何年経っても経営状況は変わりません。
経営アドバイスをしてくれない
本当に良い税理士は、売上アップやキャッシュフロー改善に貢献できる税理士です。
たとえば、事業拡大のために設備投資を考えたとき、優秀な税理士なら「どのタイミングで設備投資すれば、税制優遇を最大限活用できるか」や「金融機関から有利な条件で融資を受ける方法」をアドバイスしてくれます。
しかし、経営に関心のない税理士は決算書を作るだけで終わってしまい、「あとはご自分で調べて、申請を」と放り出され、会社が本来受けられる恩恵を見落す結果となってしまうかもしれません。
経営の未来を考えていない税理士に任せていると、「気づいたら会社の資金繰りが厳しくなっていた」「本当は受けられた助成金を見落としていた」など、後悔することになりかねません。
対応が遅い
税理士の対応が遅いと、会社の経営に悪い影響を及ぼします。
たとえば、融資を受けたいときに、金融機関から「決算書や試算表を提出してください」と言われることがあります。
このとき、税理士がすぐに対応してくれれば問題ありませんが、何週間も待たされるようなら、資金繰りに支障が出るかもしれません。
また、税務調査の連絡が来たときに頼ったのに「忙しいので対応できません」と税理士から返答されたら、会社はどうなってしまうでしょうか?
税理士が迅速に動いてくれなければ、経営者が一人で税務調査に対応しなければならず、かなりの負担になります。
その間、企業活動の大半が停止してしまうこともあるでしょう。
税理士が「なかなか連絡を返してくれない」「急ぎの相談にもすぐ対応してくれない」という状況なら、早めに別の税理士を探した方がよいでしょう。
【税理士費用を抑えたい】コスパ重視なら最低限の業務をしてくれるかを見よう
「とにかく費用を安くしたい」と考えている場合、税理士の選び方は慎重に行うべきです。
安い税理士を選んでしまうと、次のような問題が起こる可能性があります。
安さで税理士を選ぶと結局損をする
税理士の顧問料は単なる固定費ではなく、経営の成長に直結する投資です。
安さだけで選ぶと、必要なアドバイスが受けられず、結果的に損をする可能性があります。
たとえば「月3万円の税理士」と「月10万円の税理士」では、提供されるサービスが大きく異なり、経営への影響も変わります。
また、税理士費用を「コスト」と考えるか「投資」と考えるかで、会社の未来も変わってくることでしょう。
そこで以下からは、税理士の料金によって受けられるサービスの違いや、安さを重視しすぎることのリスクについて詳しく解説していきます。
月3万の税理士は単なる作業代行、月10万の税理士は利益増の提案
税理士の顧問料が「月3万円」と「月10万円」では、提供されるサービスの内容と経営への影響が大きく異なります。
月3万円の税理士は、基本的に記帳や決済代行など決められた作業を代行します。
「この経費をどのタイミングで使うべきか」といったアドバイスはしてくれるかもしれません。
しかし、これだけでは単なる作業代行であり、企業の成長にはつながらず、利益を大きく伸ばすこともできません。
一方、月10万円の税理士は、経費の使い方はもちろんのこと、「利益をどう伸ばすか」「売上をどう増やすか」といった経営全体を見据えたサポートをしてくれます。
たとえば、「この事業は今後市場が拡大する可能性が高いため、今のうちに広告投資を増やし、認知度を上げておくべき」といった戦略的な助言が受けられる可能性があります。
また、資金調達の方法や、銀行との交渉の仕方まで考慮したアドバイスをし、長期的な視点で企業の成長を支えてくれるのです。
税理士は本来こうした、月額数十万円のコンサルティングサービスを提供する存在です。
企業の財務戦略を深く理解し、しっかりと経営判断をサポートできる税理士を雇うことで、数百万円単位の利益改善につながることもあります。
顧問契約を結んでいるのに、経営の助言が得られないのであれば、それは税理士の価値をフル活用できているとはいえず、企業にとって損失といえるでしょう。
税理士費用は「コスト」ではなく「投資」
安い税理士を選べば、短期的には出費を抑えられます。
しかし、単なるコスト削減ではなく、長期的な投資と捉えなければ、事業の成長は止まってしまう可能性があるのです。
現在、日本の経営環境は確実に厳しくなっています。
政府は2030年までに最低賃金を1.5倍に引き上げる方針を明言しており、さらに原価の高騰やAIの進展も加われば、人件費や運営コストなどの固定費が今後確実に増加していくことが予想されます。
もし、節税ばかりを優先し、利益を生み出すための投資を怠れば、企業の資本は圧迫され、固定費の増加に対応できずに経営が苦しくなってしまうでしょう。
たとえば、「売上は現状維持で十分!」と考え、税理士をも経費として節約しようとすると、資金繰りや利益改善のアドバイスが受けられないまま、固定費だけが膨らんでいくでしょう。
事業規模が変わらず売上が増えなければ、最低賃金の上昇や原価の高騰によって、利益率がどんどん低下し、やがて設備投資や人材確保が難しくなり、競争力を失っていくことも考えられます。
「現状維持」は、衰退なのです。
逆に、長期的な視点での経営サポートができる税理士を、多少コストがかかっても「投資」として選べば、ベストな資金運用のアドバイスが受けられ、成長に向けた戦略的な財務管理が可能になります。
たとえば、「今のタイミングで設備投資を行えば、補助金の活用でコストを削減でき、将来的な売上増加につながる」といった、現状に即したリアルな提案を受けることで、利益の最大化が図れるかもしれません。
こうした経営戦略まで考えられる税理士を選べば、最初は高く感じても、そのアドバイスによって生み出される利益で、顧問料以上のリターンを得られることも十分にありえます。
このように、税理士費用を単なる「コスト」と考えるのではなく、未来の利益を生み出すための「投資」として捉えることが、長期的な経営の成功につながるのです。
【もっと企業成長したい】攻めの経営を支える税理士を選ぼう
「節税は大事だが、それだけでは会社は成長しない」と考えている経営者は、税理士選びの基準を見直すべきです。
成長を支える税理士とは、「経営者が本当に必要としている情報を提供し、利益を最大化するための戦略を提案できる税理士」です。
では、成長したい企業はどのような視点で税理士を選べばよいのか、詳しく解説していきます。
売上・利益・キャッシュフローを良い方向に導けるか?
優秀な税理士は、「利益を最大化するために、どのような戦略が最適か?」という視点でアドバイスをしてくれます。
たとえば、「節税」ばかりに気を取られていると、本来なら成長に投資すべきお金まで削ってしまい、結果的に会社の発展が遅れてしまいます。
しかし、攻めの経営を支える税理士なら、「どこにお金を使えば、将来的に売上が伸びるのか?」を考えたアドバイスができるのです。
また、資金繰りに関するアドバイスも重要です。
「融資を受けるならこのタイミングがベスト」「補助金を活用して投資を進めるべき」など、具体的な提案ができる税理士は、経営の成長を後押ししてくれます。
逆に、利益アップやキャッシュフロー改善の視点を持たない税理士では、せっかくの成長の機会を逃してしまう可能性があります。
「決算対応」だけでなく、「未来の利益」を生み出せるか?
決算書を作ることは確かに税理士の仕事ですが、それだけでは企業の未来は変わりません。
たとえば、決算対策として「利益を圧縮して節税する」ことはよくある話です。
しかし、節税のために無理に経費を増やしてしまうと、資金繰りが悪化し、次年度の成長に必要な投資ができなくなるリスクがあります。
本当に優秀な税理士なら、「この支出は、将来的にどれくらいの利益を生み出せるのか?」という視点でアドバイスをくれます。
「単なる経費削減ではなく、利益を生み出す支出にフォーカスする」という考え方ができる税理士を選びましょう。
企業成長のための「財務戦略」を持っているか?
経営戦略と財務戦略は切っても切り離せません。
たとえば、事業拡大を考えているなら、どのタイミングで投資すべきか、どのように資金を調達すべきか、といった戦略が必要になります。
優秀な税理士は、単なる会計処理ではなく、「財務戦略をどう組み立てるべきか」をアドバイスできます。
以下のような視点を持つ税理士なら、経営の成長を後押ししてくれるでしょう。
- 設備投資や新規事業の資金調達のタイミングを見極められる税理士
- 補助金や助成金を活用し、成長を加速させる方法を提案できる税理士
- キャッシュフローを改善し、無理のない経営計画を立てられる税理士
きちんとした財務戦略のアドバイスを受けられるかどうかで、企業の成長スピードが大きく変わることがあります。
たとえば、売上が伸びるタイミングで事前に設備投資を行うことで、増産に成功し、競合よりも早く市場を獲得できる可能性が高くなるでしょう。
一方で、財務戦略を誤ると、資金繰りが悪化し、黒字であっても資金不足による経営難に陥るリスクも考えられます。
経営の未来を考え、成長のチャンスを確実に掴むためには、財務戦略を立てられる税理士を選ぶことが重要です。
【初めて税理士を探す】良い税理士を選ぶなら、事務所より「担当税理士」を見よう!
税理士を初めて探す場合、「どの事務所がいいのか?」という視点で探してしまいがちです。
しかし、実際には「事務所のブランド」よりも「担当税理士」が重要です。
良い税理士を選ぶためには、以下3つのポイントを意識しましょう。
- 事務所のブランドに惑わされるな!税理士選びは担当税理士が全て!
- スキル・経験・レスポンスの速さを確認し、相性の合う担当税理士を選ぶべし!
- 試算表の使い方を聞き、税理士の理解度を見極めよう!
それぞれ具体的にどのようなポイントなのかを解説します。
事務所のブランドに惑わされるな!税理士選びは担当税理士が全て!
「大手事務所だから安心」「知名度があるから信頼できる」と考えるのは危険です。
なぜなら、どんなに有名な事務所でも、実際に担当するのはその中の一人の税理士だからです。
たとえば、「有名な税理士法人に依頼したら、実際に担当になったのは経験の浅い新人だった」というケースもよくあります。
これでは、期待していたレベルのサポートを受けることはできません。
実際、経験の浅い税理士が担当になると、税務申告のミスや節税対策の漏れ、銀行融資の際の資料作成ミスなどが発生する可能性があります。
たとえば、決算前に「とりあえず利益を圧縮した方がいいですね」と提案され、よく考えずに高額な備品を購入してしまうと、どうなるでしょうか。
おそらく、数カ月後に資金ショートしてしまったり、補助金の申請条件を満たさなくなってしまうでしょう。
また、税務調査の際に担当税理士の経験が浅く、「この経費は業界的に一般的です」と説明したものの、税務署の担当官が「他社では聞いたことがない」と指摘してくることも考えられます。
すると、何の準備もしていないにも関わらず会社側が長時間の説明をするほかなく、まともに仕事ができなくなってしまうケースも起こり得るでしょう。
また、新人税理士の指導のもと、役員の交際費を福利厚生費として処理していたところ、税務調査で「これは給与とみなされる」と判断され、源泉所得税や社会保険料の不足分を求められ、追徴課税が発生、というケースも考えられます。
特に、福利厚生費として認められるためには「全従業員が公平に利用できる制度であること」が求められるため、役員のみを対象とした支出は税務リスクが高く、注意が必要です。
逆に、最初から実力のある税理士を選べば、以下のような企業の成長を支えるサポートを受けられる可能性があります。
- 決算の前にしっかりと利益調整を行い、納税額を最適化する
- 融資審査に通るための財務管理を徹底する
- 税務調査が入ってもちゃんと対応ができるよう事前準備を整える
また、経営視点を持つ税理士なら、「この事業は数年後に法改正で市場に規制がかかる可能性があるから、今のうちに別の収益源を作っておいた方がいい」といった長期的なリスク管理まで考えた提案をしてくれることでしょう。
たとえば、飲食店なら、通常メニューの一部を持ち帰り販売(テイクアウト)用に適した包装で提供し、消費税8%の軽減税率を適用することで、消費税10%のイートインとの差を活かした価格戦略が可能になります。
すると、競争が激化する中でも価格の優位性を持たせ、売上を維持する手段の一つとなるかもしれません。
※ただし、軽減税率の適用条件を満たさないと税務リスクが生じる可能性があるため、税理士と相談のうえ対応をしっかりと検討することが重要です。
このように、税理士を選ぶ際は、事務所の規模やブランドではなく、「実際に自分の会社を担当してくれる税理士は何に詳しくて、自分のいる市場に合わせた提案をしてくれるのか?」をしっかり確認しましょう。
それだけで、経営の安定度が変わる可能性があります。
スキル・経験・レスポンスの速さを確認し、相性の合う担当税理士を選ぶべし!
担当税理士がどれくらいのスキルを持っているかは、実際に話してみないとわかりません。
特に重要なのが、以下の3点です。
- スキル:自社の業界や事業内容に詳しいか?
- 経験:経営に関するアドバイスができるか?
- レスポンスの速さ:すぐに対応してくれるか?
たとえば、「あの補助金がうちでも使えるのかわからない」などと相談したときに、すぐに丁寧に説明してくれる税理士なら信頼できます。
しかし、業界の知識が乏しい税理士の場合、本来適用できるはずの節税策を知らず、数百万円単位で余計な税金を支払うことになるかもしれません。
また、経験不足の税理士に財務戦略の相談をして、「とりあえず銀行融資を受ければいい」と安易な提案をされ、将来的なキャッシュフローのシミュレーションが不十分なまま借入を決定してしまったら、どうなるでしょうか。
結果として、返済が重くのしかかり、成長投資のタイミングを逃してしまうといったことも考えられます。
さらに、レスポンスの遅い税理士と契約してしまうと、「決算ギリギリにならないと連絡が来ない」「税務調査の対応が後手に回り、必要な資料を揃える時間が足りず不利な判断をされる」「補助金申請の締め切りに間に合わず、数百万円のチャンスを逃す」といった事態に陥ることもあります。
逆に、スキル・経験・レスポンスの速い税理士を選べば、経営の見通しが劇的に変わるかもしれません。
たとえば、税理士のアドバイスを受けて早めに設備投資を決め、生産力が上がった結果、翌年度の売上を伸ばすといったケースが考えられます。
また、迅速な対応ができる税理士なら、突然の税務調査にも慌てることなく、必要な資料を整え、無駄な追徴課税を防ぐことができるはずです。
このように、税理士を選ぶ際は、事務所の規模や料金だけで判断せず、実際に担当者と話し、スキル・経験・レスポンスの速さを徹底的に確認することが重要です。
試算表の使い方を聞き、税理士の理解度を見極めよう!
税理士の実力を見極めるためには、「試算表の使い方を説明してもらう」のがおすすめです。
試算表とは、会社の経営状況を把握するための財務データのこと。
貸借対照表(BS)や損益計算書(PL)の数値をもとに作成される会計帳票であり、企業の資金繰りや経営状況をリアルタイムで確認するために使われます。
優秀な税理士なら、「この数値をどう活用すれば、売上や利益が伸びるか」を具体的に説明できます。
たとえば、試算表の数値を分析し、「来月の資金不足が予想されるため、取引先と支払い期限を交渉し、負担を軽減しましょう」「広告費を少し抑えれば、半年後に自己資本比率を改善できます」といった提案をしてくれる税理士なら、経営の舵取りが格段に楽になります。
しかし、試算表の説明が曖昧だったり、「とりあえず決算のときに見れば大丈夫ですよ」などと言う税理士は、経営の視点を持っていない可能性があるのです。
もしそんな税理士に任せていると、「なんとなくお金が回っていると思っていたが、突然資金ショートを起こした」「利益が出ているはずなのに、手元資金が減り続けている理由がわからない」といった事態に陥る可能性があります。
試算表の説明を頼んだときの対応をチェックし、経営のパートナーとしてふさわしい税理士かどうかを判断しましょう。
【税務調査に対応してほしい】税務調査に強い税理士を選ぼう!
税務調査の連絡が来ると、多くの経営者は不安になります。
しかし、普段から税務をきちんと管理していれば、慌てる必要はありません。
ただし、「税務調査に強い税理士」と「そうでない税理士」では、対応に差があります。
もし税務調査のリスクが気になるなら、今の税理士が本当に経営に貢献できているかを見直すべきです。
本来、健全な経営状況であれば税務調査を恐れる必要はありません。
以下からは、税務調査が不安な場合にどんな税理士を選ぶべきか、具体的に解説します。
税務調査が不安なら、その場しのぎの対応ではなく「経営の見直し」を!
税務調査への対応だけを考えて税理士を選ぶのは、短期的な視点にすぎません。
本当に重要なのは、「そもそも税務調査が入りにくい経営状態を作ること」です。
一般的に税務調査が入りやすい業種とそうでない業種などが言われていますが、基本的には利益の数字が大きく変動していたり、経費の使い方が不透明だったりすると、税務調査の対象になりやすくなります。
しかし、普段から税理士がきちんとしたアドバイスをしていれば、不審に思われるポイントを事前に改善することができます。
短期的に「税務調査の対策だけ」を考えて税理士を選んでも、根本的な問題が解決しなければ、また別の問題が起こる可能性があるのです。
たとえば、直前になって慌てて書類を揃えても、過去の帳簿に不整合があれば調査官に指摘され、結果として追加の税金や罰則を課されることもあります。
さらに、調査時に曖昧な説明をしてしまうと、「意図的な隠ぺいの可能性あり」と判断され、追徴課税だけでなく、銀行からの信用も失い、融資が厳しくなる可能性があります。
一方、真っ当な税理士を選び、常に経営全体の動きを注視しておけば、「この支出はどの勘定科目に入れるべきか」「売上の増減をどのように記録するか」といった日々の処理を正しく行えるでしょう。
どうしても帳簿管理が苦痛なら、思い切って帳簿だけ書いてくれる特化型の税理士に任せる方法を検討してみてください。
帳簿を税理士に任せることで、以下のようなメリットがあります。
- 本業に集中できる(面倒な記帳作業に時間を取られない)
- 税務リスクが減る(ミスや抜け漏れを防げる)
- 節税のチャンスを逃さない(適用できる控除や経費を正しく処理)
- 経理業務が効率化(請求書や領収書の整理もスムーズに)
- 税務調査の際も安心(正確な帳簿があれば対応が楽)
- 記帳代行ならコストも比較的安価(顧問契約より手軽に依頼できる、ただし決算3ヶ月前など直前では嫌がられることが多く注意)
結果として、税務調査が入ったとしても問題を指摘されることがなく、スムーズに調査を終えることができる可能性が高まります。
まずは、経営全体を見直し、調査リスクの少ない、健全な経営状態を作れる税理士を選んでみてはいかがでしょうか。
税理士の選び方で失敗しないために見極めるべきポイント
税理士を選ぶ際に失敗しないためには、次の3つのポイントを確認する必要があります。
- ポイント1:実際に担当してくれる税理士と直接話す!
- ポイント2:料金ではなく、「提供価値」で選ぶ!
- ポイント3:短期間の試用契約を活用し、本契約する価値があるか確かめる!
以下からは、特に見落としがちなこうした3つのチェックポイントについて詳しく解説します。
ポイント1:実際に担当してくれる税理士と直接話す!
税理士事務所を選ぶ際、「有名な事務所だから大丈夫」と思い込むのは危険です。
実際にあなたの会社を担当する税理士が誰なのかを、事前に確認することが最も重要です。
特に、大手事務所では「営業担当が契約を取り、その後に税理士が割り当てられる」という流れになっていることがあります。
この場合、実際に担当する税理士のスキルや相性が事前に分からず、契約後に「思っていたのと違った」と後悔することになりかねません。
また、「実際の担当者と契約前に話せない」ような事務所は、避けたほうがよいでしょう。
経営者が直接話をして、税理士の対応力や考え方を確認することが不可欠です。
ポイント2:料金ではなく、「提供価値」で選ぶ!
税理士の料金は事務所によって異なりますが、「安い=良い税理士」ではありません。
むしろ、安さを優先して選ぶと、会社の成長を妨げる可能性があります。
たとえば、安い税理士と高い税理士では、以下の表のようにサービスの内容が大きく異なります。
| 税理士のタイプ |
対応業務 |
経営アドバイス |
資金繰りサポート |
補助金・融資相談 |
|---|---|---|---|---|
| 安い税理士 | 決算・税務申告などの基本業務のみ | ほぼなし | なし | なし |
| 高い税理士 | 決算・税務申告+経営戦略サポート | あり | あり | あり |
なぜ、手厚いサポートをする税理士は料金が高くなるのでしょうか。
それは、単なる税務処理だけでなく、経営戦略の提案や、資金繰りのアドバイス、補助金・融資の支援など、企業の成長に直結するいくつものサポートを提供するためです。
こうした包括的な経営サポートを行うためには、経験豊富な専門チームを抱え、最新の税法や節税策を常に研究する必要があり、その分の人件費・研究費がかかるのです。
もし安さだけで税理士を選んでしまうと、本来活用できたはずの節税策や補助金を見逃し、結局、年間数百万単位の損をする可能性があります。
たとえば、補助金の申請に関する知識がない税理士を選んだせいで、他の競合企業は500万円の補助金を受け取れたのに、自社は申請すらせず、資金繰りに苦しむことになるケースも考えられます。
また、安い税理士の場合、顧問先が多すぎて1社ごとの対応が手薄になることがあり、問い合わせても「確認しておきます」と言われたまま1週間以上放置され、急ぎの資金調達や税務対応の判断が遅れてしまうことも起きがちです。
最悪の場合、税務申告のミスに気づかず、後から税務調査が入り、多額の追徴課税を払うことになりかねません。
逆に、高い税理士を選べば、以下のように財務アドバイスを活かした結果が得られるはずです。
- 資金繰りが改善し、取引先との支払い条件を有利に変更
- 経営計画をしっかり立てられ、銀行からの融資をスムーズに
- 利益率が向上し、従業員の給与を増額
税理士費用は「コスト」ではなく「投資」と考えるべきです。
安い税理士を選んでしまうと、長期的には大きな利益を逃すどころか、損することになりかねません。
目先の料金ではなく、「この税理士は会社の成長にどれほど貢献してくれるのか?」 という視点で選ぶことが、経営を成功させるカギとなります。
ポイント3:短期間の試用契約を活用し、本契約する価値があるか確かめる!
税理士といきなり長期契約を結ぶのではなく、「短期間の試用契約」や「セカンドオピニオン」を活用することがおすすめです。
たとえば、複数の税理士に試験的に依頼し、それぞれの対応を比較することで、本当に信頼できる税理士を見極めることができます。
実際に試用契約をせずに税理士を選んでしまい、後悔するケースは少なくありません。
そもそも、セカンドオピニオンや試用契約を完全に拒否する税理士事務所であれば、その時点で候補から外すべきです。
試しに依頼することすら許されないなら、契約後に「思っていたのと違った」と気づいたときのリスクが大きすぎることになります。
そうした税理士と契約してしまうと、「契約前は良さそうに思えたが、実際に依頼してみたら対応が遅すぎて、急ぎの資金繰り相談にも3日以上返信がなかった」 ということが起こり得るでしょう。
さらに、「試算表のミスに気づかないまま決算を迎え、直前で 『数百万円の誤りがある』と指摘され、大慌てで修正対応に追われた」 というケースも考えられます。
こうした状況に陥ると、税理士を変更するにも時間がかかり、その間は信用ならない税理士を雇い続けることになるため、さらに税務リスクが発生する可能性もあるのです。
確かに、複数の税理士に依頼することで一時的な費用はかかります。
しかし、これまで見てきたように、税理士選びを誤ると、経営の方向性を間違えたり、無駄な税負担が増えたりするリスクがあるのです。
このようなセカンドオピニオンを、最適な税理士を選ぶための「試験費用」と考えれば、決して無駄な出費ではありません。
税理士の選び方を間違えると、会社の成長が止まる!今すぐ見直そう
今回は、税理士の選び方について詳しく解説しました。
税理士は、会社の成長を支える重要なパートナーですが、間違った税理士を選ぶと、経営に深刻な影響をもたらしてしまうことがあります。
税理士を料金の安さだけで選ぶと、記帳や決算申告はしてくれても、経営のアドバイスはまず受けられません。
結果的に安い税理士は利益を伸ばす機会を逃し、会社の成長が止まる原因になります。
契約する際は、いきなり本契約せず、試用契約で対応を確認することが大切です。
相性が悪いと後で変更が難しく、無駄な手間やコストが増えます。
また、将来の経営を考えない税理士では、資金繰りや利益改善がうまくいかず、事業拡大の妨げになります。
税理士は経営のパートナーとして慎重に選び、会社の未来を守りましょう。
税理士を変更したい!次の税理士の選び方に迷ったら?
自社に合った税理士の選び方がわからないときは、専門のサポートを受けるのが最も確実な方法です。
単なるネット検索や知人の紹介に頼るのではなく、自分の要望を柔軟にかなえられるマッチングサービスを利用できれば、税理士選びで失敗せず、経営の課題に合ったサポートを受けられる可能性が高まります。
THE CXO では、あなたの会社の状況や経営方針に合った税理士を紹介し、最適なマッチングをサポートします。
「どんな税理士を選べばいいかわからない」「今の税理士に不満があるが、次の税理士をどう探せばいいかわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
会社の未来を支える税理士を見つけることが、経営の成長を加速させる第一歩です。
今すぐ、自社に最適な税理士選びを始めましょう!