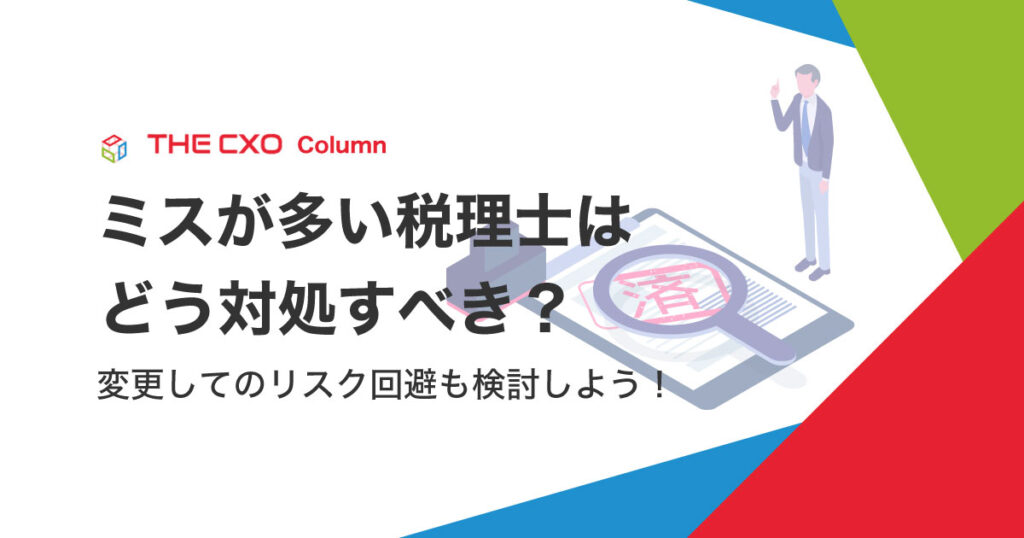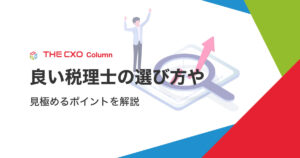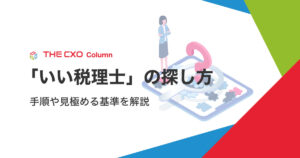税理士を変えるべき最適なタイミングとは?失敗しない方法を解説
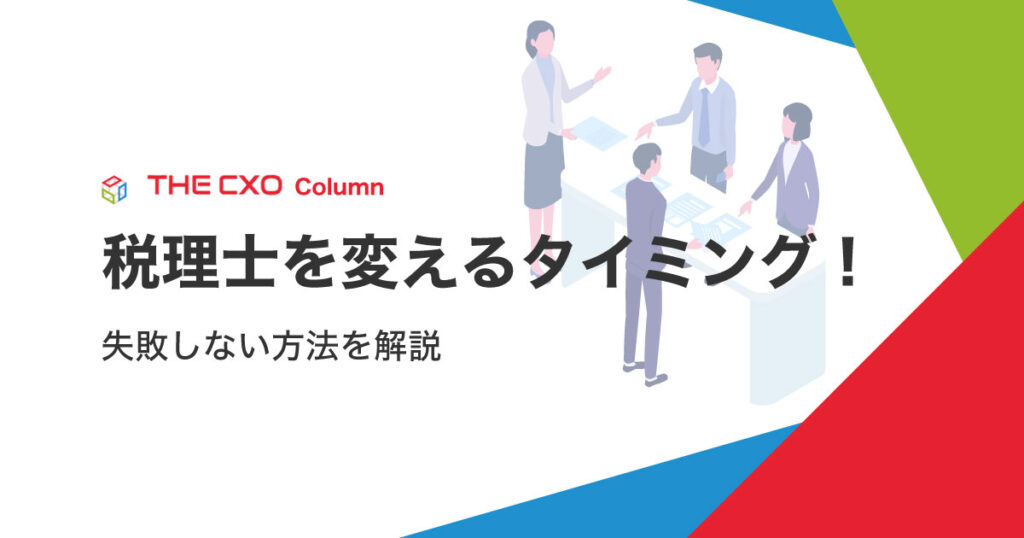
現在の税理士に対して、不満を感じているものの「本当に変えていいのか?」と迷っていませんか。
税理士の変更は、決して珍しいことではなく、むしろ適切なタイミングで行えば、経営にとってプラスになります。
そもそも、一般的な税理士の選び方には誤解が多く、たとえば「有名な事務所だから」「紹介されたから」「料金が安いから」といった理由だけで選ぶのは正しくありません。
税理士は、ただの帳簿処理担当ではなく、経営を支える重要なパートナーです。
選び方を間違えると、税務のミスや経営判断の遅れといった問題につながります。
そこで本記事では、「税理士を変えるべきサイン」と「実際に変更する最適なタイミング」について詳しく解説します。
不満があるなら、いつでも変えて構いませんが、特にスムーズに進められる時期もあるため、その点も押さえておきましょう。
株式会社カタリスタ 代表取締役
THE CXO 株式会社 代表取締役
飯島 彰仁(いいじま あきひと)
Iijima Akihito
経営計画コンサルタント、中小企業の社外CXO。大手会計事務所元代表取締役社長として、同社を年商22億円、従業員数447名の規模にまで成長させた実績を持つ。
これまで3,000社以上の中小企業に対し、財務やマーケティングを通じた経営向上に貢献。
その中で、中小企業の成長のためには、単なる税務処理を超え、経営に深く関与する税理士が必要不可欠であることを痛感。
その経験をもとに、税理士が真の価値を発揮する「社外CXOメソッド」を開発。累計300人以上の税理士に伝授し、「税務の枠を超え、中小企業のあらゆる相談に乗れるパートナー」を養成。
指導した税理士達からは、顧問先の売上向上、利益向上、V字回復や事業改善など成功報告が続々と寄せられている。

- 1. 【結論】税理士を変えるベストタイミングは「変えたい」と思った時
- 2. 税理士を変えるタイミングの基準
- 2.1. 事業フェーズ(創業期・成長期・安定期)
- 2.2. 自社の課題の変化
- 3. 「このままで大丈夫?」税理士を変えるべき危険な7つのケース
- 3.1. 連絡が遅い・対応が悪い
- 3.2. 記帳や申告の代行しかしていない・節税対策してくれない
- 3.3. 訪問がなく、コミュニケーションが希薄
- 3.4. 税務・会計業務のミスが増えた
- 3.5. 事業の規模や方向性が変わったのに、クラウド会計などに対応してくれない
- 3.6. 顧問料とサービスが見合わない
- 3.7. 事業承継や相続の準備がしたい
- 4. 税理士を変更しやすいタイミング
- 4.1. 決算の4〜6か月前
- 4.2. 決算後すぐ
- 4.3. 法人税申告・確定申告が終わったタイミング
- 4.4. 新制度対応の前、税務調査予告が来た時
- 5. 税理士を変更しづらいタイミングは決算の3カ月前!
- 6. 税理士変更は迷う時間がもったいない!最適なタイミングとスムーズな進行をTHE CXOがサポート
【結論】税理士を変えるベストタイミングは「変えたい」と思った時
税理士を変更するタイミングに正解はありません。
契約期間が決まっている場合を除けば、不満を感じた時点でいつでも変えて問題ありません。
「もう少し様子を見よう」と先延ばしにしていると、経営に悪影響が出る可能性があります。
たとえば、連絡が遅い税理士に任せていると、税務申告の期限が迫ってもアドバイスを受けられず、結果的に不要な税金を支払うことになりかねません。
また、事業が成長している状況に見合う節税対策をしてくれない税理士を使い続けていると、結果的にトータル数百万円単位で損をすることもあります。
税理士の変更は手間がかかると思われがちですが、ちゃんとした引き継ぎを行えばスムーズに進みます。
むしろ、合わない税理士を使い続けるほうが、経営にとってはるかに大きなリスクです。
税理士を変えるタイミングの基準
税理士を変更するべきかどうかは、「なんらか不満がある」など感覚頼りで判断するとともに、はっきりとした基準を持つことも重要です。
特に、事業のフェーズや自社の課題の変化によって、必要な税理士のスキルやサポート内容が変わるため、状況に応じて見直す必要があります。
税理士を見直すべき基準として意識したい点は、次の通りです。
- 事業フェーズ(創業期・成長期・安定期)
- 自社の課題の変化
以下から、それぞれ詳しく見ていきましょう。
事業フェーズ(創業期・成長期・安定期)
企業の成長段階によって、税理士に求められる役割は異なります。
創業期は、資金調達や創業融資、開業費の税務処理に詳しい税理士が役立ちます。
しかし、事業が成長すれば、財務戦略や組織再編、M&Aの知識なども必要になるため、創業支援に特化した税理士では対応しきれないことがあります。
たとえば、年間売上が1,000万円程度の事業者が、資金繰りや節税の相談を中心にしていた場合、創業支援型の税理士で十分でしょう。
しかし、売上が1億円を超え、社員が増え、法人税対策や事業拡大の計画が必要になってくると、成長支援に強い税理士に切り替えたほうが経営メリットは大きくなります。
安定期に入った企業の場合、次に重要になるのは、事業承継や相続対策です。
親族内での事業継承を考えるなら、相続税や贈与税に強い税理士が必要となるでしょう。
また、M&Aによる事業売却を視野に入れるなら、デューデリジェンス(企業価値評価)の実務経験がある税理士に依頼するのがベターです。
このように、会社の成長とともに税理士に求めるスキルセット(知識・経験・対応力など)も変わるため、定期的に顧問税理士を見直すことは欠かせません。
自社の課題の変化
税理士を選ぶ際には、自社が抱えている課題をはっきりさせておくことが大前提です。
たとえば「お腹が痛いのに眼科に行く」でしょうか?
誰しも、そのような間違った状況は自然と避けるはずです。
税理士も医者選びのように、きちんと「専門家」を選ばなければなりません。
改めて、税理士選びでこうした「課題の違い」について考えてみましょう。
たとえば、税務調査が課題の場合です。
税務調査に対応できる税理士を求めているのに、単なる記帳代行に特化した税理士と契約してしまい、いざ税務調査が入った際になんのサポートも受けられない、といった事態が挙げられます。
同様に、業務効率化が課題の場合はどうでしょうか。
クラウド会計を活用して業務効率化を進めたいのに、紙の帳簿管理しか対応できない税理士を雇ってしまう、というケースが考えられます。
デジタルな会計処理ができない税理士では、書類枚数が膨れ上がり、管理もしづらく、経理業務が無駄にややこしくなります。
自社の課題が変わった際に、現在の税理士が対応できるかどうかを判断するためには、税理士のセカンドオピニオンを活用するのもおすすめです。
「このままで大丈夫?」税理士を変えるべき危険な7つのケース
税理士を変えるべきタイミングは、不満を感じた時だけとは限りません。
税理士がいるのに逆に経営が行き詰まっているな、経営しづらいな、なんか面倒だな、というような気配を感じた場合は、すぐにでも税理士を見直すべきです。
特に、次の7つのケースに当てはまるなら、税理士の変更を検討するべきタイミングといえます。
- 連絡が遅い・対応が悪い
- 記帳や申告の代行しかしていない・節税対策してくれない
- 訪問がなく、コミュニケーションが希薄
- 税務・会計業務のミスが増えた
- 事業の規模や方向性が変わったのに、クラウド会計などに対応してくれない
- 顧問料とサービスが見合わない
- 事業承継や相続の準備がしたい
以下からは、こうした「税理士変更を考えるべきサイン」について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
連絡が遅い・対応が悪い
税理士とのコミュニケーションがスムーズにいかない場合、経営判断に支障をきたします。
たとえば、資金繰りについて急ぎで相談したいのに、何日も返答がないと、それだけで経営が止まってしまいます。
また、税理士に質問を投げかけてたのに「調べておきます」と言われたまま放置されるケースも少なくありません。
こうした対応が続くと、経営者は必要な情報を得られず、最適な税務戦略を立てることができなくなります。
税理士は「経営のパートナー」であり、単なる外注先ではありません。
連絡が遅い、対応が雑、相談しづらいといった問題があれば、早急に見直しを検討すべきです。
記帳や申告の代行しかしていない・節税対策してくれない
記帳代行や申告のサポートは税理士の基本業務ですが、それだけでは不十分です。
税理士は企業の財務や税務のデータをすべて扱う立場にあるため、本来であれば経営に関する数値がすべて開示された時点で、その企業にとって有益な経営コンサル並のアドバイスができるはずです。
しかし、実際には 「記帳代行+申告業務のみ」にとどまる税理士が多く、経営支援に積極的に関与する税理士は限られています。
こうしたギャップは、税理士の報酬体系や業務スタンスの違い、さらには企業側の「税理士=申告代行業務の人」という意識の問題も影響して起こるものです。
そのため、「税理士に経営アドバイスを期待するなら、最初からそういうスタンスの税理士を選ぶこと」が重要です。
実際、成長を支える税理士は、単なる税務処理だけでなく、節税・資金繰り・財務戦略まで含めた包括的なサポートをしています。
企業が税理士を顧問にする最大のメリットは、「経営のアドバイス」や「きちんとした節税対策」を受けることにあります。
たとえば、会社の利益が増えているのに、税理士から節税策の提案がまったくないとしたら、大きな損失につながるかもしれません。
場面場面に応じた税務戦略ができていれば、法人税や所得税を何十万円、場合によっては何百万円も削減できる可能性があります。
また、補助金や助成金の活用に関するアドバイスがまったくない場合も問題です。
事業の成長には、資金調達や制度の活用が不可欠ですが、税理士がこうした自社に有利な情報を提示してくれないのであれば、他の税理士に相談する価値は十分にあります。
訪問がなく、コミュニケーションが希薄
税理士が顧問先であるあなたのもとに訪問してこない場合、企業の経営状況を深く理解できていない可能性があります。
もちろん、オンラインでのやり取りは主流になりつつありますが、経営の重要な局面では、対面での相談が不可欠なことも多いものです。
経営者の悩みは、単なる税務処理だけではありません。
資金繰りや人件費の見直し、新規事業の立ち上げなど、幅広い問題が絡んできます。
そのため、実際に会社を訪問し、現場の状況を見ながら論拠のある助言をしてくれる税理士のほうが、経営にとってメリットをもたらします。
税務・会計業務のミスが増えた
申告ミスや記帳の誤りが頻発する税理士に任せていると、企業の信用問題にもつながります。
たとえば、税務申告の計算ミスによって過少申告が発覚すると、税務調査で指摘を受け、追徴課税を支払わなければならないリスクが高まります。
逆に、必要以上に税金を払い過ぎているケースもあり、本来であれば節税できたはずの資金を無駄にしている可能性もあります。
また、会計処理の誤りがあると、決算書の数字が正確でなくなり、銀行からの融資審査に悪影響を及ぼすことも考えられます。
もし、税理士のミスによるトラブルが発生しているなら、早めに他の税理士に相談すべきです。
ミスが多い税理士はどう対処すべき?変更してのリスク回避も検討しよう!
「うちの税理士、よくミスをするけど、これって普通なのか?」と思ったことはありませんか? 経理や税務に関するミスは、企業経営に大きな影響を与える可能性があります。 決算書の誤り、税務申告の不備、税務調査時の指摘事項など、税 […]
事業の規模や方向性が変わったのに、クラウド会計などに対応してくれない
事業が成長すれば、経理業務も効率化すべきです。
しかし、税理士が未だに紙の帳簿やExcelベースの処理にこだわり、クラウド会計などの最新技術に対応できていない場合、企業の成長を妨げる要因になります。
たとえば、複数の支店や拠点を持つ企業がクラウド会計を導入すれば、リアルタイムで財務データを共有できるため、経営判断のスピードが上がります。
しかし、税理士がクラウド会計の知識を持っていないと、システム移行ができず、旧態依然とした手間のかかるアナログな方法に縛られることになるのです。
最新の会計ツールを活用できる税理士であれば、経理の負担を減らしつつ、より戦略的な経営判断を支援してくれます。
顧問料とサービスが見合わない
「税理士に支払う顧問料が、会社の財務に対して相応の価値をもたらしているか?」については、常に見直すべきです。
もし、毎月高い顧問料を支払っているのに、受けられるサービスが単なる記帳代行や決算申告だけなら、コストパフォーマンスが悪いと言えます。
たとえば、同じ価格帯でも、税務調査のリスクを最小限に抑えたり、資金繰りや補助金活用のアドバイスをしてくれる税理士もいます。
一方で、「質問しても曖昧な回答しか返ってこない」「ただ決算書を作るだけ」といった税理士では、経営の役に立ちません。
このような場合、セカンドオピニオン的に無料相談などを活用して他の税理士と比較すれば、今の税理士が本当に自分に合っているかどうかを判断する材料になります。
事業承継や相続の準備がしたい
事業承継や相続の問題は、税理士の専門性が問われる分野です。
親族内での事業承継を考えている場合、相続税や贈与税の対策をきちんとしておかないと、多額の税金が発生し、事業の継続が困難になることがあります。
もし、事業譲渡やM&Aを考えているなら、税制上の最適なスキームを組む必要があり、経験豊富な税理士のサポートが不可欠です。
今の税理士がこうした専門的なアドバイスができないなら、事業承継や相続に強い税理士への切り替えを検討しましょう。
税理士を変更しやすいタイミング
税理士の変更は「変えたい」と思ったときに行えば問題ありません。
特にスムーズに移行しやすいタイミングは、以下の通りです。
- 決算の4〜6か月前
- 決算後すぐ
- 法人税申告・確定申告が終わったタイミング
- 新制度対応の前、税務調査予告が来た時
それぞれのタイミングで変更するメリットと注意点について、詳しく見ていきましょう。
決算の4〜6か月前
決算の4〜6か月前に税理士を変更すると、新しい税理士が十分な準備をする時間を確保でき、スムーズに決算の対策がしやすくなります。
たとえば、法人税の節税を考える場合、決算ギリギリに対策を打とうとしても、できることは限られます。
しかし、数か月前から準備していれば、役員報酬の調整や設備投資の計画、必要経費の最適化など、さまざまな方法を検討できるのです。
また、現在の税理士との契約を見直す時間的な余裕もできるため、トラブルなく移行しやすい時期でもあります。
決算後すぐ
決算が終わった直後のタイミングも、税理士を変更しやすい時期のひとつです。
決算処理がすべて完了し、法人税の申告も終えていれば、新しい税理士に過去の決算データを引き継ぎやすくなります。
また、翌期の経営方針を新しい税理士と相談しながら決めることで、経営パートナーとしてのより良い関係がスタートできるのです。
たとえば、決算後に「もっと節税の提案をしてくれる税理士に依頼すればよかった」と感じることがあれば、その時点で変更を決断するのが良いでしょう。
次の決算まで1年の猶予があるため、新しい税理士もじっくりと準備ができます。
法人税申告・確定申告が終わったタイミング
法人の決算後だけでなく、個人事業主の確定申告が終わった後も、税理士変更の良いタイミングです。
確定申告の時期が過ぎると、多くの税理士は新しい顧問契約を受け入れやすくなります。
特に、個人事業主の場合は、3〜4月は比較的業務が落ち着くため、新しい税理士とじっくり打ち合わせをする時間を確保しやすい時期でもあります。
また、確定申告を終えた後に「もっと積極的なアドバイスをくれる税理士を選ぶべきだった」と感じた場合、翌年の申告で後悔しないためにも、この時期に変更するのがベストです。
新制度対応の前、税務調査予告が来た時
税理士を変えるのに適したタイミングの一つが、新しい税制や制度が始まる前です。
税金や経理のルールが変わると、対応が間に合わないとトラブルになり、経営にも影響が出ることがあります。
たとえば、「インボイス制度」 という新しいルールでは、適格請求書が発行できないと、取引先が不利になるため、契約を打ち切られるケースがあります。
「今の税理士に相談したけど、対応方法がわからないと言われた」という状況では、事業にとって大きなマイナスになります。
また、「電子帳簿保存法」 という新しいルールでは、紙の領収書をデータで管理する必要があります。
ところが、「今の税理士が古い考えで、すべて紙で処理しようとする」というような場合、会社の経理がどんどん手間になり、無駄な時間と人件費が増えてしまいます。
このように、新しい制度にすぐ対応できない税理士を使い続けると、取引先を失ったり、経理の負担が増えたりと、余計なリスクを抱えることになります。
新しい制度が始まる前なら、余裕を持って準備ができるので、税理士を切り替えるには最適なタイミングです。
また、税務調査の可能性がある場合も、事前にしっかり準備できる税理士に変更しておけば、余計な指摘を受けずに済みます。
税務調査は突然通知されることが多いため、準備に不安を感じるかもしれません。
しかし、企業は日頃から適切な帳簿管理や申告を行い、仮に毎年税務調査が入っても問題がない状態にしておくべきです。
そのため、本来は特別なことではなく、自社に合う税理士とともに正しく処理していれば過度に心配する必要はありません。
このように、税理士を変えるなら、新しい制度に対応しやすいタイミングを狙いましょう。
事前に新制度や税務調査の準備を進められる税理士と契約すれば、スムーズに移行でき、事業のリスクを減らすことができます。
税理士を変更しづらいタイミングは決算の3カ月前!
税理士の変更は基本的にいつでも可能ですが、決算の3カ月前からだけは特に注意が必要です。
この時期に変更しようとすると、新しい税理士にとって非常に手間が増えがちで、労働対価として合わないため、面倒がって引き受けてくれないケースが多くなります。
会社は「この1年間でどれくらい儲かったのか」を1年に1回計算する決算を行い、税務署に報告しなければなりません。
決算のために、会社のお金の流れをまとめた決算書を作ることになります。
税理士は、決算書を作るために、日々の会計データを確認し、経費や利益を整理する作業を行います。
決算の3カ月前になると、税理士はすでにクライアントごとの決算準備を進めており、新しい契約を受け入れる余裕が少なくなるのです。
特に、これまでの会計処理が正しいかを確認するには時間がかかるため、直前になって税理士を変えると、以下のようなトラブルが起こる可能性があります。
- 決算書の作成が間に合わず、期限を過ぎてしまう(延滞税を払わされる)
- 会計データの引き継ぎが不十分で、経費の漏れなど税理士が計上ミスをする
このような理由から、決算の3カ月前に税理士を変更しようとしても、引き受けてもらえなかったり、十分な準備ができないまま決算作業に入ることになり、結果的に会社として損失を生む可能性があります。
ただし、どうしても決算の3カ月前に税理士を変更しなければならない場合は、以下のような対策をすれば、スムーズに移行できる可能性を高めることはできます。
- 可能な限り、前の税理士から会計データを整理してもらってから変更する
- 月ごとの会計データをきちんとまとめ、新しい税理士が状況をすぐ把握できるようにする
- 決算業務だけは前の税理士に依頼し、その後に変更する
慎重に準備をすれば決算の3カ月前でも税理士を変える対応はできますが、リスクが多いため、できるだけこの時期を避けるのが無難です。
税理士変更は迷う時間がもったいない!最適なタイミングとスムーズな進行をTHE CXOがサポート
今回は、税理士を変更するべきサインや、最適なタイミングについて詳しく解説しました。
現在の税理士に不満を感じたのであれば、その時点で変更すればOKです。
迷っている時間が、最ももったいないといえます。
「まだいいかもしれない」と先延ばしにしているうちに、損をしている可能性があるからです。
いくら今の税理士を変えようと思っていても、税理士を雇っている限り、顧問料は毎月発生し続けます。
不満があるまま放置すると、本来受けられるはずの節税対策を受けられずに余計な税金を支払っていたり、助成金や補助金の申請機会を逃していたりするかもしれません。
特に、事業の成長や新しい税制への対応が求められる場面では、税理士のサポートが経営の支えになります。
一方で、税理士を変更する際の手続きに不安を感じる経営者も多いでしょう。
「解約を伝えるタイミングは?」「新しい税理士はどうやって探せばいい?」といった疑問を持つのは当然です。
THE CXOでは、税理士変更をスムーズに進めるためのサポートを行っています。
単なる「税理士の紹介」ではなく、経営者の課題やニーズに合った税理士をマッチングすることを重視し、実務を担当する税理士の人柄や対応力も考慮したうえで選定します。
税理士は、会社の未来に関わる重要なパートナーです。
「税理士が本当に経営の力になってくれているか?」を今一度見直し、必要であれば早めの行動を心がけてみてください。