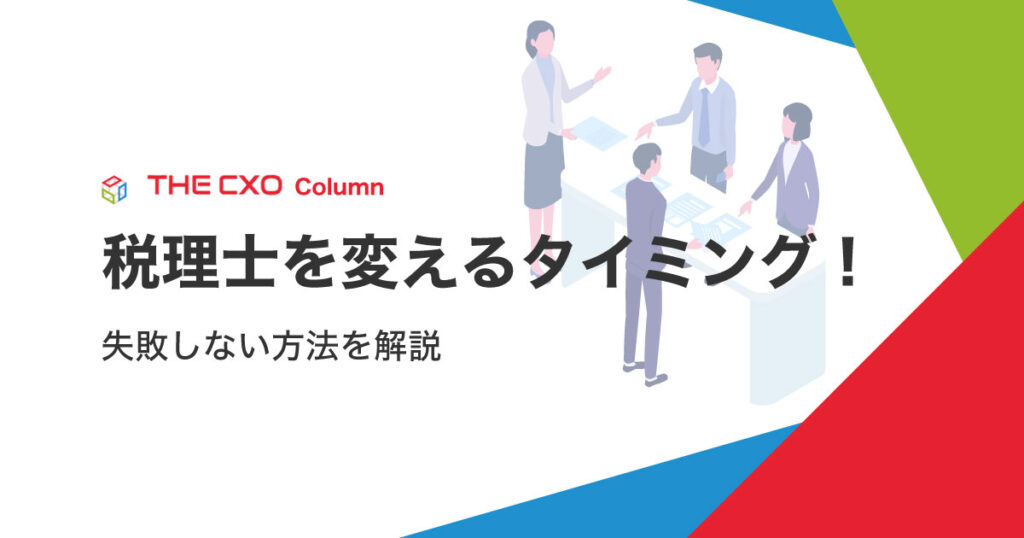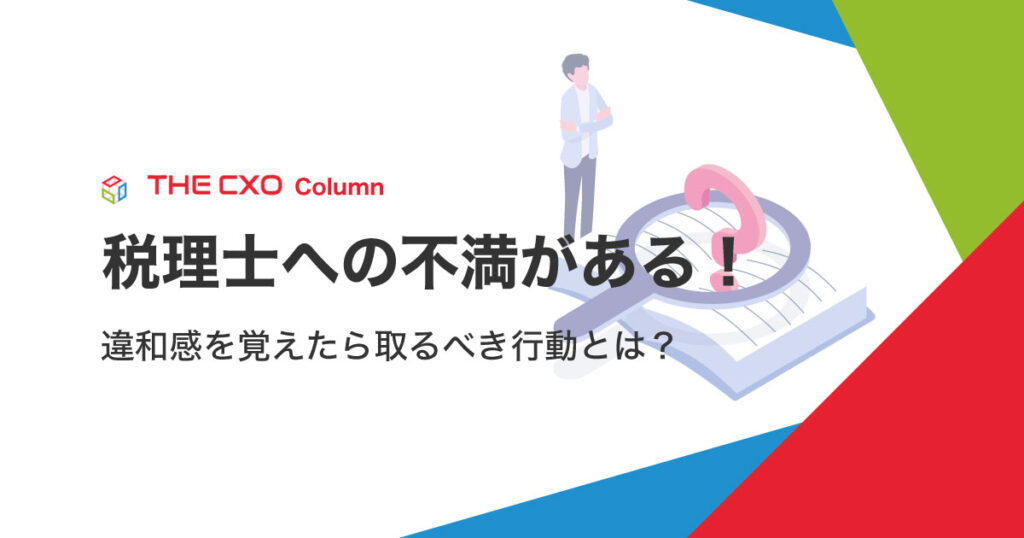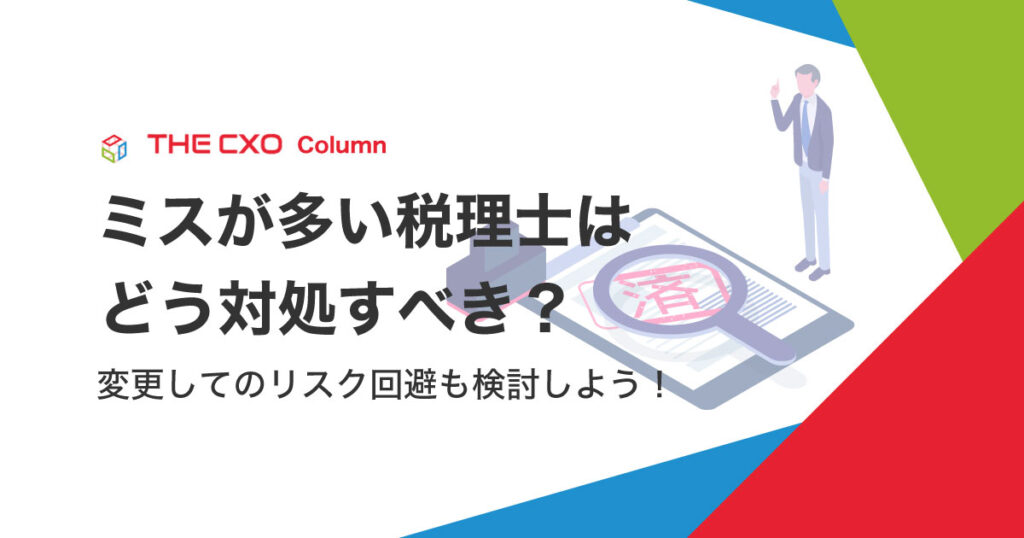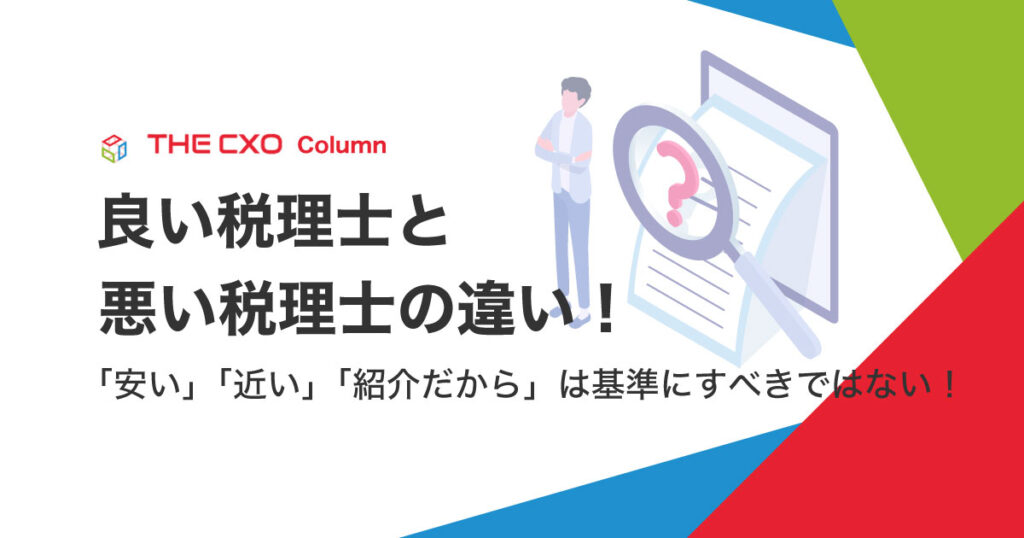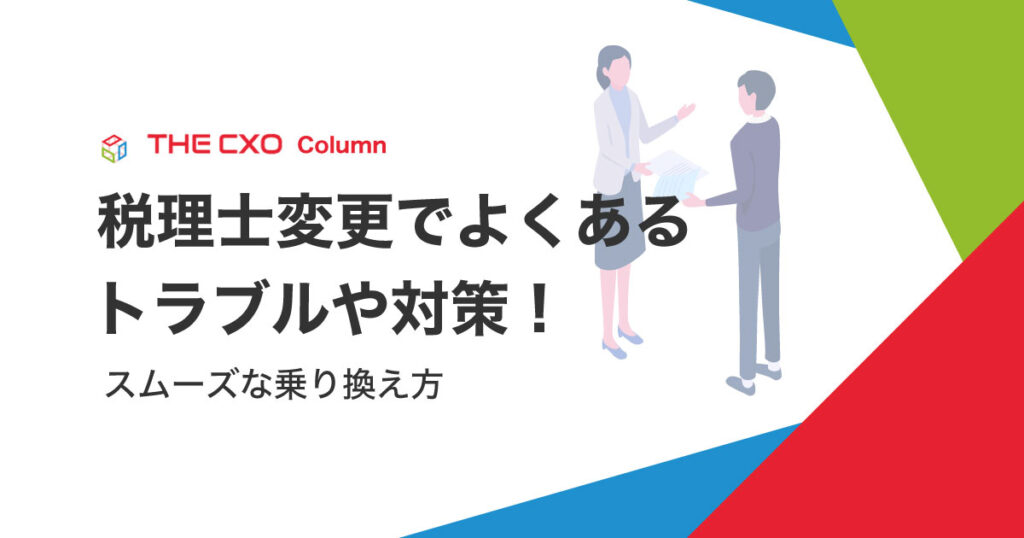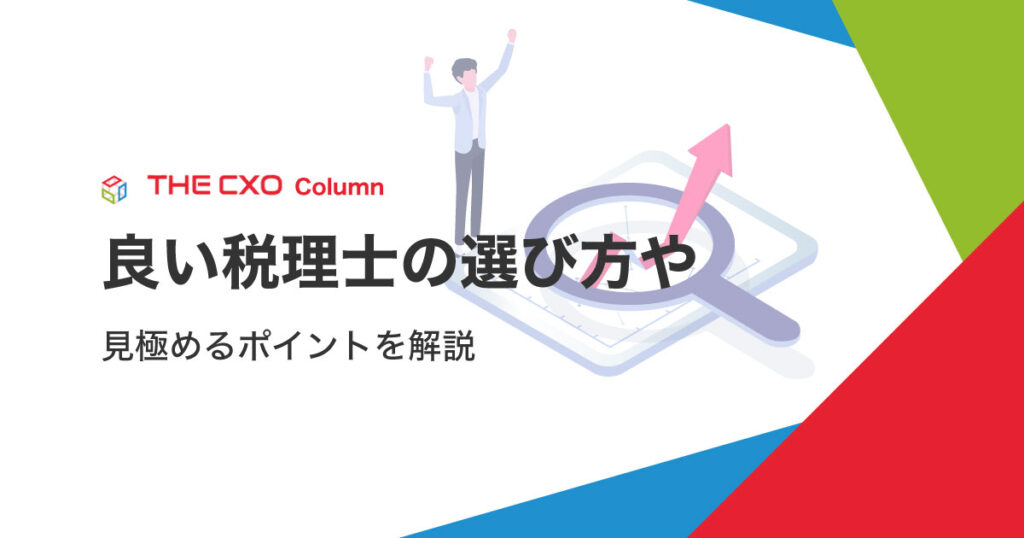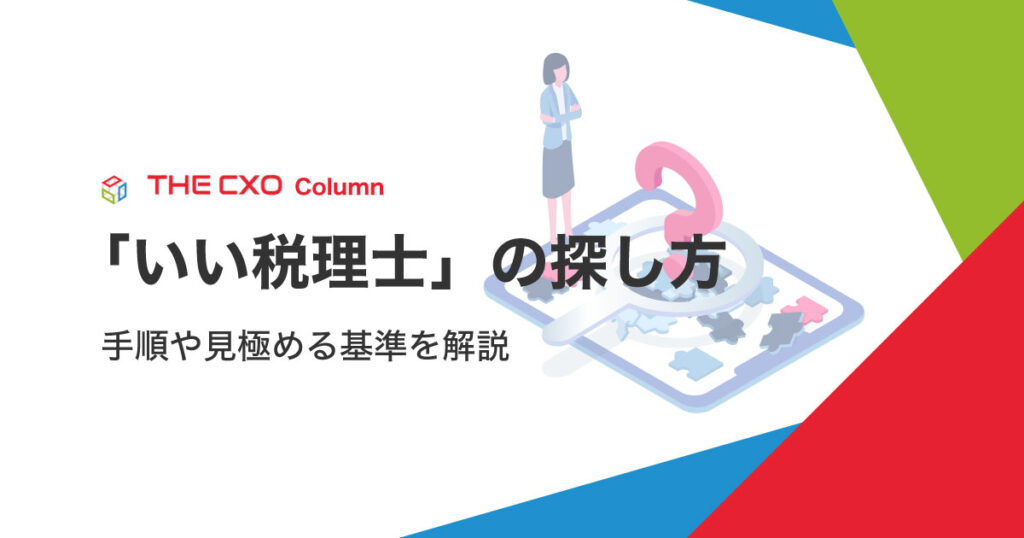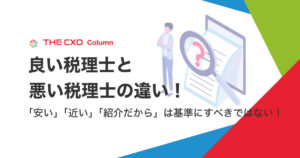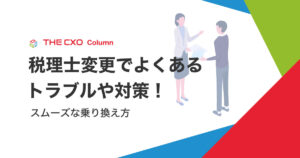税理士を変えたい!変更する際の注意点や新しい税理士の見極め方を解説
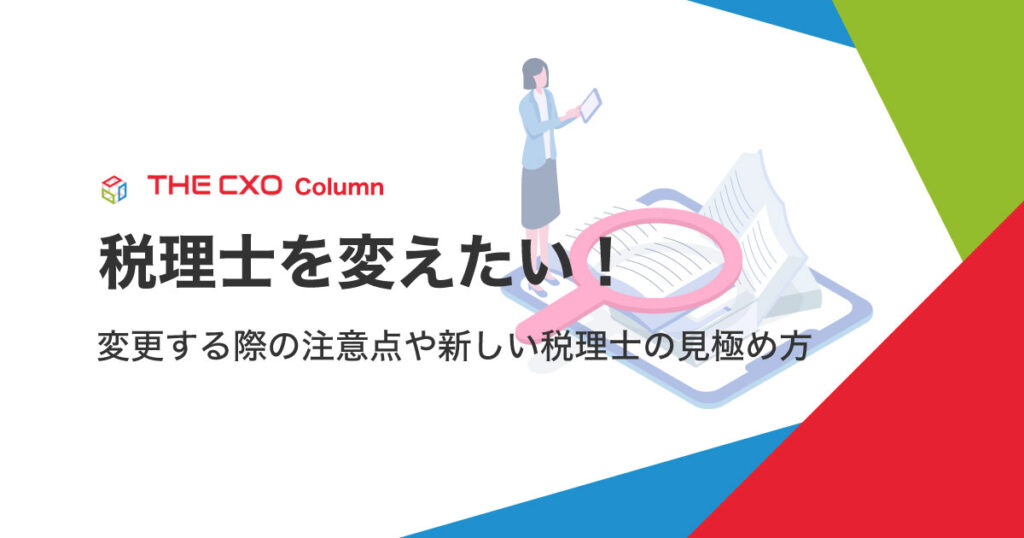
「税理士を変えたい」と思う理由は企業によって異なりますが、少なくとも「税理士を変えたい」という気持ちが芽生えているのなら、すぐに税理士の変更の検討を始めるべきです。
- 先代からの付き合いで変更しづらい
- 税理士の変更によって会社にマイナスな影響がでないか不安
- 友人や知人からの紹介なので変えづらい
など色々なリスクを考えてしまって変更に踏み切れないという方もいらっしゃるでしょう。
しかし、少なくとも今の税理士が自社のニーズや成長フェーズに合っていないからこそ、「変えたい」という気持ちが湧き上がってきている訳です。「変えたい」と思う税理士と付き合い続けていくことには何のメリットもありません。
税理士は企業成長をバックアップしてくれる心強いアドバイザーのような存在です。単なる記帳代行や、決算申告の代行屋さんではありません。
企業の数値化や数値をベースにした改善提案など、税理士の枠を超えてアドバイスできる税理士との出会いによって、企業の成長量、スピードは大きく変わります。
実際に税理士を変えたことにより、一気に企業成長を遂げた企業は数多く存在します。
このように、「もっと企業成長ができる可能性」を止めてまでも、「変えたい」と思う税理士と惰性で付き合い続けるのは、企業にとっても、経営者にとっても、何よりそこで働く社員にとっても不幸な選択といえるでしょう。
だからこそ、「税理士を変えたい」と思ったら、企業や社員の将来のためにも、思い切って税理士の変更の検討に踏み切りましょう。
この記事では、税理士を変える最適なタイミングやメリット、あなたにとって最適な税理士と出会う方法について詳しく解説していきます。
株式会社カタリスタ 代表取締役
THE CXO 株式会社 代表取締役
飯島 彰仁(いいじま あきひと)
Iijima Akihito
経営計画コンサルタント、中小企業の社外CXO。大手会計事務所元代表取締役社長として、同社を年商22億円、従業員数447名の規模にまで成長させた実績を持つ。
これまで3,000社以上の中小企業に対し、財務やマーケティングを通じた経営向上に貢献。
その中で、中小企業の成長のためには、単なる税務処理を超え、経営に深く関与する税理士が必要不可欠であることを痛感。
その経験をもとに、税理士が真の価値を発揮する「社外CXOメソッド」を開発。累計300人以上の税理士に伝授し、「税務の枠を超え、中小企業のあらゆる相談に乗れるパートナー」を養成。
指導した税理士達からは、顧問先の売上向上、利益向上、V字回復や事業改善など成功報告が続々と寄せられている。

- 1. 【結論】税理士を変えたいならすぐ変えてOK!
- 2. 経営者が税理士を変えたいと思う主な理由
- 3. 税理士を変えることで得られる5つのメリット
- 3.1. 積極的な提案がもらえるようになり、経営の質が向上する
- 3.2. 試算表の提出スピードが速くなり、迅速な経営判断が可能になる
- 3.3. 経理の効率化が進み、業務負担が軽減される
- 3.4. 顧問料を見直すことで、コスト削減につながる可能性が高まる
- 3.5. 最新の税制に対応したアドバイスが受けられる
- 4. 税理士を変えたいと思った時に注意すべき点
- 4.1. 良い税理士を見つけるまでにはある程度時間と手間がかかる
- 4.2. 決算の3カ月前からは対応してくれない税理士が多いので注意する
- 4.3. 前任税理士からの引き継ぎは契約解除前にきちんと行う
- 4.4. 税理士に預けている書類はきちんと契約解除前に返してもらう
- 4.5. 契約内容を事前に確認しておく(特に解除に伴う点)
- 4.6. 同じ選び方で税理士を選ばないように注意する
- 5. 税理士変更に成功するためのポイント
- 5.1. 自社の課題を明確にする
- 5.1.1. 顧問料が値上がりする可能性もある
- 5.2. 自社のフェーズを把握する
- 5.2.1. 成長フェーズに合わない税理士を選ぶとどうなる?
- 5.3. 税理士に期待することを整理する
- 5.4. 支払える顧問料を試算する
- 5.5. 税理士の得意分野・得意フェーズをリサーチする
- 6. 税理士選びの決め手は「実際の担当税理士の対応力」!担当税理士本人に会って見極める
- 6.1. なぜ従来の税理士選びは間違っているのか?それは「直に会わない」から
- 6.2. 自分だけの「チェックリスト」で税理士の対応力を判断する
- 7. 税理士を変更するときの具体的な手続きの流れを解説!
- 7.1. ① 現在の顧問税理士との契約内容を確認
- 7.2. ② 事前に新しい税理士を確保
- 7.3. ③ 現在の税理士に解約希望を伝える
- 7.4. ④ 書類の返却と引き継ぎの準備を徹底
- 7.5. ⑤ 新しい税理士との契約を締結
- 8. 税理士に初回相談する前にチェックすべき4つの重要ポイント
- 8.1. 税理士事務所の体制が整っているか
- 8.2. 自分の会社の業界に精通しているか
- 8.3. 直接会ってのコミュニケーションの相性はどうか
- 8.4. クラウド会計や最新税制に対応しているか
- 9. 良い税理士を見つけるならTHE CXOへご相談ください
- 9.1. 当社のマッチングサービスが選ばれる理由
- 10. まずは無料相談を活用し、最適な税理士を見つけよう
【結論】税理士を変えたいならすぐ変えてOK!
「税理士の変更はいつがベストなのか?」という質問をよく聞きますが、結論としては「変えたいと思った時がベストなタイミング」です。
一般的には、以下のようなタイミングが税理士を変えやすいといわれています。
- 法人税申告書を提出した後
- 税務調査が完了した後(修正申告書を提出した後)
- 法人税申告書を提出いた後から次の決算の3ヶ月前
しかし、これはあくまで一般論であり、「この時期であればスムーズに税理士を変えやすい」というだけの話です。上記タイミングから外れていても税理士変更は可能です。
そもそも税理士を変更するのは、今の税理士に何かしらの不満や不信感、頼りなさを感じているからでしょう。
そんな信を置けていない税理士に重要な税務調査の対応や法人税申告を任せていいのでしょうか。
「今の税理士に不満がある」「このままでは経営がうまくいかない」と感じているなら、時期にこだわらずすぐに変更を検討すべきです。
税理士の変更推奨タイミングに該当していなくても、「対応できる税理士が少ない」というだけで税理士の変更はできます。
税理士を変えるべき最適なタイミングとは?失敗しない方法を解説
現在の税理士に対して、不満を感じているものの「本当に変えていいのか?」と迷っていませんか。 税理士の変更は、決して珍しいことではなく、むしろ適切なタイミングで行えば、経営にとってプラスになります。 そもそも、一般的な税理 […]
経営者が税理士を変えたいと思う主な理由
税理士を変えたいと思う理由は企業によってさまざまだと思われます。
一般的には、以下のような理由で税理士変更を検討される企業が多いといえます。
- サービスへの不満(記帳や申告業務をこなすだけで、経営のアドバイスや節税・補助金の活用に関する提案がない、正確性に欠けるなど)
- 価格への不満(顧問料に見合ったサービスを受けられていない)
- 企業のニーズの変化(企業が税理士に対して求めるサポート内容が変わった)
- 税務調査対応への不満(社長の味方になってくれなかった)
- 税理士事務所の体勢の変化(税理士事務所の体勢が変わってしまった)
税理士は、単なる「税務処理の代行者」ではなく、あなたのビジネスを支える重要なパートナーです。
経営に役立つ税理士を選ぶことで、企業の成長スピードは大きく変わります。
税理士への不満がある!違和感を覚えたら取るべき行動とは?
税理士との関係に、次のような不満を感じたことはありませんか? このように、税理士に対する違和感が積み重なり、不信感へとつながるケースは少なくありません。 しかし、税理士への不満をそのまま放置してしまうと、会社の成長に悪影 […]
税理士を変えることで得られる5つのメリット
税理士を変えたいと考えているなら、それは何らかの不満があるからこそです。
しかし、ただ不満を解消するためだけではなく、税理士を変更することで「今よりも良い経営環境を作る」ことができるという点を意識することが大切です。
税理士を変えることで得られる主なメリットは、次の5つです。
- 積極的な提案がもらえるようになり、経営の質が向上する
- 試算表の提出スピードが速くなり、迅速な経営判断が可能になる
- 経理の効率化が進み、業務負担が軽減される
- 顧問料を見直すことで、コスト削減につながる可能性が高まる
- 最新の税制に対応したアドバイスが受けられる
以下からは、税理士を変更することで得られる5つのメリットについて詳しく解説します。
積極的な提案がもらえるようになり、経営の質が向上する
経営のパートナーとなる税理士を選ぶことで、財務状況をもとに具体的なアドバイスを受けられるようになります。
こうした経営アドバイスがないと、たとえば、財務管理が甘くなったことで銀行からの融資審査に落ち、成長のための資金調達に失敗することもあるのです。
節税対策だけでなく、資金繰りの改善や経営戦略のアドバイスを受けることで、会社の成長を加速できます。
試算表の提出スピードが速くなり、迅速な経営判断が可能になる
レスポンスの速い税理士なら、試算表の提出が早まり、リアルタイムで会社の財務状況を把握できます。
たとえば、試算表の提出が遅れると、経営者が会社のお金が足りなくなっていることに気づくのが遅れてしまうことがあります。
試算表を見ないまま経営を続けていると、「売上はあるのに、お金がない」という状況になり、気づいたときには、支払うべきお金が足りなくなってしまうこと(資金ショート)も起こり得るのです。
そうなると、急いで銀行からお金を借りようとしても、審査に時間がかかって間に合わず、従業員への給料が払えなかったり、取引先への支払いが遅れて信用を失ったりすることにつながります。
税理士とともに試算表をきちんと読み取り、資金繰りや投資判断のスピードが上がることで、経営の選択肢は広がっていくことでしょう。
経理の効率化が進み、業務負担が軽減される
最新のクラウド会計に対応している税理士を選べば、経理業務を大幅に効率化できます。
たとえば、経理をすべて手作業で行っていると、仕訳(お金の流れを記録する作業)や領収書の整理に多くの時間がかかり、入力ミスや記帳ミスのリスクも高まります。
最悪の場合、税務署から指摘を受けて追加の税金を支払わなければならなかったり、必要な経費を申告し忘れて余計な出費を招いたりする恐れもあるでしょう。
しかし、クラウド会計を導入すれば、銀行口座やクレジットカードと自動連携して取引を記録できるため、手作業による負担やミスを大幅に減らせます。
リアルタイムで最新の財務状況を把握できるので、資金繰りの見通しが立てやすくなり、経営判断のスピードと正確性も上がるはずです。
ただし、クラウド会計を入れただけでは、必ずしも経理効率が劇的に向上するとは限りません。
会社全体の経理フローがバラバラだったり、「どういう手順で処理するのか」が定まっていなかったりすると、入力ミスや作業の重複がなくならないからです。
経理業務そのものを標準化・簡略化し、「だれが・いつ・どのように処理するのか」というルールをきちんと整備することで、はじめてクラウド会計の恩恵を最大限に活かせます。
また、税理士や経理担当者との役割分担をはっきりさせておくことも重要です。
経営者がどこまで経理業務に携わり、どこから税理士に任せるかをしっかり決めておけば、無駄な作業や二度手間が発生しにくくなります。
たとえば、「領収書は月末にまとめて処理する」のではなく、「発生した時点でリアルタイムにデータを入力する」というルールを設定すれば、作業の負担を分散できます。
ほかにも、「必要最低限のデータ入力は経営者側で行い、煩雑な帳簿付けや月次・年次決算のチェックは税理士が担当する」といった形にすると、本業に集中しながら正確かつ効率的に経理を進められるでしょう。
さらに、請求書発行システムや経費精算アプリなど、会計ソフト以外のツールも活用すれば、経費管理や請求業務を自動化し、より高いレベルの効率化が望めます。
たとえば、領収書の写真をスマートフォンで撮るだけでデータ化し、クラウド会計と連携して仕訳を自動生成するといった仕組みを取り入れれば、経理担当者の手間や入力ミスを一段と減らすことが可能です。
このとき、税理士がきちんとアドバイスや指導を行うことが、経理の効率化を成功させるためのポイントになります。
クラウド会計の導入方法や運用の仕方を誤れば、かえって手間が増えてしまうこともあるため、経験豊富な税理士のサポートや指導は不可欠です。
経理業務を大幅に効率化し、余分な税金の支払いリスクを下げるためにも、クラウド会計に強い税理士の力を借りながら、経理フローの標準化・簡略化、きちんとした役割分担、そしてツールの導入を総合的に検討することをおすすめします。
ミスが多い税理士はどう対処すべき?変更してのリスク回避も検討しよう!
「うちの税理士、よくミスをするけど、これって普通なのか?」と思ったことはありませんか? 経理や税務に関するミスは、企業経営に大きな影響を与える可能性があります。 決算書の誤り、税務申告の不備、税務調査時の指摘事項など、税 […]
顧問料を見直すことで、コスト削減につながる可能性が高まる
現在の税理士に不満があるなら、顧問料とサービス内容が見合っていない可能性が高いです。
税理士を変更することで、同じ費用でもより質の高いサービスを受けられる場合があります。
もし、顧問料が高い割にサービスの質が低い税理士を雇っている場合、本来なら受けられるはずの節税アドバイスや資金繰りのサポートを受けられずに、結果的に多額の税金を無駄に払ってしまっているかもしれません。
たとえば、きちんと税務処理がされなかったがために、気づかないまま数十万円単位の節税のチャンスを逃している可能性もあります。
また、レスポンスが遅い税理士を使い続けていると、経営判断のタイミングを逃し、資金繰りの悪化につながるリスクもあります。
こうした問題は、税理士を変えるだけで簡単に解決できる場合が多いのです。
顧問料の見直しをしないことは、知らないうちに経営の足を引っ張る「見えないコスト」を払い続けることと同じです。
一度じっくりと比較し、適正な価格で最適な税理士を選ぶことが、経営の安定につながります。
最新の税制に対応したアドバイスが受けられる
税制は毎年のように改正されています。
法人税や消費税のルールが変更されたり、新たな補助金や助成金が追加されたりするのです。
こうした情報をうまくキャッチし、企業に合った最適な対策ができる税理士を選ぶことで、経営の安定性が向上します。
たとえば、税制改正に対応できていない税理士を使い続けると、本来なら受けられるはずの節税措置を見逃してしまい、余計な税金を支払ってしまうことがあるのです。
法人税や消費税の控除制度は頻繁に変わるため、数年前と同じやり方を続けていると、知らないうちに税負担が増えてしまっている可能性もあります。
さらに、補助金や助成金の活用に関しても、最新の情報に精通していない税理士の場合、申請できる制度を知らずに機会を逃してしまうことがあります。
たとえば、新設された補助金の申請期限が迫っており、その情報が届かなかったために本来なら数百万円の支援を受けられたはずなのに、申請すらできずに終わってしまうケースもあるのです。
こうしたリスクを防ぐためには、最新の税制に強く、補助金・助成金の活用にも精通した税理士を選ぶことが重要です。
税制に詳しい新しい税理士なら、単なる税務処理だけでなく、経営の幅を広げるアドバイスが受けられ、事業の成長にもつながります。
税理士を変えたいと思った時に注意すべき点
税理士を変更する際には、以下の6つの点に注意しましょう。
- 良い税理士を見つけるまでにはある程度時間と手間がかかる
- 決算の3カ月前からは対応してくれない税理士が多いので注意する
- 前任税理士からの引き継ぎは契約解除前にきちんと行う
- 税理士に預けている書類はきちんと契約解除前に返してもらう
- 契約内容を事前に確認しておく(特に解除に伴う点)
- 同じ選び方で税理士を選ばないように注意する
以下からは、税理士を変更する際に特に注意すべき各ポイントについて解説します。
良い税理士を見つけるまでにはある程度時間と手間がかかる
税理士の変更を考えたとしても、すぐに新しい税理士が見つかるとは限りません。
特に、「経営のパートナー」として信頼できる良い税理士を選ぶのであれば、単なる記帳代行や申告業務をこなすタイプではなく、経営の方向性を理解し、積極的な提案をしてくれるタイプの人材を探す必要があります。
たとえば、すぐに代わりの税理士を決めようと焦るあまり、大手事務所に所属している方を安易に選んでしまったり、同業種の実績が豊富な方を無作為に選んでしまうなど、目に見える条件や肩書き、ブランドに振り回されてしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし、料金や知名度など、表面的に判断しやすい部分だけを見て税理士を選んでしまうと、後で「レスポンスが遅い」「全然訪問してくれない」などの不満につながってしまうケースも多いので、税理士の選び方として避けるべきなのです。
そうならないためにも、新しい税理士を選ぶ際には、以下のポイントを押さえ、ゆっくり時間と手間をかけて選ぶことが重要です。
| 選び方のポイント |
内容 |
|---|---|
| 面談を複数回実施する | 1回の面談だけでは、その税理士の実力や対応力を十分に判断することはできません。 最低でも2~3回は面談を行い、自社の課題や求める役割について細かく話し合うことが大切です。 |
| 実際の担当税理士と直接会う | 会計事務所の規模や評判だけで決めるのは危険です。 実際に業務を担当する税理士と直接話し、レスポンスの速さや提案力、相性を確かめる必要があります。 |
| チェックリストを作成し、比較検討する | 事前に「税理士に求める条件」をリストアップし、各税理士を比較することで、自社に最適な税理士を見つけやすくなります。 税理士に求める条件をはっきりさせるためには、自社課題の洗い出しなどが必要です。 |
焦って決めてしまうと、再び税理士を変えたくなる事態に陥る可能性があります。
時間と手間を惜しまず、慎重に選びましょう。
良い税理士と悪い税理士の違い!「安い」「近い」「紹介だから」は基準にすべきではない!
税理士は企業経営において欠かせない存在です。 しかし、多くの経営者が「とりあえず近いところで探す」「知人に紹介されたから」「料金が安いから」といった理由で税理士を選び、後になって後悔するケースが少なくありません。 「相談 […]
決算の3カ月前からは対応してくれない税理士が多いので注意する
決算期が迫っているタイミングで税理士を変更しようとすると、新しい税理士が引き受けてくれない可能性があります。
特に、決算の直前などギリギリのタイミングでは、既存の税理士から書類を受け取り、短期間で決算処理を完了させなければなりません。
税理士にとって、超短期での決算対応は大きな負担であり、嫌な仕事です。
「1ヶ月弱の期間で、膨大な書類の整理や過去の帳簿の精査をして欲しい」と頼まれたら、どう思うでしょうか。
税理士とはいえ短期間で決算処理するのは極めて難しく、失敗すれば当人の評価も下がってしまうため、対応を断られるケースが多いです。
税理士の変更を考えているなら、決算の3ヶ月以上前から準備を進めるのが理想です。
新しい税理士にスムーズに業務を引き継ぐためにも、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
税理士を変えるべき最適なタイミングとは?失敗しない方法を解説
現在の税理士に対して、不満を感じているものの「本当に変えていいのか?」と迷っていませんか。 税理士の変更は、決して珍しいことではなく、むしろ適切なタイミングで行えば、経営にとってプラスになります。 そもそも、一般的な税理 […]
前任税理士からの引き継ぎは契約解除前にきちんと行う
税理士を変更する際は、現在の税理士からの引き継ぎが重要です。
引き継ぎが不十分だと、過去の会計データや申告書類に不整合が生じ、新しい税理士がスムーズに業務を進められなくなる可能性があります。
たとえば、契約解除後に「あの数字ってどうなっていただろう?」と前任の税理士に聞いても、返信が遅かったり、「契約解除後」ということでちゃんと対応してもらえないことがあるのです。
そのため、特に以下の点に注意しましょう。
- 過去の決算書や申告書をすべて整理しておく
- e-Taxやクラウド会計ソフトのログイン情報を確保する
- 新しい税理士と現行の税理士が連携できるように調整する
税理士変更を円滑に進めるためには、現行の税理士に対して「スムーズな引き継ぎをお願いしたい」と伝え、必要な資料を事前に整理しておくことが大切です。
税理士に預けている書類はきちんと契約解除前に返してもらう
税理士に預けている書類は、契約解除前に必ず返却してもらうようにしましょう。
特に、以下のような重要書類は、新しい税理士との契約後にも必要になるため、抜け漏れがないように管理する必要があります。
- 過去の決算書類
- 法人税・消費税の申告書控え
- 仕訳帳や試算表
- 銀行との融資関連資料
- 税務署・都道府県税事務所への届出書類
契約解除後に書類を請求しても、もう関係ない顧客だからと後回しにされ、スムーズに対応してもらえないケースもあります。
そのため、契約解除前にすべての書類が手元にあることを確認しておくことが重要です。
契約内容を事前に確認しておく(特に解除に伴う点)
税理士との契約を解除する際には、契約の内容をしっかり確かめておきましょう。
契約内容を確認しておかないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
「契約やめます」と伝えればすぐに解約できるわけではなく、契約によっては一定のルールが定められている場合があるのです。
特に、以下のポイントをチェックしましょう。
| 確認すべき項目 |
注意点 |
|---|---|
| 契約解除の通知期限 | 事前に通知しなければならない期間(1ヶ月前、3ヶ月前など)が定められている場合があります。 |
| 違約金の有無 | 一部の税理士事務所では、契約途中での解除に違約金が発生する場合があります。 |
| 未払いの顧問料や追加費用の有無 | 解約時に、精算が必要な費用があるかどうかを確認しておきましょう。 |
たとえば、「途中解約による違約金」が発生する契約になっている場合、知らずに解約すると予想外の費用を請求されることもあります。
特に、年単位の契約をしている場合は、契約期間を満了せずに解除すると残りの月数分の顧問料を一括で請求されるケースもあるのです。
契約解除の条件を事前に確認し、トラブルを防ぐために、可能であれば書面でのやり取りを残しておくことが望ましいです。
口頭でのやり取りだけでは「言った・言わない」のトラブルにつながるため、メールや契約書の写しを保存しておきましょう。
税理士変更でよくあるトラブルや対策・安全な乗り換え方
税理士を変更したいと考えたとき、多くの方が「スムーズに進められるだろう」と思いがちですが、実際にはさまざまなトラブルが発生することがあります。 契約解除をめぐる問題や、必要な書類の返却が滞るケース、さらには新しい税理士と […]
同じ選び方で税理士を選ばないように注意する
税理士を変更する際に、これまでと同じ方法で探してしまうと、結局また合わない税理士を選んでしまう可能性があります。
よくある失敗例として、以下のような選び方が挙げられます。
| 選び方 |
リスク・問題点 |
|---|---|
| ネットの上位表示されている税理士事務所から選ぶ | マーケティングが上手なだけで、実力があるとは限らない |
| 知人の紹介だけで決める | 知人の会社・業態には合っていても、あなたの会社に適しているとは限らない |
| 税理士事務所の規模だけで判断する | 大手事務所でも、担当税理士の実力次第でサービスの質が大きく異なる |
税理士を探す際は、必ず「実際の担当税理士本人」と会い、相性や対応力を確かめることが重要です。
慎重に選ぶことで、あなたの会社に最適な税理士と出会うことができます。
自社と相性の良い税理士の選び方や見極めるポイントを解説
事業を続ける上で、税理士の存在は欠かせません。 しかし、記帳や決算の申告を機械的にこなすだけの税理士に不満を感じている経営者は少なくないでしょう。 税理士の顧問料は、毎月支払っているはずです。 つまり、顧問税理士を抱える […]
税理士変更に成功するためのポイント
税理士を変更する際には、以下の点を意識しましょう。
- 自社の課題を明確にする
- 自社のフェーズを把握する
- 税理士に期待することを整理する
- 税理士の得意分野・得意フェーズをリサーチする
- 税理士選びの決め手は「実際の担当税理士の対応力」!担当税理士の担当者に合って見極める
- 自分だけの「チェックリスト」で税理士の対応力を判断する
単に「今より良さそうな税理士」を探すのではなく、自社の課題をはっきりさせ、それに合った税理士を選ぶことが重要です。
以下からは、税理士変更を成功させるために押さえておくべきポイント、それぞれについて解説します。
自社の課題を明確にする
税理士を選ぶ際には、まず自社の課題を明確にすることが大切です。
税理士の役割は単なる記帳や申告作業だけでなく、経営のサポートを行うことにもあります。
自社の課題を整理することで、税理士に求める役割がはっきりとわかります。
たとえば、以下のような視点で考えてみるとよいでしょう。
- 節税対策が不十分と感じているのか?
- 補助金や助成金の活用についてアドバイスが欲しいのか?
- 資金繰りの相談に乗ってほしいのか?
- クラウド会計に対応している税理士が必要なのか?
- 決算書や試算表の作成スピードを重視したいのか?
もし、「なんとなく評判が良さそうだから」と税理士を選び、いざ契約してみると、以下のように「思っていたサービスと違う」「必要なアドバイスがもらえない」と後悔することがあります。
- 節税対策を期待していたのに、税務申告の代行しかやってもらえなかった
- 補助金の相談をしたかったのに、その分野は対応していないと言われた
- 資金繰りについて相談したかったのに、試算表を出すだけでアドバイスがなかった
このように、自社の課題を整理せずに税理士を選んでしまうと、サービス内容のミスマッチが起こりやすく、結局また税理士を探し直すことになる可能性があります。
自社の課題を明確にすれば、税理士に依頼したいこともはっきりし、ミスマッチを防ぐことができるでしょう。
顧問料が値上がりする可能性もある
税理士を変更する際、新しい税理士の方が顧問料が高くなる可能性もあります。
しかし、単にコストを抑えることだけを考えるのは危険です。
それは、税理士の顧問料が高くなる場合でも、それに見合う価値があるかどうかを検討することが重要だからです。
たとえば、以下のようなケースでは、顧問料が高くてもそれをペイできるほど期末の売上が増加するなど、結果的にメリットが大きくなる可能性があります。
- 税務だけでなく、経営コンサルティングを頼みたい場合
- 節税対策や補助金活用によって、会社の利益が増える場合
- 資金調達や銀行融資のサポートを受けられる場合
安さだけを基準に税理士を選ぶと、「結局何もしてくれない税理士だった」ということにもなりかねません。
会社の成長を見据えたうえで、適正なコストを考えることが大切です。
自社のフェーズを把握する
企業の成長段階によって、ベストな税理士のタイプも変わります。
たとえば、以下のようなポイントを考慮するとよいでしょう。
| 企業の成長フェーズ |
適した税理士のタイプ |
|---|---|
| 創業期 | 創業融資や補助金申請の経験が豊富な税理士 |
| 成長期 | 経営改善や資金繰り、節税対策に強い税理士 |
| 安定期 | 長期的な経営戦略のアドバイスができる税理士 |
| 事業承継・M&Aを検討している場合 | 事業承継や相続税対策に詳しい税理士 |
企業の成長フェーズを把握すれば、「今、自社がどんなサポートを求めているのか?」 がはっきりします。
税理士を選ぶときは、「なんとなく安心できそうだから」という理由ではなく、自社の成長段階に応じた課題を解決できる税理士かどうかを基準にすることが重要です。
自社のフェーズごとにベストな税理士と出会えれば、その時点での経営課題に合ったアドバイスを受けられ、事業の成長スピードを加速させることができます。
成長フェーズに合わない税理士を選ぶとどうなる?
たとえば、創業したばかりの会社が「実績豊富な大手事務所の税理士だから安心」と思って顧問契約したケースを考えてみましょう。
こうした場合は、資金繰りのアドバイスや創業融資のサポートをしてもらえず、結局融資が通らないという結果になってしまうことが考えられます。
このようなケースは、大手税理士事務所は決算業務には強いながらも、創業支援にはあまり対応していないことがあるために起こります。
また、成長期の企業が「節税のアドバイスが欲しい」と思っているのに、創業支援が専門の税理士と契約してしまうと、税金対策が十分に行われず、無駄な税負担が増えてしまうこともあるでしょう。
このように、フェーズに合わない税理士を選ぶと、必要な支援を受けられず、成長のチャンスを逃してしまうことになりかねません。
税理士に期待することを整理する
これまで見てきたように、自社の課題や成長のステップごとに税理士に求める税務サポート、そしてその細かい内容を整理すれば、適切な相手を選びやすくなり、ミスマッチを防げます。
具体的には、以下のような点をリストアップするとよいでしょう。
- 記帳代行だけでなく、経営アドバイスも欲しいのか?
- 税務調査の対応が得意な税理士を選びたいのか?
- 補助金や助成金の情報提供を求めるのか?
- 財務シミュレーションや資金繰りのアドバイスを受けたいのか?
税理士を選ぶときに、「とりあえず知り合いの紹介で決めた」「顧問料が安いから契約した」という理由だけで選んでしまうと、「思っていたサービスが受けられない」「頼んでも対応してくれない」 といったミスマッチが発生することがあります。
ミスマッチにより、たとえば、次のようなトラブルが起こる可能性があります。
- 「経営の相談に乗ってくれると思ったのに、記帳代行(経理の入力作業)しかしてくれない」
- 「税務調査の対策が必要だったのに、その分野の経験が少ない税理士だった」
- 「補助金の活用方法を知りたかったのに、『うちはそういうのは扱っていません』と言われた」
このような事態を防ぐために、税理士に何を期待するのかをはっきりと整理しておきましょう。
支払える顧問料を試算する
税理士の顧問料は、業務内容や会社の規模によって異なります。
事前に顧問料の試算をしておかないと、「契約後に想定以上の費用がかかる」「安さだけで選んだ結果、期待していたサポートが受けられない」 などの問題が起こる可能性があります。
たとえば、「顧問料はなるべく安く抑えたい」と思い、最も安い税理士を選んだとします。
しかし、実際に契約してみると、節税対策の提案もなく、決算や申告を淡々とこなすだけで、税務調査など予想外のイベントが起きた際に対応を求めても「この業務は別料金です」と追加費用を請求されるケースもあります。
逆に、「経営の相談にも乗ってほしい」と思っていたのに、契約した税理士が経営サポートには対応しておらず、結局別のコンサルタントを雇うことになり、二重のコストが発生してしまうことも考えられます。
こうしたトラブルを避けるためには、事前に「税理士に依頼したい業務」と「支払える顧問料」のバランスを考えておくことが重要です。
一般的な税理士の顧問料の目安としては、以下のような金額が考えられます。
| 企業規模 |
月額顧問料の目安 |
|---|---|
| 個人事業主 | 1万~3万円程度 |
| 売上1億円未満の法人 | 3万~5万円程度 |
| 売上1億円以上の法人 | 5万~10万円程度 |
| 上場準備企業 | 10万円以上 |
ただし、単なる記帳や申告業務のみを依頼する場合と、経営アドバイスまで求める場合では、顧問料も変わってきます。
税理士に依頼したい業務内容と、顧問料にかけられる費用を事前に考慮しておきましょう。
税理士の得意分野・得意フェーズをリサーチする
税理士によって得意分野が異なるため、自社のニーズに合った税理士を選ぶことが大切です。
たとえば、以下のような専門分野を持つ税理士がいます。
- スタートアップ支援に強い税理士
- M&A・事業承継に特化した税理士
- 節税対策や資金繰りアドバイスに強い税理士
- 海外取引や国際税務に精通した税理士
- 離婚や相続時の税務に強い税理士
税理士のホームページや過去の実績を確認し、どの分野に強いのかをリサーチすることが重要です。
しかし、ネットの情報だけでは「本当に何が得意なのか」までは分からないため、最終判断はまだしないようにしましょう。
必ず、あなたの税務を実際に担当する税理士本人と直接会って話をし、これまでの対応実績や考え方など、サポート方針を確認することが大切です。
もし、自社のニーズに合わない税理士を選んでしまうと、期待していたサポートを受けられずに後悔することがあります。
たとえば、「経営改善のアドバイスがほしい」と思って税理士を探したのに、契約した税理士が単なる記帳代行専門だったとしたら、どうなるでしょうか。
この場合、いくら相談しても「決算書の作成はできますが、経営アドバイスは対応していません」と言われてしまい、結局別の税理士を探し直すことになり、時間もコストも無駄になります。
このように、税理士の得意分野を事前にリサーチしておかないと、自分の会社に合っていない税理士と契約してしまい、労力を無駄にする ことになりかねません。
税理士選びの決め手は「実際の担当税理士の対応力」!担当税理士本人に会って見極める
税理士を選ぶ際、よくある間違いが「事務所の規模」や「紹介サービスの評価」だけで決めてしまうことです。
しかし、重要なのは 「実際に業務を担当する税理士本人の対応力」 です。
多くの税理士事務所では、営業担当や紹介サービスを通じて契約が決まりますが、実際に業務を担当する税理士に会うことなく契約してしまうケースが少なくありません。
その結果、契約後に「思っていた対応と違う」「連絡が遅い」「相談しづらい」といった問題が起こり、再び税理士を変更せざるを得ない状況になることがあります。
失敗しない税理士選びを実現するために意識すべき視点は、次の3つです。
- なぜ従来の税理士選びは間違っているのか?それは「直に会わない」から
- 大手事務所だからといって安心できるとは限らない
- 自分だけの「チェックリスト」で税理士の対応力を判断する
以下からは、間違った税理士を選ばないための重要なポイント、それぞれについて解説します。
なぜ従来の税理士選びは間違っているのか?それは「直に会わない」から
税理士を探す際、一般的に以下のような方法が利用されますが、それぞれに問題点があります。
| 税理士の探し方 |
問題点 |
|---|---|
| ネット検索 | マーケティングが上手な事務所が上位表示されるだけで、実力とは関係がない点 |
| 税理士紹介サービス | 紹介手数料目的で運営されているため、あなたの会社に本当に合う税理士が選ばれるとは限らない点 |
| 知人・同業者からの紹介 | 紹介元の事業には合っていても、あなたの事業に合うとは限らない点 |
| 税理士会や商工会議所経由 | 担当者同士の縁などでランダムに紹介されることが多く、相性や専門性の確認が難しい点 |
どの方法で税理士を探す場合でも、最も重要なのは 「実際の担当税理士本人と直接会って話をすること」 です。
担当者と対面せずに契約を決めてしまうと、後からミスマッチが発生しやすくなります。
自社に最適な「いい税理士」の探し方とは?手順や見極める基準を解説
税理士を探すとき、多くの方が「ネット検索で上位に出てきた事務所に依頼する」「知人に紹介された税理士をそのまま契約する」といった方法を選ぶのではないでしょうか。 しかし、こうした探し方では本当に自社に合う、いい税理士とは出 […]
自分だけの「チェックリスト」で税理士の対応力を判断する
税理士と初回面談をする際は、以下の表を使ってミスマッチを防ぎましょう。
くれぐれも、「窓口担当」や「営業担当」と話す時に使うのではなく、実際にあなたを担当する予定の税理士との会話で使うようにしてください。
| チェック項目 |
確認するポイント |
|---|---|
| あなたの税務を担当する税理士本人か? | 営業担当ではなく、実際に業務を行う税理士と直接話をする |
| レスポンスの速さはどうか? | 連絡を取った際に、どれくらいのスピードで返信が来るかを確認する |
| 経営方針を理解してくれるか? | 税務だけでなく、経営全般について相談しやすいかどうかを見る |
| 得意分野は何か? | たとえば、節税対策、資金調達、M&Aなど、専門性が自社に合っているかを見る |
| 相談しやすい雰囲気か? | 「何を聞いても嫌な顔をしない」「しっかり説明してくれる」と感じるかを確かめる |
| 料金がサービス内容に見合っているか? | 単なる記帳代行ではなく、経営アドバイスも含まれるかどうかを見る |
| 長期的に信頼できるか? | 今後5~10年、パートナーとして付き合えるかどうかを考える |
このチェックリストは、税理士選びの際に参考となる一般的な基準を示したものですが、最適な税理士像は企業ごとに異なります。
そのため、自社の業種・規模・経営課題に合わせて重要視するポイントを取捨選択し、独自のチェックリストとしてアレンジすることをおすすめします。
たとえば、チェックリストの続きなどに、以下のような追加の視点を加えると、より適切な税理士選びができるでしょう。
| 追加チェック項目例 |
確認するポイント |
|---|---|
| あなたの会社が抱える悩みを解決できそうか? | 現在の税務・経理業務における課題(経費管理、資金繰り、節税対策など)に対して、的確なアドバイスがもらえそうか確認する。 過去に同様のケースを扱った経験があるかを質問し、具体的な解決策を提示できるかを見る。 |
| あなたの業界に関する知見があるか? | 業界特有の税務処理(例:IT業界の研究開発税制、建設業の外注費管理、医療法人の会計処理など)に精通しているかを確認する。 他に同じ業界のクライアントを持っているかを聞き、具体的な事例を尋ねる。 |
| フォロー体制は十分か? | 定期的な面談の頻度や、税務相談に対応できる範囲を確認する。 期限間際で焦らないよう、税務申告や各種手続きをスムーズに進める仕組みが整っているかを聞く。 |
| 会計ソフト・クラウド会計に対応しているか? | 自社が使用している会計ソフトに対応しているか、または移行のサポートをしてくれるかを確認する(クラウド会計に精通している場合、リアルタイムでのデータ共有や業務の効率化が期待できる)。 |
| 税務以外のアドバイスも期待できるか? | 補助金・助成金の活用について情報提供してくれるか。 財務戦略や事業計画についての助言を行ってくれるか。 |
| 契約後の変更や追加対応の柔軟性はあるか? | 業務内容や料金体系の変更が発生した際、どの程度柔軟に対応できるかを確認する。 スポットでの相談が可能か、契約外の業務をどこまでサポートできるかを聞いておく。 |
税理士を変更するときの具体的な手続きの流れを解説!
税理士を変更する際には、スムーズに移行するために以下の手順で進めましょう。
- 現在の顧問税理士との契約内容を確認
- 事前に新しい税理士を確保
- 現在の税理士に解約希望を伝える
- 書類の返却と引き継ぎの準備を徹底
- 新しい税理士との契約を締結
以下からは、こうした税理士変更の具体的な手順について詳しく説明します。
① 現在の顧問税理士との契約内容を確認
税理士との契約を解除する際には、まず現在の契約内容をしっかり確認することが大切です。
税理士契約には、解約の際の条件が記載されていることが多く、違約金が発生するケースもあります。
以下のポイントをチェックしましょう。
- 契約解除の通知期限(例:1ヶ月前、3ヶ月前など)
- 違約金の有無(契約途中の解除で費用が発生するかどうか)
- 未払いの顧問料がないか
- 解約後のサポート有無(決算書や申告書類の作成対応など)
契約書を確認し、不明点があれば現在の税理士に問い合わせることをおすすめします。
② 事前に新しい税理士を確保
現在の税理士を解約する前に、 新しい税理士を確保しておくこと が重要です。
自社に税理士がいない期間があると、思わぬトラブルに巻き込まれるリスクがあります。
たとえば、税理士の契約を解除した後、新しい税理士が決まるまでに数ヶ月かかってしまった場合、その間に税務署から問い合わせが来ても、以下のように誰も対応できないという状況になります。
- 「書類の不備があるので修正申告してください」と税務署から連絡が来たが、対応できる税理士がいない
- 会社の税務処理が遅れ、納税期限を過ぎてしまい、延滞税(期限を過ぎたことによるペナルティ)が発生する
- 新しい税理士が決まっても、前任の税理士からの引き継ぎがないため、最初からすべての書類を整理し直さなければならない
このような問題が起こると、「もっと早く次の税理士を決めておけばよかった…」 と後悔することになります。
新しい税理士を選ぶ際には、前章のチェックリストを使うとともに、以下の点も考慮しましょう。
- 自社の課題を解決できる税理士かどうか
- 顧問料が適正かどうか
- 業務範囲がはっきりと定められているか
契約を締結する前に、面談を行い、具体的なサポート内容や料金について十分に確認してください。
③ 現在の税理士に解約希望を伝える
現在の税理士に解約希望を伝える際の対応も、円満な関係を維持するために重要です。
解約を伝える際のポイントは以下の通りです。
- 契約内容を事前に確認し、ルールに沿って進める
- 感情的にならず、ビジネスライクに伝える
- 「より会社に合った税理士を見つけた」と前向きな理由を伝える
- 必要な書類の引き継ぎをスムーズに進めてもらうよう依頼する
税理士との関係をできる限り円満に解消することで、スムーズな引き継ぎが可能になります。
④ 書類の返却と引き継ぎの準備を徹底
税理士変更の際に最も重要なのが、書類の引き継ぎです。
必要な書類をきちんと回収しないと、新しい税理士が業務をスムーズに引き継ぐことができず、税務処理に支障が出る可能性があります。
新しい税理士が決まってから、「過去の決算書類や税務申告書の控えが手元にない」と気づいた場合、以下のトラブルが起こる可能性があります。
- 「どの税金をいくら払ったのか」が分からず、誤った金額で申告してしまう
- 過去の帳簿データがないため、新しい税理士がゼロから情報を整理し直さなければならず、時間もコストも余計にかかる
- e-Taxのログイン情報が分からず、電子申告ができなくなる
このような状況を防ぐためには、解約前に以下の書類を確実に回収しましょう。
- 過去の決算書類(3~5期分以上)
- 法人税・消費税の申告書控え
- 仕訳帳・試算表・総勘定元帳
- e-Taxのログイン情報・電子申告用の証明書
- クラウド会計・会計ソフトのログイン情報
- 税務署や市区町村への届出書類(青色申告承認申請書など)
特に、e-Taxのログイン情報は重要です。
もし自身でe-Tax情報を把握していない場合、引き継ぎがうまくいかないと、電子申告自体ができなくなる恐れがあるため、確実に確保してください。
⑤ 新しい税理士との契約を締結
新しい税理士と契約する際には、 業務範囲や顧問料をはっきりさせておくことが大切です。
トラブルを防ぐため、以下の点を確認しておきましょう。
- 具体的な業務内容(記帳代行、決算対応、税務調査対応など)
- 月額顧問料と決算報酬の金額
- 契約解除の条件(通知期限や違約金の有無)
- 担当税理士本人が変わらないかどうか
契約書の内容をしっかり確認し、不明点があれば契約前に質問しておくことをおすすめします。
税理士に初回相談する前にチェックすべき4つの重要ポイント
新しい税理士と契約する前には、必ず初回相談を行うべきです。
相談の場では、次のことを確認しましょう。
- 税理士事務所の体制が整っているか
- 自分の会社の業界に精通しているか
- 直接会ってのコミュニケーションの相性はどうか
- クラウド会計や最新税制に対応しているか
通常、初回相談は無料で1時間程度行われることが多いため、事前にしっかり準備しておきましょう。
以下からは、初回相談時にチェックすべきポイントを解説します。
税理士事務所の体制が整っているか
税理士事務所によっては、実際に業務を担当する税理士と会わずに契約が進んでしまうケースがあります。
そのため、 「担当税理士本人」と直接面談できる体制が整っているか を確認することが重要です。
たとえば、税理士事務所の営業担当と話を進め、「経験豊富な税理士が担当します」と説明を受けたとします。
しかし、契約が終わった後で実際に業務を担当するのは、あなたの業界に関する税務経験の浅い税理士だったといったケースが起こり得ます。
こうした問題を防ぐため、面談時には「あなたが私の担当税理士ですか?」と必ず確認し、営業担当ではなく実務担当者と直接話をするようにしましょう。
実務担当者に会わせようとしないような事務所とは、その場で話を打ち切ることも検討してください。
自分の会社の業界に精通しているか
税理士によって、得意とする業種や分野が異なります。
たとえば、製造業、飲食業、IT業界、不動産業など、それぞれの業界に詳しい税理士を選ぶことで、より的確なアドバイスを受けられます。
飲食業の経営者が税理士を選ぶ際、飲食業の経験がない税理士と契約してしまうと、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 飲食業ならではの「原価率の管理」「食材ロスの処理」について、適切なアドバイスがもらえない
- 業界特有の税制優遇(例:飲食業のインボイス制度の影響)を見落とし、余計な税金を払うことになる
- 同業他社の成功事例や最新トレンドを知らず、経営改善の提案が的外れになる
自社の業界に詳しいかどうかを判断するために、以下の質問をしてみるとよいでしょう。
- 「私の業界のクライアントはどのくらいいますか?」
- 「この業界特有の税務リスクはありますか?」
業界特有の知識を持っている税理士なら、的確な回答が返ってくるはずです。
直接会ってのコミュニケーションの相性はどうか
税理士との相性は重要です。
特に、以下のポイントを直接訊いてみましょう。
- あなたは私の税務を担当する税理士本人ですか?
- どこまでサポートしてもらえますか?
- 得意分野は何ですか?
- 業種・事業規模に合ったアドバイスができますか?
- 相談のしやすさは?(どんな連絡手段を用意してくれるか)
- 対応の速さは?
税理士と長期的な関係を築くためには、 「話しやすい」「相談しやすい」 という要素も重要です。
クラウド会計や最新税制に対応しているか
会計ソフトの対応状況もチェックしておくべきポイントです。
たとえば、 「弥生会計」「MFクラウド」「freee」 などのクラウド会計を使いたい場合、その税理士が対応しているかどうかを確認しましょう。
もし、クラウド会計に対応していない税理士を選んでしまうと、以下のような問題が起こる可能性があります。
- データのやり取りが紙ベースになり、請求書や領収書を郵送する手間が増える
- 経理作業を効率化できず、記帳の負担が大きくなる
- リアルタイムでの財務状況を把握できず、資金繰りの判断が遅れる
特に、クラウド会計を導入すると、銀行口座やクレジットカードと連携して自動で仕訳(取引記録の入力)を行えるため、経理作業を大幅に効率化できます。
導入を考えている場合は、事前に「このクラウド会計に対応していますか?」と確認し、対応できる税理士を選びましょう。
クラウド会計ソフト自体の違いはそこまで大きくないため、「自社が今使っている会計ソフトを継続できるか?」 という視点で考えたほうが実務的です。
税理士から別の会計ソフトを勧められた場合でも、納得できる理由があり、しっかりサポートしてもらえるなら、移行を検討する価値があるでしょう。
良い税理士を見つけるならTHE CXOへご相談ください
税理士を探す方法はいくつかありますが、事務所のホームページを見たり、紹介サイトを利用したりするだけでは、本当に相性の良い税理士を見つけるのは難しいのが現実です。
実際に税理士と会って話をすれば、「合う・合わない」「良い・悪い」といった判断はできるでしょう。
しかし、問題はそこにあります。
何度も面談を重ね、手間をかけるほど、時間も労力も削られていく。
そもそも、すべての税理士が最初から対面で話してくれるわけではありません。
中には、初回無料相談を受け付けていない税理士もいるでしょう。
そのため、「誰に会うべきか」を最初に絞り込むことが、税理士選びにおける大きなポイントなのです。
THE CXOでは、あなたの企業の経営状況やあなたの企業が抱える課題に合わせて、最適な税理士だけを厳選して紹介しています。
当社のマッチングサービスが選ばれる理由
- 経験豊富な税理士と直接つながれる:紹介するのは、経験や実績を持ち、実際に対面で話をしやすい税理士のみ!
- 事業規模や業種に合った最適な税理士を紹介:無駄な面談を繰り返さず、最初から「会うべき相手」とつながれる
THE CXOなら、「とりあえず会ってみる」を繰り返すことなく、最適な税理士をスムーズに見つけられます。
経営のパートナーとして長く付き合える税理士をお探しの方は、ぜひご相談ください。
まずは無料相談を活用し、最適な税理士を見つけよう
今回は、税理士を変更する際に知っておくべきポイントや注意点、成功のための具体的な手順について詳しく解説しました。
まずは、自社の課題を明らかにしてください。
自社の課題に合った税理士がどんな人かを考えてみましょう。
税理士は、ただ帳簿をつけたり申告を手伝ったりするだけでなく、会社の経営を支える大切な存在です。
そのため、「安い」「近い」などの理由だけで選ぶのではなく、実際の担当税理士と直接会い、自社の課題を理解してくれるかを見極めることが重要です。
契約前には、業務内容や料金をしっかり確認し、レスポンスの速さや提案力にも注目しましょう。
もし、「今の税理士に不満がある」「経営の相談ができる税理士を探したい」と考えているなら、私たちTHE CXOの無料相談を活用してみてはいかがでしょうか?
THE CXOは、あなたの会社の業種や事業規模に合った最適な税理士を紹介し、実際の担当税理士と直接面談できる仕組みを提供しています。
税理士変更を成功させるためにも、まずは無料相談で最適な税理士を見つけましょう!