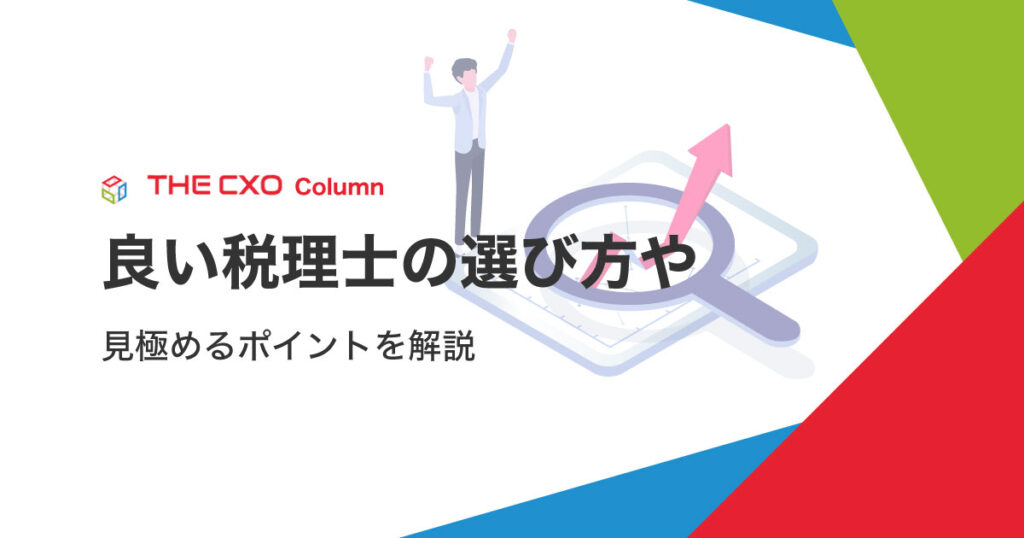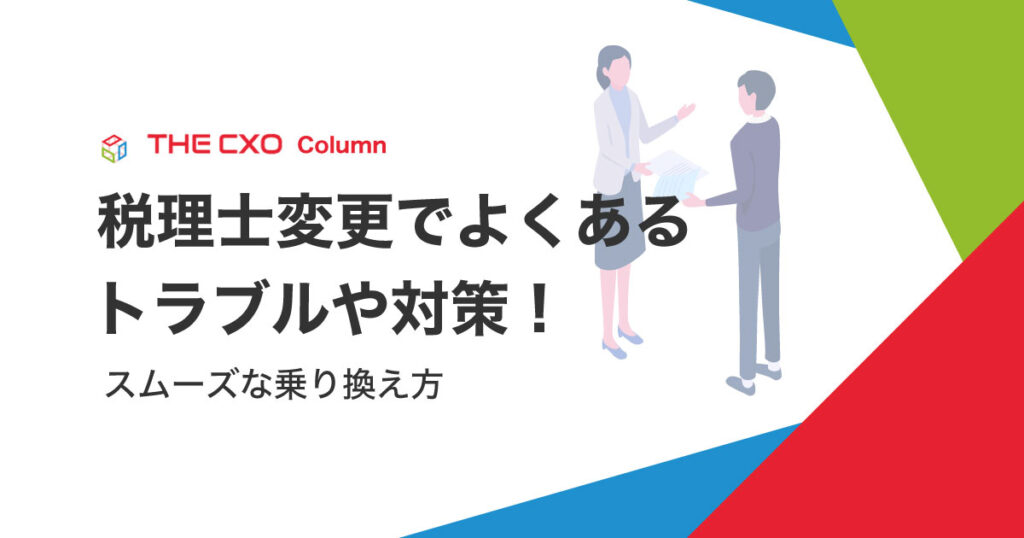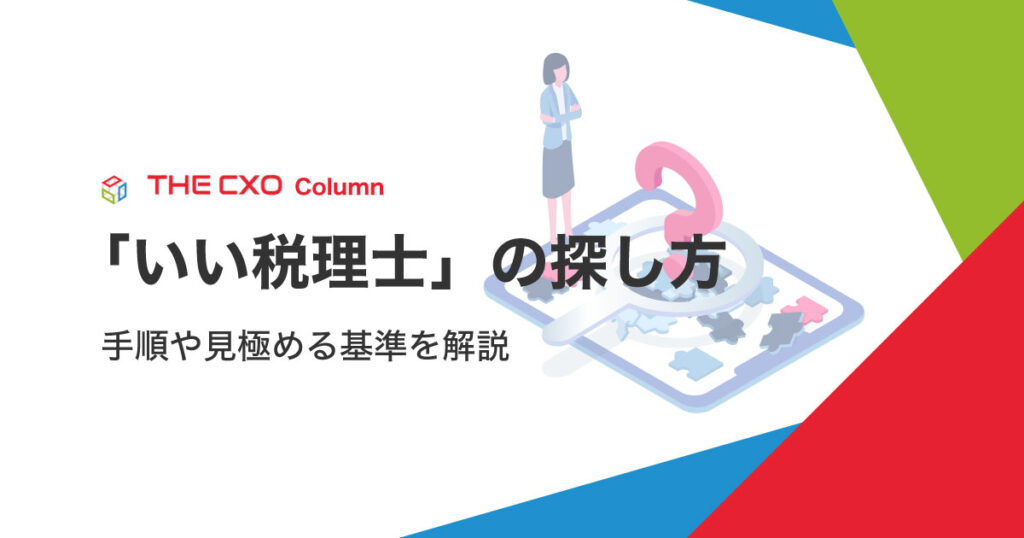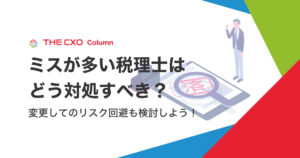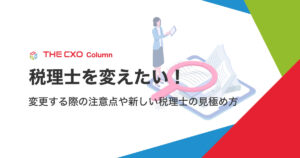良い税理士と悪い税理士の違い!「安い」「近い」「紹介だから」は基準にすべきではない!
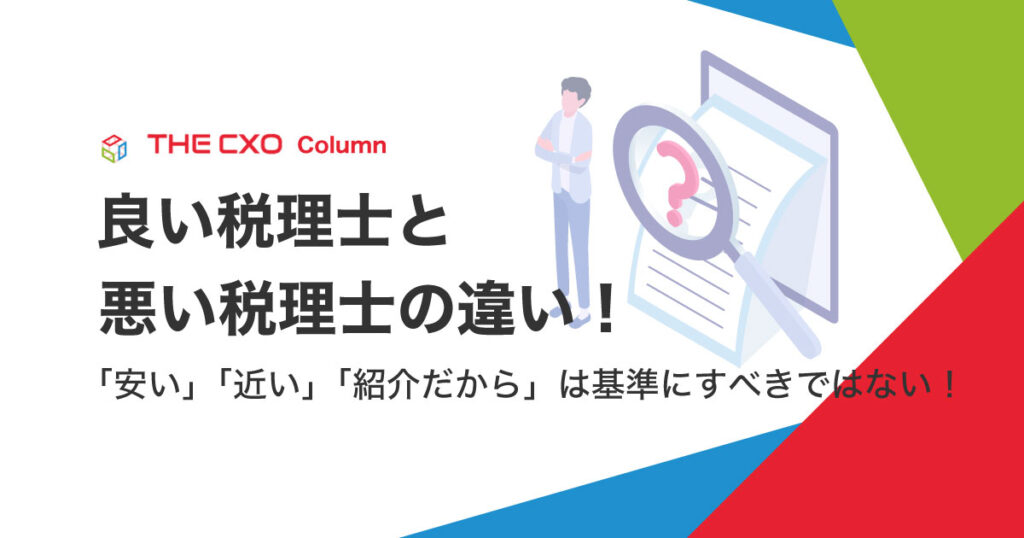
税理士は企業経営において欠かせない存在です。
しかし、多くの経営者が「とりあえず近いところで探す」「知人に紹介されたから」「料金が安いから」といった理由で税理士を選び、後になって後悔するケースが少なくありません。
「相談してもなかなか返事が来ない」「決算や申告はやってくれるけど、経営のアドバイスがない」「毎月顧問料を払っているのに、何もしてくれない」といった不満を感じているなら、それは税理士選びを間違えたサインかもしれません。
本当に良い税理士は、単なる会計処理の担当ではなく、経営のパートナーとして企業の成長を支えてくれます。
一方で、悪い税理士と契約してしまうと、経営の足を引っ張られ、無駄な税金を払ったり、資金繰りに困ったりすることになりかねません。
本記事では、良い税理士と悪い税理士の違いをはっきり示し、「どのような基準で税理士を選べばいいのか」「今の税理士は本当に最適なのか」を徹底解説します。
株式会社カタリスタ 代表取締役
THE CXO 株式会社 代表取締役
飯島 彰仁(いいじま あきひと)
Iijima Akihito
経営計画コンサルタント、中小企業の社外CXO。大手会計事務所元代表取締役社長として、同社を年商22億円、従業員数447名の規模にまで成長させた実績を持つ。
これまで3,000社以上の中小企業に対し、財務やマーケティングを通じた経営向上に貢献。
その中で、中小企業の成長のためには、単なる税務処理を超え、経営に深く関与する税理士が必要不可欠であることを痛感。
その経験をもとに、税理士が真の価値を発揮する「社外CXOメソッド」を開発。累計300人以上の税理士に伝授し、「税務の枠を超え、中小企業のあらゆる相談に乗れるパートナー」を養成。
指導した税理士達からは、顧問先の売上向上、利益向上、V字回復や事業改善など成功報告が続々と寄せられている。

- 1. 企業にとって良い税理士とは「ただの会計処理担当」ではない
- 1.1. 税理士=単なる会計業務担当ではない
- 1.2. 良い税理士がいれば経営が改善する
- 1.3. 節税・記帳代行だけでは不十分、経営アドバイザーとしての役割が重要
- 2. 担当税理士の質がすべてを決める!事務所のブランドに惑わされるな
- 3. 企業にとって本当に必要な良い税理士の6つの特徴
- 3.1. レスポンスが速い
- 3.2. 事務的な対応ではなく、経営アドバイスができる
- 3.3. 自社の所属する業界や企業フェーズに詳しい
- 3.4. 経営の未来をシミュレーションできる
- 3.5. 会計処理だけでなく、利益向上の提案をしてくれる
- 3.6. 税制改正や補助金情報をいち早く提供できる
- 4. 避けるべき悪い税理士の5つの特徴
- 4.1. 高圧的な態度の税理士
- 4.2. 料金が不透明で後から高額請求してくる税理士
- 4.3. 経営に無関心で、ただの作業員になっている税理士
- 4.4. 無駄な保険や投資を強引に売り込む税理士
- 4.5. 会社の業種やフェーズに無関心な税理士
- 5. 従来の税理士の探し方では自社にとって良い税理士に出会いにくい
- 5.1. ネット検索で出てくる税理士はマーケティングが上手なだけ
- 5.2. 税理士協会や商工会議所、銀行の紹介は質が保証されるわけではない
- 5.3. 友人・知人の紹介は自分のビジネスに合うとは限らない
- 5.3.1. 紹介だからといって安易に契約すると断りづらい
- 6. 今の税理士は本当に自社にとって良い税理士?見直すTHE CXO式チェックリスト
- 6.1. こんな不満があれば税理士変更を検討するべき
- 6.2. 税理士変更の前にすべきこと(トラブルを避ける方法)
- 7. 自社にとって良い税理士を選ぶことは、経営を伸ばす最大の投資!
企業にとって良い税理士とは「ただの会計処理担当」ではない
企業経営において税理士の役割は単なる会計処理にとどまりません。
本当に優秀な税理士であれば、会社の成長をサポートし、利益の最大化を手助けしてくれます。
一方で、税理士選びを間違えると、コストがかかるばかりか、経営上の機会損失にもつながるため注意が必要です。
良い税理士を選ぶための基本的な考え方は、次の通りです。
- 税理士=単なる会計業務担当ではない
- 良い税理士がいれば経営が改善する
- 節税・記帳代行だけでは不十分、経営アドバイザーとしての役割が重要
以下からは、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
税理士=単なる会計業務担当ではない
税理士というと、「決算や確定申告を代行してくれる人」というイメージが強いかもしれません。
しかし、企業経営において求められる税理士の役割は、それだけではありません。
たとえば、きちんとした節税対策ができれば、企業のキャッシュフローを改善し、余剰資金を経営戦略に回すことができます。
税務調査に対応するときも、経験豊富な税理士がいれば、資料準備や税務署との交渉をスムーズに進めることができるのです。
もし、税務調査時の対応が悪い税理士だった場合は、書類の準備が不十分で余計な指摘を受け、追加課税や罰則を課される可能性があります。
単に税務申告をするだけの税理士と、経営の視点を持って税務戦略を提案してくれる税理士では、企業にとっての価値が異なります。
税理士を選ぶ際には、「この人に任せれば経営の意思決定がしやすくなるか?」という視点を持つことが重要です。
良い税理士がいれば経営が改善する
優秀な税理士と契約することで、企業の財務状況は良くなります。
たとえば、毎月の試算表をもとに、利益の出方や経費の使い方を分析し、どこを改善すればより効率的に利益を確保できるのかを提案してくれる税理士がいれば、より着実な経営判断ができることでしょう。
また、資金調達の際にも、銀行との交渉をスムーズに進めるためのアドバイスを受けることができます。
金融機関が重視する財務指標や、融資審査でのポイントを理解している税理士がいれば、きちんとしたタイミングで融資を受けることが可能になります。
実際、税理士を変更したことで「無駄な税金を払わずに済んだ」「融資がスムーズに通るようになった」といったケースは珍しくありません。
逆に、アドバイスをしない税理士のもとで経営を続けていると、本来活用できる制度や節税策を見逃し、結果的に経営の足かせになることもあります。
税務アドバイスが不十分な税理士を選んでしまった場合、本来適用できる節税策を知らず、余計な税金を払い続けてしまうかもしれません。
その結果として、同業他社よりも資金の余裕がなくなり、競争力が低下する可能性もあります。
節税・記帳代行だけでは不十分、経営アドバイザーとしての役割が重要
税理士の仕事は「記帳をして申告書を作ること」だけではありません。
むしろ、記帳代行は最低限の業務であり、本当に優秀な税理士は、経営の未来を見据えた経営アドバイザーとしての提案を行います。
税理士としての資格を取得できた方なのであれば、本来誰もがそのようなコンサル能力も持っているはずなのです。
それなのに、「記帳代行しかしませんよ、アドバイスする時間なんてないですし」という税理士の方を見かけることもあるでしょう。
その方は多くの顧客に記帳代行のサービスを提供する、薄利多売の経営方針が自分に合っていると自覚されているのかもしれません。
この場合、税理士自身に向いたビジネススタイルが記帳代行であったということであり、それはそれで悪いことではありません。
しかし、企業経営の観点から見ると、単なる記帳代行だけでは不十分であり、財務戦略や資金繰りのアドバイスまで行える税理士のほうが、長期的に見て、より価値のある存在となります。
たとえば、事業拡大を計画している企業なら、税負担を考慮しながら資金繰りをどうするか、どのタイミングで設備投資を行うべきかといったアドバイスが必要です。
こうした視点を持たない税理士と契約していると、単に「今年の税金がいくらか」という話しかできず、経営の方向性を誤ることになりかねません。
また、税制改正や補助金制度の変化に対応できる税理士であることも重要です。
たとえば、事業再構築補助金や雇用関連の助成金など、企業が活用できる制度はいくつもありますが、そうした助成金をしっかりと案内し、活用方法を提案できる税理士であれば、企業は財務面でメリットを得ることができます。
担当税理士の質がすべてを決める!事務所のブランドに惑わされるな
税理士を探す際に、以下のように考えてしまうことはありませんか?
- 「大手の会計事務所だから、安心」
- 「老舗の税理士事務所だから信頼できる」
このように考えてしまうのは危険です。
企業経営にとって本当に重要なのは、どこの事務所に所属している税理士かではなく、「『担当税理士』が誰か」という点です。
会計事務所の中には、新規顧客を獲得する際に営業担当や受付スタッフが面談を行い、実際の税務業務は別の税理士に振り分けるケースが少なくありません。
つまり、企業側が「この事務所のこの人は、サービスが良さそうだから依頼しよう」と思って契約しても、実際に担当する税理士が誰なのか、どのような人物なのかを事前に確認できないまま契約が進んでしまう、ということが、残念ながら昨今の税理士契約の現状です。
この仕組みが問題なのは、事務所のネームバリューに安心して契約した結果、経験の浅い税理士や、専門外の税理士、対応が遅い税理士に当たる可能性があることです。
仮に、税務の知識が不足していたり、レスポンスが遅かったりする税理士が担当になった場合、その影響を受けるのはあなたと企業経営そのものです。
そのため、税理士を選ぶ際には「どの事務所に依頼するか」よりも「誰が担当するのか」を最優先で考えることが大切です。
契約を決める前に、実際に担当する税理士と面談し、自社の経営課題について相談したときにどのような回答をするのかを確認することをおすすめします。
もし「この税理士なら信頼できそうだ」と感じたら契約を検討し、「話をしてもピンとこない」「質問に対する回答が曖昧」「経営に対する関心が低い」と感じた場合は、他の税理士を探したほうが良いでしょう。
税理士の選び方や見極めの基準については、以下の記事でも詳しく取り扱っているので、ぜひ参照してみてください。
自社と相性の良い税理士の選び方や見極めるポイントを解説
事業を続ける上で、税理士の存在は欠かせません。 しかし、記帳や決算の申告を機械的にこなすだけの税理士に不満を感じている経営者は少なくないでしょう。 税理士の顧問料は、毎月支払っているはずです。 つまり、顧問税理士を抱える […]
企業にとって本当に必要な良い税理士の6つの特徴
税理士によって得意分野や対応力には差があります。
本当に優れた税理士は、単なる会計処理の代行だけでなく、企業の成長を支えるパートナーとしての役割を果たします。
良い税理士の特徴として、特に重要なポイントは次の6つです。
- レスポンスが速い
- 事務的な対応ではなく、経営アドバイスができる
- 自社の所属する業界やフェーズに詳しい
- 経営の未来をシミュレーションできる
- 会計処理だけでなく、利益向上の提案をしてくれる
- 税制改正や補助金情報をいち早く提供できる
以下からは、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
レスポンスが速い
税理士の対応スピードは、経営判断のタイミングに直結します。
たとえば、急ぎの融資相談や税務署からの問い合わせに対し、税理士の返答が遅いと、企業の意思決定が遅れ、機会損失につながります。
税理士の中には、1週間以上も返事をくれない、あるいは何度催促しても対応が遅れるケースもあります。
どんなに能力が高くても、なぜか返事だけはできないという特性を持った方は残念ながらどの業界にも稀にいます。
しかも、こういった特性はその方の人格、性格に根源的に直結していることが多く、「顧客に迷惑をかける」という重大な過ちを犯してなお、その程度では矯正できない、つまり永久に治らないケースが多いものです。
しかしながら、その能力を見込んで返事の遅さを許してしまうのであれば、ただの飼い殺し。
あなたの会社がその税理士を、何の見返りもなく養っているだけです。
つまり、顧問料をそのままごみ箱に投げ捨てているも同然です。
こうした税理士を顧問にしていると、あなたの会社の資金繰りや税務リスクに対応しきれなくなる可能性が高くなります。
早い段階で、運が悪かったと見切りをつけ、顧問契約を解約しましょう。
良い税理士は、緊急時には迅速に対応し、日常的な相談にも遅れずに対応します。
「この税理士なら、すぐに相談できる」という安心感があるかどうかが重要です。
事務的な対応ではなく、経営アドバイスができる
単に帳簿を整理して申告書を作るだけの税理士では、企業の成長には貢献できません。
優れた税理士は、企業の財務状況を分析し、具体的な経営アドバイスを提供できます。
たとえば、利益が増えているのにキャッシュが残らない場合、単なる会計処理ではなく「どの部分の支出を見直すべきか」「資金繰りをどう改善するか」といった視点で提案できる税理士であれば、経営の改善が期待できるはず。
また、節税対策だけでなく、事業戦略と税務のバランスを考えた「活きた税務アドバイス」を受けられるかどうかも重要です。
たとえば、事業拡大のために設備投資を検討している場合、補助金を活用できるのか、減価償却のタイミングをどう調整するべきかといった具体的なアドバイスをくれる税理士がいれば、経営判断の精度が上がります。
自社の所属する業界や企業フェーズに詳しい
業界ごとに会計や税務のポイントは異なります。
たとえば、飲食業ではキャッシュフロー管理が重要になります。
IT企業では研究開発費の税制優遇を最大限に活用することが必要です。
飲食業は現金収入が多い一方で、仕入れや人件費の支払いは後払いになることが多いため、資金の流れを把握できないと「月末の支払いができない!」と慌てて高金利の短期融資に頼るはめになります。
また、IT企業の研究開発費の税制優遇について無知な税理士を雇っていると、本来なら受けられる「研究開発税制による法人税の控除」や「ベンチャー企業向けの補助金」の申請を逃すことになります。
結果として、競合他社は税金を抑えながら開発投資を増やし、新技術で市場を席巻していくのに、自社だけが資金不足で開発スピードが落ち、競争力を失うという事態が起こりかねません。
また、企業の成長フェーズによっても、求められる税理士のスキルは違います。
創業期には資金調達に強い税理士が必要ですが、成長期には財務戦略や節税対策を提案できる税理士が必要です。
安定期や成熟期、事業承継を考えるフェーズでは、相続やM&Aに詳しい税理士が必要になるでしょう。
事業承継のタイミングで相続税やM&Aに詳しくない税理士に任せると、深刻な財務上の問題が発生する可能性があります。
たとえば、親族への事業承継において、自社株の評価額をきちんと算出できなければ、相続税の負担が想定以上に膨らみ、資金繰りが圧迫されることがあります。
結果として、経営資源の確保が難しくなり、最悪の場合、会社を売らなければならなくなることも。
相続対策を誤ると、多額の税金が発生し、経営の継続が困難になる事態も十分に起こりえるのです。
もし現在の税理士が、自社の業界や事業フェーズに関心を持っておらず、一般的な対応しかしてくれないのであれば、他の税理士を探したほうがよいかもしれません。
経営の未来をシミュレーションできる
税理士の役割は、過去の数字を整理することだけではありません。
本当に経営に貢献できる税理士であれば、企業の未来を見据えたシミュレーションを行い、具体的なアドバイスができます。
たとえば、売上が順調に伸びている会社であれば、「3年後にどの程度の税負担が発生するのか」「利益を最大化しつつ適正な納税を行うために、今のうちに何をすべきか」といったシミュレーションができるはずです。
もし、このような予測ができず、単に「今年の税金はこれくらいです」と伝えるだけの税理士であれば、経営者にとっては不十分です。
良い税理士であれば、売上が伸びている企業に対し、3年後・5年後の税負担を試算し、今から準備すべき対策を提案できるでしょう。
たとえば、設備投資を計画的に行い、減価償却費を活用した税負担の分散をアドバイスするなどです。
また、役員報酬の適正額を設定し、法人税と所得税のバランスを最適化していけば、不要な税負担を減らしながら利益を最大化する方法を具体的に示すことも可能です。
事業の拡大や設備投資、雇用の増加などに関する具体的な数字を示しながら、経営者と一緒に未来を考えられる税理士こそが、企業にとって価値のあるパートナーといえます。
また、金融機関から融資を受ける際も、シミュレーション能力の高い税理士がいれば心強いです。
金融機関から融資を受ける際には、単に「事業計画書を作ればいい」というわけではありません。
良い税理士なら、銀行が重視する財務指標(自己資本比率、営業利益率、EBITDAなど)を分析し、決算書のどの部分を改善すれば審査に通りやすくなるかを提案します。
たとえば、「このままの決算書では貸借対照表の自己資本比率が低く見えるため、短期借入を長期借入に切り替えることで、銀行の評価を向上させることができる」といった実践的なアドバイスなどが考えられます。
また、信用格付けを意識し、金融機関に対するプレゼン資料の作成支援や、融資担当者との交渉ポイントを指導することもできるはず。
金融機関がどのような指標を重視するのか、決算書のどの数字を改善すれば融資の審査が通りやすくなるのかを具体的に示してくれる税理士がいると、資金調達の成功率が変わります。
会計処理だけでなく、利益向上の提案をしてくれる
税理士が企業に対して「もっと利益を増やすために、こうしたほうがいい」と具体的なアドバイスをしてくれることは少なくありません。
しかし、実際には「経費を抑えましょう」といった当たり前のことしか言わない税理士も多いのが現状です。
もし、こうした税理士と契約していた場合、企業は売上向上のチャンスを逃し、「利益は伸び悩んでいるのに、なぜか節税だけは頑張っている」という本末転倒な状況に陥ることがあります。
たとえば、飲食店の経営者が税理士に「利益を増やすには人件費を削減すべき」と言われたとします。
確かに、人件費を減らせば短期的には支出が抑えられます。
しかし、スタッフが足りなくなれば注文が遅れ、接客の質が落ち、お客さんの満足度が下がる可能性があります。
すると口コミやレビューにネガティブなことが投稿され、リピーターが減り、新しいお客さんも増えにくくなり、売上が下がって結局利益も減るという悪循環に陥ることがあるのです。
売上が落ちれば、いくら人件費を削っても経営が苦しくなることは明らかです。
特に、もともと利益率が低い業種では、支出を抑えるだけで経営を立て直すのは難しく、売上を増やす視点がなければ、会社の成長は止まってしまいます。
本当に役立つ税理士なら、単に「人件費を減らしましょう」ではなく、メニューの価格を見直して利益率を上げる方法や、混雑時の効率を上げるための働き方の工夫など、売上を増やすための提案をしてくれるはずです。
また、補助金や助成金を活用して人件費の負担を軽くする方法もあります。
こうした知識を持つ税理士なら、会社の利益を本当に増やす手伝いができるのです。
さらに、税理士の知識を活かせば、資金調達の幅も広がります。
たとえば、製造業の会社が設備投資を考えているとき、「この機械は補助金の対象なので、半分の費用で導入できます」といった提案ができる税理士なら、経営者にとって大きなメリットになります。
国や自治体が出している補助金の中には、会社の成長に役立つものが多くあります。
しかし、「申請の期限が過ぎていた」「こういう制度があると知らなかった」と後で後悔するケースも少なくありません。
こうしたチャンスを逃さないためにも、最新情報を常に把握し、経営者に有益な提案ができる税理士を選ぶことが大切です。
税制改正や補助金情報をいち早く提供できる
税制は毎年のように改正され、改正に伴って企業が対応すべき内容も変化します。
たとえば、インボイス制度や電子帳簿保存法の導入など、新しい制度が施行されるたびに、企業の会計・税務のやり方も見直さなければなりません。
もし税理士がこうした税制度変更に詳しくなく、対応が遅れると、企業は思わぬ税務リスクを抱えることになります。
たとえば、インボイス制度にしっかり対応しなかった場合、取引先が「この会社の請求書は仕入税額控除の対象にならない」と判断し、取引を見直される可能性があります。
「今後は他社と取引する」と言われたら、売上が減ることになりかねません。
また、税制改正に伴う節税策を知らなかった場合、本来受けられるはずの税制優遇を逃してしまうリスクがあります。
たとえば、新しい税制で「特定の設備投資を行った企業に対し、税額控除が適用される」と決まっていたとしましょう。
もし企業がこの情報を知らずに設備を導入してしまえば、本来なら数百万円の税額控除を受けられたはずなのに、何も知らずに全額支払うといったことになります。
これは、税制優遇を知らないだけで大損してしまった状態です。
税制対応を怠った場合に起こりうる最悪のケースとして、電子帳簿保存法の対応ミスがあります。
本来、電子データで保存すべき書類をきちんと管理していなかった場合、税務調査で指摘を受け、過去数年分の帳簿が無効とされ、多額の追徴課税が発生する可能性があるのです。
さらに、税務調査の結果が悪いと、金融機関からの信用も低下し、融資審査に影響することもあります。
優れた税理士なら、こうした税制改正の最新情報を常に把握し、企業が損をしないように正確なアドバイスを行います。
たとえば、インボイス制度の影響を事前に説明し、「取引先との契約を見直しましょう」「今のうちに適格請求書の発行登録を済ませておきましょう」といった提案をしてくれる税理士なら、企業は余計なトラブルを回避できます。
また、税制優遇の情報を定期的に提供し、「来年度はこの投資をすれば税額控除を受けられる」「この助成金を活用すれば、実質負担が半額になる」といった提案をしてくれる税理士がいれば、経営の選択肢も広がります。
単に「決算書を作るだけ」の税理士ではなく、企業の税務リスクを未然に防ぎ、経営にプラスをもたらす提案をしてくれる税理士こそ、本当に価値のあるパートナーといえるでしょう。
避けるべき悪い税理士の5つの特徴
良い税理士が企業の成長を支える存在であるのに対し、次のような「悪い税理士」と契約してしまうと、経営の足を引っ張られることになります。
- 高圧的な態度の税理士
- 料金が不透明で後から高額請求してくる税理士
- 経営に無関心で、ただの作業員になっている税理士
- 無駄な保険や投資を強引に売り込む税理士
- 会社の業種やフェーズに無関心な税理士
税理士を変更したいと考えている経営者の多くは、「税理士に不満があるが、具体的に何が問題なのかわからない」と感じています。
しかし、税理士の対応に問題があると、経営判断の遅れや無駄な税金の支払い、場合によっては税務リスクの増加につながるため、はっきりした基準を自分の中に持ち、相手を見極めることが大切です。
以下からは、絶対に避けるべき悪い税理士それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
高圧的な態度の税理士
税理士は経営者のパートナーであり、良い関係を築けることが重要です。
しかし、一部の税理士は、専門知識を武器にして経営者に対して高圧的な態度を取ることがあります。
たとえば、「こんなことも知らないんですか?」と見下すような発言をしたり、相談しても「それは無理ですね」と突き放すような対応をしたりする税理士がいます。
上記は単純にパワーハラスメントなどで税理士会などに届け出るべきでもありますが、こうした税理士と関わっていると、経営者は税務について質問しづらくなり、本来得られるはずのアドバイスを受けられないままになってしまいます。
本来、税理士は経営者の立場に寄り添い、最適な選択肢を提示するべき存在です。
あなたに税務の知識がないことを指摘してくるような税理士ではなく、「こうすれば解決できますよ」と前向きな提案ができる税理士を選ぶことが重要です。
料金が不透明で後から高額請求してくる税理士
税理士と契約する際には、顧問料の金額や、追加料金が発生するケースについてはっきりさせておくことが重要です。
しかし、中には契約時に料金をはっきり提示せず、後から高額な請求をしてくる税理士もいます。
たとえば、通常の顧問契約には含まれない業務について、事前の説明もなく追加料金を請求するケースがあります。
「決算申告は別料金」「税務調査対応は顧問契約に含まれない」といった条件が後から発覚し、想定以上の費用がかかることになるのです。
こうしたトラブルを避けるためには、契約前に「顧問料に含まれる業務」と「追加料金が発生する業務」をしっかり確認しておく必要があります。
経営に無関心で、ただの作業員になっている税理士
税理士の中には、記帳や申告を機械的にこなすだけで、経営のアドバイスを全くしない方もいます。
こうした税理士と契約していると、単なる会計処理の代行に高額な顧問料を支払っているだけの状態になってしまいます。
たとえば、経営の相談を持ちかけても「うちは記帳と申告だけです」と言われたり、節税や資金繰りの相談をしても具体的な提案が一切なかったりするケースなどです。
このような税理士は、企業の成長をサポートする存在ではなく、単なる「経理業務の外注先」に過ぎません。
本当に役立つ税理士は、企業の現状を分析し、経営者にとって有益なアドバイスができます。
現状の税理士に「決算書の数字を説明するだけ」「経営のアドバイスが一切ない」といった不満を感じているなら、早めに別の税理士を検討するべきです。
税理士変更でよくあるトラブルや対策・安全な乗り換え方
税理士を変更したいと考えたとき、多くの方が「スムーズに進められるだろう」と思いがちですが、実際にはさまざまなトラブルが発生することがあります。 契約解除をめぐる問題や、必要な書類の返却が滞るケース、さらには新しい税理士と […]
無駄な保険や投資を強引に売り込む税理士
一部の税理士は、生命保険や投資商品を販売することで手数料を得ています。
こうした税理士は、本来の税務サポートとは関係のない金融商品を強引に勧めてくることがあります。
経営者にとってこのような税理士は、ただの時間を無駄にする要因です。
税理士側は、過去に縁があった金融業者などとタッグを組み、別にあなたにとって何の役にも立たない金融商品を勧める「営業役」に成り下がっており、当来の自分の価値を下げているだけでしかありません。
たとえば、「節税対策として生命保険に加入しましょう」と提案されたものの、実際には税金の削減効果が小さく、解約すると大きな損失が出るような商品を契約させられるケースがあります。
また、「この不動産投資をすれば節税になります」と言われて購入したものの、収益性が低く、最終的に負担が増える結果になったという事例もあります。
本来、税理士の役割は「税務の専門家」として企業の利益を守ることです。
もし「この保険に入るといいですよ」「この投資をすれば節税になります」としつこく勧誘してくる税理士がいたら、本当に企業のためを思っているのかを疑い、質問の場を設けたり、別の税理士をセカンドオピニオンとして活用すべきです。
会社の業種やフェーズに無関心な税理士
企業の業種や成長フェーズによって、税務のポイントは異なります。
しかし、すべての税理士が業界ごとの特性を理解しているわけではありません。
たとえば、スタートアップ企業であれば、資金調達や補助金の活用が重要になりますが、そうした知識がない税理士ではきちんとしたサポートができません。
また、小売業では「棚卸資産の評価」が利益に影響します。
売れ残った在庫の計算方法によって税額が変わるのですが、業界知識のない税理士が雑に処理すると、「まだ売れていない在庫なのに、すでに売れたものとして利益を計上してしまう」ということがあります。
つまり、実際には現金が増えていないのに税金だけが高くなり、最悪の場合、税金を払うために銀行から借金しなければならないといった事態を招くこともあります。
さらに、美容院や整骨院などのサービス業では、税務調査でお客さんから一時的に預かる「預かり金」が問題になることがあります。
本来、こうした業種では「売上」と「預かり金」を区別して記帳しなければならないのですが、業界に詳しくない税理士が「すべて売上として計上する」という誤った処理をしてしまうと、税務調査で過大な売上を申告していたとみなされ、数年分の修正申告を求められ、多額の追徴課税が発生することがあります。
こうしたリスクを避けるためにも、税理士を選ぶ際には「この業界の税務に詳しいか?」「自社のビジネスモデルを理解しているか?」を必ず確認することが重要です。
業界特有の会計ルールを無視し、経営の実態を考えない税理士は、会社の発展を妨げるどころか、大きな損失を招くリスクさえあります。
手遅れになる前に、あなたにふさわしい税理士を見つけることが必要です。
自社と相性の良い税理士の選び方や見極めるポイントを解説
事業を続ける上で、税理士の存在は欠かせません。 しかし、記帳や決算の申告を機械的にこなすだけの税理士に不満を感じている経営者は少なくないでしょう。 税理士の顧問料は、毎月支払っているはずです。 つまり、顧問税理士を抱える […]
従来の税理士の探し方では自社にとって良い税理士に出会いにくい
税理士を探す際、多くの企業が「ネット検索」「税理士協会や商工会議所の紹介」「知人の紹介」といった方法を取ります。
自社に最適な「いい税理士」の探し方とは?手順や見極める基準を解説
税理士を探すとき、多くの方が「ネット検索で上位に出てきた事務所に依頼する」「知人に紹介された税理士をそのまま契約する」といった方法を選ぶのではないでしょうか。 しかし、こうした探し方では本当に自社に合う、いい税理士とは出 […]
しかし、こうした方法では本当に自社に合った税理士に出会えるとは限りません。
なぜなら、こうした手法にはそれぞれ、次のような落とし穴があるからです。
- ネット検索で出てくる税理士はマーケティングが上手なだけ
- 税理士協会や商工会議所、銀行の紹介は質が保証されるわけではない
- 友人・知人の紹介は自分のビジネスに合うとは限らない
以下から、それぞれの問題点について詳しく見ていきましょう。
ネット検索で出てくる税理士はマーケティングが上手なだけ
現在、多くの税理士事務所が自社のホームページを持ち、SEO対策を行っています。
そのため、検索結果の上位に表示される税理士事務所は、必ずしも「実力のある税理士」ではなく、「マーケティングが上手な税理士」である可能性が高いです。
たとえば、「税理士 ○○市」などのキーワードで検索すると、多くの税理士事務所のホームページが表示されます。
しかし、その中には「問い合わせは多いが、実際の業務は未経験の若手税理士が対応する」「広告費をかけて集客しているだけで、サービスの質は一般的」といった事務所も含まれています。
また、ネット上の口コミにも注意が必要です。
実際に利用した顧客の声ではなく、業者が書いた「やらせレビュー」が混じっていることも多いため、口コミだけを鵜呑みにするのは危険です。
ちなみに、嘘の情報が書かれたレビューは、優良であるように見せかけ、誤認を招いたとして景品表示法違反となるおそれがあります。
もしネット検索で税理士を探す場合は、ホームページの情報だけで判断せず、実際に面談をして「どのようなサポートが受けられるのか」「担当税理士が誰なのか」を確認することが重要です。
税理士協会や商工会議所、銀行の紹介は質が保証されるわけではない
税理士協会や商工会議所、銀行経由で税理士を紹介してもらう方法もあります。
しかし、こうした紹介で巡り合った相手が「本当に良い税理士」とは限らない点には注意が必要です。
たとえば、税理士協会や商工会議所の紹介では、地域の税理士が順番に紹介されるケースが多く、企業のニーズに最適な税理士が選ばれるわけではありません。
紹介された税理士が「ただ近いから」「会員だから」という理由だけで選ばれている可能性もあります。
また、銀行から紹介される税理士も注意が必要です。
銀行は融資審査や取引の関係で提携税理士を抱えていることが多いですが、紹介された税理士が企業の成長を本当に支えてくれるかどうかは別問題です。
たとえば、会社が本来は金利の低い他行の融資を検討していたのに、「今の銀行との関係が悪くなるかもしれないので、融資は変えないほうがいいですよ」とアドバイスされた結果、数年間にわたり高い金利を支払い続ける、ということも起こり得ます。
紹介制度を利用する場合は、「なぜこの税理士が紹介されたのか」を必ず確認し、実際に話をして相性を確かめることが大切です。
友人・知人の紹介は自分のビジネスに合うとは限らない
知人や経営者仲間から税理士を紹介してもらうのも、よくある方法です。
しかし、近い方からの紹介にもリスクがあります。
たとえば、紹介してくれた知人の会社と自社の業種や規模が異なる場合、その税理士が必ずしも自社に適しているとは限りません。
知人の会社では問題なく対応していたとしても、自社の業務に必要な専門知識が不足しているケースもあります。
紹介してくれた方の会社と、あなたの会社は全くの別物です。
税理士を選ぶ際には、「紹介だから安心」という思い込みを捨て、必ず自分の目で確認することが重要です。
さらに、紹介で契約すると「合わなかったから断る」という判断がしづらくなるデメリットもあります。
以下から、詳しく見てみましょう。
紹介だからといって安易に契約すると断りづらい
知人や取引先からの紹介で税理士と契約すると、「思っていたサービスと違った」「経営方針に合わない」と感じても、断りづらい状況になりがちです。
たとえば、紹介された税理士が「話しやすいが、経営のアドバイスはほとんどしてくれない」という場合でも、紹介者との関係を考えると解約しづらくなります。
その結果、不満を抱えたまま契約を続けることになり、企業の成長を妨げる要因になりかねません。
また、紹介された税理士に対して「知人の会社では対応が良かったのに、うちでは対応が雑」という思いを持ってしまうケースもあります。
これは、税理士側が「紹介者の顔を立てているだけで、新規顧客に対してはそこまで手厚いサービスを提供しない」といったことが原因として考えられます。
もし紹介で税理士を探す場合でも、必ず「どのようなサポートが受けられるのか」「自社に合った税理士なのか」を慎重に確認することが重要です。
今の税理士は本当に自社にとって良い税理士?見直すTHE CXO式チェックリスト
現在の税理士に不満を感じている場合、漠然と「このままでいいのか?」と悩んでいるだけでは問題は解決しません。
税理士の変更を検討すべきかどうかを判断するには、具体的な基準を持つことが重要です。
ここでは、「このような不満がある場合、税理士を変えたほうがいい」というチェックポイントを整理しました。
また、税理士を変更する前にやるべきことについても解説します。
以下からは、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
こんな不満があれば税理士変更を検討するべき
税理士の仕事は単なる記帳や申告だけではなく、企業の成長をサポートすることにもあります。
しかし、次のような不満がある場合は、現在の税理士が自社にとって最適ではない可能性があります。
| No. |
チェック項目 |
概要 |
|---|---|---|
| 1 | レスポンスが遅い | 税理士に問い合わせをしても返信が遅く、何度も催促しなければならない場合、経営判断に悪影響を及ぼします。特に、資金調達や税務署対応など緊急なケースでは、迅速に対応できなければ意味がありません。 |
| 2 | アドバイスの質が低い | 決算書の作成や税務申告はしてくれるものの、経営のアドバイスがほとんどない税理士は、「単なる作業員」となっている可能性があります。節税対策や資金繰りの相談をしても、具体的な提案がない場合は要注意です。 |
| 3 | 料金体系が不透明 | 契約時にわかりやすい料金の説明がなく、後から追加請求が発生する税理士には注意が必要です。「決算料は別料金」「税務調査対応は顧問契約に含まれない」など、契約時に知らされていなかった費用がかかる場合は、契約を見直したほうがよいでしょう。 |
| 4 | 会社の成長に対応できていない | 企業の成長フェーズによって、求められる税理士のスキルは変わります。創業期には資金調達や補助金の活用に詳しい税理士、成長期には財務戦略や節税対策を提案できる税理士が必要です。現在の税理士が自社の成長に対応できていないと感じたら、別の税理士を検討する時期かもしれません。 |
税理士変更の前にすべきこと(トラブルを避ける方法)
税理士を変更する際には、以下の表のようにいくつかのポイントを押さえておくことで、スムーズに移行することができます。
| No. |
チェック項目 |
説明 |
|---|---|---|
| 1 | まずは現在の税理士と改善交渉してみる | 不満がある場合、すぐに変更せず、一度話し合ってみるのも選択肢のひとつ。「メールの返信が遅い」「経営アドバイスが少ない」などの問題を率直に相談すれば、改善されることもあります。 |
| 2 | セカンドオピニオンを活用する | いきなり変更するのが不安なら、他の税理士に相談して意見を聞いてみるとよい。「今の税理士は一般的に見てどうなのか?」「もっと良い税理士はいるのか?」を客観的に判断する材料になります。 |
| 3 | 顧問契約の解約手続きと引き継ぎ準備を確認する | 契約内容を確認し、スムーズに解約できるように準備を進める。特に、決算前に解約すると混乱する可能性があるため、ベストなタイミングを図ることも重要。新しい税理士が引き継ぎやすいように必要な書類も整理しておく。 |
特に、現在の税理士との関係を悪化させずに進めることが重要です。
自社にとって良い税理士を選ぶことは、経営を伸ばす最大の投資!
今回は、良い税理士と悪い税理士の違いについて詳しく解説しました。
税理士を選ぶ際、単に「安い」「近い」「紹介だから」という理由で決めてしまうと、経営の足を引っ張る結果になりかねません。
むしろ、自社に最適な税理士を見極め、ベストなサポートを受けることは、企業の成長にとって欠かせない投資です。
税理士は単なる節税対策のためではなく、企業の利益を最大化する存在です。
単に経費を増やして税金を減らすのではなく、資金繰りや売上向上まで考えたアドバイスができる税理士を選ぶべきです。
また、税理士の費用は「コスト」ではなく「投資」と考える必要があります。
顧問料が安い税理士は多くの企業を抱えているため、十分なサポートが受けられないこともあります。
逆に、少し高くても経営戦略や資金調達に強い税理士なら、長期的に見て利益を伸ばせる可能性があります。
本当に価値のある税理士を見極めるには、複数の税理士と話し、自社の経営課題を相談したうえで、しっかりしたアドバイスをくれるかを確認しましょう。
税理士は経営の未来を左右する存在です。今の税理士が最適かどうかを一度見直し、必要ならより良い税理士を探し、企業の成長につなげていきましょう。